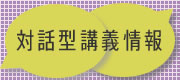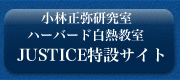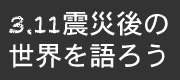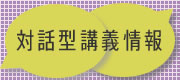

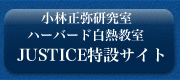

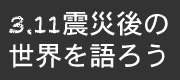
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« グローカル公共哲学の射程-新自由主義に抗して | Home | 日韓公共哲学共同研究会所感 »
Posted: admin on 10:35 pm | 書籍・雑誌情報(Books, Journals, Magazines), 論文・書評・所感など
「社会諸科学の哲学・政治哲学・公共哲学――『政治的恩顧主義(クライエンテリズム)論』の方法論的背景とその展開」 小林正弥
一.日本行動主義的政治科学批判――経験的批判と方法論的批判
拙著『政治的恩顧主義(クライエンテリズム) 論――日本政治研究序説』(に始まる研究)は、その副題が現しているように、日本政治の構造を的確に把握する事の出来るような概念ないし理論を構築する事を目的としている。その際に、批判の対象として最も意識したものが、研究に着手した当時に華々しく登場して来た実証主義的政治科学、殊にいわゆる日本多元主義論であった。この派の機関紙のような雑誌『レヴァイアサン』が発刊された一九八七年には、私は東京大学法学部の助手二年目であり、相対的には抵抗力のある筈の、その研究機関に於いてさえ、周囲の若手研究者には、これが時代の潮流(トレンド)であるかのように感じ、その流れに掉さして業績を上げていこうと思う人が少なくなかった。この派の思想的・方法的破綻が明らかになったように思われる今となっては、隔世の感があるが、それが当時の漠たる雰囲気であり、そして今でもなおこの呪縛は学界に残存している。
日本多元主義論の批判として、まず第一に考えられるのは、勿論、その理論的内容を日本政治の現実に即して「経験的」に批判する事である。この必要性は論を俟たないし、筆者自身も、余力が有れば今後本格的に行ってみたいと思っている重要な課題である。ただ、助手時代の筆者にとって、周囲の殆ど抗し難いような雰囲気の中で、この――自称する所の――「新しい流れ」に対抗する為には、それだけでは十分ではないと思われた。何故なら、仮に経験的な形で反論を試みたにしても、「実証主義」の方法論の華麗さに幻惑されている限り、その的呪縛から解放されるのは容易ではない、と想像されたからである。経験的反論の結果は、恐らく(丸山眞男以来の)戦後日本政治学の基本的な主張(例えば、官僚制支配や民主政治の形骸化など)を――正当にも――確認する事になるであろうが、方法論の呪縛に一度囚われている人にとっては、自らの研究の礎を失ってしまう恐怖に晒されるが故に、その結果を虚心坦懐に見つめて反省する事は容易ではないだろうからである。現に、新藤宗幸・山口二郎両教授らは、筆者に比して現実的・経験的な角度から多元主義論を批判され、筆者も大いに声援を送っているのであるが、それでもなお実証主義的政治科学は一時猖獗を極め、――山口氏が徒労感を学会などで洩らされる程――なかなか収まる気配を見せなかったのである。
そこで、(生来哲学的・抽象的思考に向きがちな)筆者は、このような経験的批判を補完するものとして、実証主義の哲学的・方法論的批判を行う事を志した。拙著で書いたのは、そのごく一部でしかないが、このような関心に基づく方法論的・哲学的観点は、拙著の重要な骨格を成している。(丸山眞男ら戦後政治学の洞察の再定式化による新世紀政治学の構想など)日本政治学との関連については、拙著の「序章」及び「終わりに」に書いたので、以下では、より普遍的な意義を持つこれらの側面について、回顧的な説明を行ってみよう。
二.原論文における方法論――微視的(ミクロ)原子論/巨視的(マクロ)全体論と「本来の政治学」
戦後政治学ないし社会科学に関心を持つ筆者は、例えば、マックス・ヴェーバーらの方法論ないし方法論争に元来興味を感じており、行動主義的政治科学の批判にあたって、このような方法論争に遡って考えるのは、ある意味では当然の成り行きであった。実際、海外でも、例えばガネルやリッチの仕事に明らかなように、筆者の言う「アメリカ政治科学の自己省察」(拙著二六一頁注一〇参照)に於いて、哲学や社会学の成果が実証主義的政治科学批判の文脈で用いられる事は、決して珍しい事ではなく、むしろ当然であろう。
しかしながら、海外の常識は必ずしも日本の常識ではなく、何よりも日本政治自体の経験的分析という、手短な具体的成果を追い求めていた日本政治学者の多くにとって、これは迂遠で不毛な抽象的方法談義と見えたかもしれない。これに輪をかけたのが、筆者の恩顧主義(クライエンテリズム)研究の方法である。
比較政治学の研究としては、(拙著で「対関係交換理論」と呼んだ)通説に従って恩顧主義(クライエンテリズム)ないし庇護者(パトロン)―随従者(クライアント) の概念を理解し、すぐ経験的研究に入るのが、普通であろう。派閥・後援会・政治的腐敗の研究や、日本のそれらの現象と他の地域に於けるそれらを比較するなど、為すべき主題は山のように有るし、研究に着手した当時は、筆者も、このような視点に立脚した歴史政治学的・比較政治学的研究を行う事を考えていたのである。ところが、拙著第3章で詳しく扱ったアイゼンシュタット=ロニガーの恩顧主義(クライエンテリズム) 論を本格的に考察する内に、このような見通しは根本的に変更され、かなり抽象度の高い概念ないし理論の研究を中心にする事になった。アイゼンシュタット自身も、高名な社会学者にふさわしく、六十年代以来、様々な方法論的考察を積み重ね、ヴェーバー以来の社会学の伝統を彼なりに発展させて、恩顧主義(クライエンテリズム)研究を重要な媒介として「比較文明的接近法(アプローチ)」に到達していたのである。そこで、筆者の恩顧主義(クライエンテリズム)研究は、これをまず方法論的に吟味し、その弱点を克服する形で進む事になった。
ごく簡単に述べれば、通説の対関係交換理論が、社会学の交換理論に依拠しており、「各人が自己利益の最大化を目指す」という原子論的・個人主義的方法論に立脚しているのに対し、アイゼンシュタットらは、構造主義の代表者・レヴィーストロースの概念(「一般交換」)を導入し、全体論的・集合主義的方法論に立脚した巨視的(マクロ)恩顧主義(クライエンテリズム)論を――筆者が主理論と呼ぶ――基軸として提起した。もっとも、アイゼンシュタットらは、対関係交換理論のような微視的(ミクロ)・原子論的理論を完全に放棄したわけではなく、これも「副理論」として存在し、不十分な形ながら双方が共存している。そこで、筆者は、レヴィーストロース自身の「一般交換/限定交換」の概念に遡って恩顧主義(クライエンテリズム)を――「垂直的限定交換」として――規定しつつ、巨視的(マクロ)・全体論的な方法論と微視的(ミクロ)・原子論的な方法論とを統合ないし総合しようと企図したのである。これは、レヴィーストロースの構造主義を、その難点を補う形で再構成したものであるが故に、その方法論を「新構造主義」と呼び、筆者の理論を「新構造主義的恩顧主義(クライエンテリズム)論」と命名したのである。
また、「恩顧主義(クライエンテリズム) の概念が、まず人類学で形成され、社会学や政治学・歴史学などに導入された」という学説史を反映して、筆者の研究も、これらの諸領域の研究を広く学際的に扱う事になった。そして、実は、ギリシャ以来の古典的政治学に於いては、このような学際的考察がむしろ当然であった事に鑑みて、このような政治学を「本来の政治学」と呼んだのである。単に対象領域の大きさに着目して言えば、通常の政治学が「小政治学」であるのに対し、「本来の政治学」は「大政治学」という事になるであろう。さらに、このような古典的政治学を本格的に確立する為には、単に方法論というに止まらず、哲学的基礎が必要であると考え、原論文では、注にそれを「哲学編」として予示しておいた。
これらの結果、多くの政治学者達とは、学問的背景ないし対象の点で乖離が生まれる事になったように思われる。実際、『国家学会雑誌』に掲載された原論文は、明確な批判を受ける事も殆ど無かった反面、「難解」という評を受ける事が多く、その論旨を十分に理解して頂く事が少なかったような気がする。そして、筆者自身も、右のような方向は、――世界的にも類例の無い――筆者自身が開発しつつある理論的・方法論的フロンティアであると思っていたが故に、そのような事情を余り意に介する事も無く、研究の完成を目指して勤しんでいたのであった。
三.ケンブリッジの反実証主義的学際性――ギデンズ、ダン、スキナーの横顔
実は、このような理論的展開は、「別に海外の動向から直接学んだわけではなく、世界でも独創的な試みである」と自負していた為に、筆者は、自らの理論の完成の方に精力を傾注しており、海外に行って学びたいとは余り思っていなかった。そもそも、日本行動主義的政治科学は、アメリカに留学した若手政治学者が、その実証主義的方法を日本政治分析に無反省・無邪気に適用した為に生まれたものであり、その様子を見るにつけ、筆者は、丸山眞男以来の日本政治学の伝統や洞察を踏まえて、日本政治の考察に適した――「どこの国の借り物でもない、みずからの地盤に根を下した政治学」(丸山眞男[i])の――理論ないし概念を形成する事を志していた。その結果、(正に日本政治研究の為の必要性に基づいて着想した)普遍的な理論的アイデアを豊富に得る事が出来て、その実現に多大な時間を要するのに、海外に行って時間を費やすのが勿体無く思えたのである。こうして、筆者は、三二歳まで海外に行った事は全くなく、簡単な英会話すら試みた事が無いような状況であった。これは、今日では、むしろ珍しい方であろう。
然るに、その完成作業には予想外の時間を要し、まだ完成させていないにも拘らず、周囲の状況や薦めもあって、一九九五―九七年にケンブリッジ大学社会政治学部に客員研究員(後半は同時にセルウィン・コレッジの準フェロー)として海外研修に行く機会を得た。ケンブリッジ大学を選んだのは、アメリカ政治科学とは異なった政治学の姿が、イギリス、殊に古典的な学問の伝統が強いオックスブリッジに存在するのではないか、と漠然と期待したからである。この期待は裏切られず、例えば社会政治学部でも、素朴な行動主義・実証主義には批判的な人が多く、(ロック研究などで著名な)政治理論の泰斗ジョン・ダン教授John Dunn)に代表されるような伝統的な学風が健在であると共に、現存する世界一の社会学者アンソニー・ギデンズ教授(Anthony Giddens)が一年目にはまだおられ、フランクフルト学派・フーコーらポスト構造主義・現代言語哲学・解釈学などの、多様な新しい潮流の影響も強かった。将来世代国際財団・将来世代総合研究所の依頼で、両氏らの協力の下に、「自己と将来世代」についての国際会議(ケンブリッジ将来世代フォーラム、一九九六年一一月十二―一四日)を開催してその成果を英国で出版する[ii]など、書き出せば思い出は尽きないが、ここでは割愛して、話題を方法論に絞ろう。
筆者は、ギデンズ、ダンら社会政治学部の講義は勿論の事ながら、哲学・歴史・古典・科学哲学・自然科学・神学などの様々な学部の講義やゼミに、2年間の間毎日数時間づつ意欲的に参加した。おそらく学生時代より沢山の講義を集中的に聴講したのではないかと思う。政治に於ける「理解」を主題に掲げるダン教授の講義(「政治の理解」)は、イギリス人にも聴き取り難いという修飾的な英語を駆使するものながら、学識の深さを感じさせる重厚なものであった。これとは対照的に、(メモすら全く持たずに話す)ギデンズ教授の語り口は軽やかで明快であり、(マルクスやヴェーバーから始まって二十世紀の社会思想の諸潮流を包括的に描き出す)その講義(「社会理論の発展」、後半はJ.トンプソン博士John B. Thompson)は、思想を生き生きと鮮やかに描き出す点に於いて、講義自体が卓越した芸術作品の如き美しさを湛えていた。また、(歴史学部に於ける)クェンティン・スキナー教授(Quentin Skinner)の講義(「自由の観念――ホッブズからT.H.グリーン」)[iii]は、極めて鋭利な分析と(自由に対して)迸る道徳的情熱が印象的で、圧巻であった。それは、(筆者が極僅かに耳にした事のある)丸山眞男の語り口を髣髴とさせるものであり、東西の極めて優れた政治思想史家の間の類似性は、非常に印象的であった。これらの偉大な学者のいずれもが、素朴な実証主義には批判的で、かつ学際的であった。ダン教授にしても、著名な政治思想史に加えて、革命(同名の講義も存在)やアフリカ政治などについての比較政治学的研究も公刊しておられ、この点を聞いた所、そのような学際性を自明視しておられたし、スキナー教授の有名な思想史方法論はコリングウッドらの哲学の刺激を受けているし、さらにギデンズ教授に至っては、殆どあらゆる現代哲学・社会科学の動向を踏まえて独自の理論を構築しておられるので、その学際性は改めて述べるまでもない。
組織的にも、社会政治学部自体が、社会学・政治学・社会心理学・社会人類学などの多領域を含んでいるが、これらの講義に加えて、他学部の講義を自由に聴講する事が出来たのは、筆者にとって非常に有益であった。ここでは一々書ききれないが、特に印象に残ったものとして、他に、ジョナサン・スコット(Jonathan Scott, 歴史、「古典的共和主義」)、M.バーニヤート(Myles Burnyeat,古典、プラトン)やB.ウォルディ(B. B. Wardy,同上)、マイケル・レッドヘッド(Michael Redhead, 科学哲学、量子論の哲学、素粒子論の哲学等)、ロス・ハリソン(Ross Harrison, 哲学、平等等)、E.T.オルソン(Eric T. Olson, 哲学、人格的同一性)などの各氏の講義を挙げておこう。この内の何人かの著作は、邦訳なども刊行されていて、日本でも著名である。また、スキナーやダンによる有名なセミナー(「政治思想と知性の歴史」)を始め、様々なセミナーや講演が催され、筆者も、ハーバーマス、ローティ、D.ルイス、D.M.アームストロング、R.ドーキンスらの話を聴く事が出来た。これも、ケンブリッジならではの恩恵であろう。
前述のように、既に論文で多様な分野の文献を読んでいたのだが、日本では学部間で「蛸壺」的(丸山)な状況が存在し、他分野の研究者と稔りある会話を直接する機会がそれまで殆ど無かったので、ケンブリッジで自由に他領域の専門家の講義やセミナーを聞き、質問などによって自分の理解を確かめるのが非常に楽しかった。これを通じて、筆者は、(それまで文献によってのみ得ていた)これらの分野についての自分の知識が正確であり、論文での論述が決して的外れではない、という確信を得る事が出来た。他領域については、それまで、書物を通じての、いわば独学で、いかに文献を読んではいても自分の知識について完全な確信を持ち得なかったので、生き生きした会話によって、右の感触を得る事が出来たのは、筆者にとって、非常に大きな意味を持つ事であった。このような学際的な交流が可能になったのは、ケンブリッジの学者の教養や視野の広さと共に、学部とコレッジとの二重のシステムなどに負う所が大きいであろう。我国と比べて、この学際的な知的環境を羨ましく思うと共に、それを何らかの形で導入できないかと思った次第である。
四.「社会諸科学の哲学」と「政治哲学」との邂逅――ケンブリッジでの発見
のみならず、筆者は、これらの講義の中から、今後の研究にとって決定的に重要と思われる二つの領域を発見した。それは、いずれも、(フランクフルト学派の批判的研究者である)レイモンド・ゴイス博士(Raymond Geuss)[iv]が講義されていた「社会諸科学の哲学」と「政治哲学」である。ゴイス博士(当時社会政治学部、後、哲学部)は、おそらくアメリカから来られた(元コロンビア大学教授)為もあって、私のような異邦人にも殊に親切で、ギデンズ教授らと共に学期始めのパーティーでお会いして以来、非常にお世話になった。氏は、例えば、イギリス人にも難解な英語を駆使するダン教授と、セミナーを一緒に開催し、ダン教授と学生との間を媒介しておられたように、とても親切で優れた教育者である。
筆者がゴイス教授と親交を持つ事が出来たのは、氏のこのような人格による所が預かって大きいが、先の二領域の発見は、それとは一応独立した、純粋に学問的な事柄である。まず、筆者がケンブリッジで始めて聞いた講義の一つが若いパトリック・バエルト博士(Patrick Baert)[v]による「社会諸科学の哲学への歴史的入門」であり、バエルト博士は、「実証主義→ポパーら→クーン→バスカールらの批判的実在論(critical realism)」というような筋立てで短期の講義をされた。筆者が批判的実在論の存在を知ったのは、この講義によってである。もともと科学哲学に興味を持っていた筆者は、この講義に触発されて、その後、マイケル・レッドヘッド教授やJ.バターフィールド博士(Jeremy Butterfield)の科学哲学の講義に出席し、さらにゴイス博士の講義「社会諸科学の哲学に於ける諸論点」に参加したのであった。
ゴイス博士は、まず十九世紀以来の通説的見解(Received View)を①統一科学②自然科学の優位③経験的偏向(バイアス)④ 事実と価値の区別、と整理された上で、その統一科学の発想に対して、19世紀末以来、異論が生じ、自然科学と社会科学の二元性を主張する考え方(解釈学や新カント派)、さらには逆に人間科学・社会科学の側から科学の統一性を主張する考え方(ガダマーら)が現れた、という全体的な構図を示された。その上で、通説的見解について、自然科学的な法則性・説明・予測などの考え方や、それに基づく研究方法、例えば観察、一般化ないし帰納、仮設―演繹的方法、実験などを説明され、(これらが社会科学にも成立すると見倣す)通説的見解の中に含まれるものとして、実証主義(コントら)や論理実証主義を説明され、例えば、その法則―演繹的モデルなどに対する批判を説明された。そして、これに対抗する「意味」に着目する考え方として、①大陸の解釈学(ディルタイら旧解釈学と、ガダマーら新解釈学)、②行為の合理性・理由への着目(アンスコームやデヴィッドソン)、③ヴェーバー、④発話行為論(オースティンやスキナー)、〔⑤ ヴィットゲンシュタイン〕を挙げられた。最後に、この二つを超える考え方として、――批判理論の研究者らしく――(外在的・内在的)批判の観念に簡単に言及し、(意味への着目が陥りがちな)相対主義について説明を加えられた。
筆者にとって極めて啓発的だったのは、ゴイス博士自身の結論以上に、「社会諸科学の哲学」という領域ないし科目が、このように確立している事実を知った事であった。これこそ、筆者が原論文執筆時に試行錯誤しながら、方法論ないし「哲学編」という用語によって表そうとしていた内容と、大きく重なるものだったからである。いわば、それまで筆者が日本で各領域の文献を調べ、それぞれの領域に断片的に存在する情報を集めながら模索していた主題が、ケンブリッジでは既に体系的に講義されていた事を知った訳であり、自分が単独で追求してきた主題が既に重要なものとして確立している事実を知った事は、大きな喜びであった。筆者が、この学問領域を帰国後に紹介・導入したいと考えたのは、改めて述べるまでもない。
そこで、筆者は、「このような学問領域は、日本には殆ど存在しないので、紹介・導入したい」とゴイス博士に述べて、幾つかの質問を行った。例えば、科学(science)という用語には、今日、余りにも自然科学のイメージが付着してしまっているので、自然科学の方法論と社会『科学』のそれとの関係を考える領域の名称として、社会科学の哲学(philosophy of social sciences)が適切なのかどうか」という点、それに関連して、「自分の事を『社会科学者』と呼ぶかどうか」などについてである。博士は、「これは自分達が始めた新しいプロジェクトである」とされて、筆者の企図を大いに喜ばれると共に、大略次のように答えられた。「確かにその懸念はあり、例えば、ダン教授ならば、おそらく自分の事を『政治科学者(political scientist)』とは呼ばず、『政治理論家(political theorist)』と呼ぶだろう。ただ、ここでsciencesというように複数形を使っている点に注意して欲しい。これは、自然科学的な統一科学のイメージに限定されていない学問観を示している。歴史的には、十九世紀にはJ.S.ミルらが「道徳科学(moral science)」という用語を用いていたように、scienceという言葉は必ずしも今日の自然科学の意味で用いられて来た訳ではないから、このような(複数形の)用法も無理ではない。もし、それでも気になるのなら、例えば、『社会的知識の哲学(philosophy of social knowledge)』ないし『社会探求の哲学(philosophy of social inquiry) 』などと表現したらどうか。」この小稿の題で、敢えて「社会諸科学の哲学」と複数形に訳したのは、この博士の説明を承けての事である。
既に紙数が尽きたので、もう一つの主題たる政治哲学については、一言だけ触れるに止めよう。「社会諸科学の哲学」の場合とは異なって、政治哲学が学問領域として存在している事位は、筆者も知っていた。ただ、日本に於いては、法哲学のみ発展していて、政治哲学は諸大学に殆ど独立した講座が無い為に、ロールズの紹介すら細々と為されているに過ぎなかった。もともと「哲学編」の重要な部分が政治哲学となる事は自明なので、ケンブリッジでは当初から意識的に政治哲学の講義等に全て参加するように心掛けたのである。ゴイス博士は政治哲学の講義やセミナーも行っており、この点でも裨益する所が大きかった。勿論、ケンブリッジは政治思想史研究のメッカなので、それも可能な限り摂取するように努め、スキナー教授の講義やゴイス博士との会話から、いわゆるケンブリッジ学派の(日本で強調されている方法論のみならず)共和主義研究の重要性を認識して、(ペティットらの)今日の政治哲学としての共和主義の出現を認識した事も、大きな収穫であった。こうして、(日本では漠然としたものに過ぎなかった)政治哲学の明確なイメージを得る事が出来たので、これも日本政治学に是非本格的に導入したいと思いつつ、帰国の途に着いたのである。
五.日本での出会いと急展開――政治哲学・公共哲学・社会哲学
帰国後、これらの希望を実現する機会は、予想以上に早く、かつ思いがけない形で次々とやって来た。まず、千葉大学で、前田康博教授の定年退官に伴って、筆者が(教授の担当されていた)政治原論の講義を引き継ぐ事になり、それを「政治哲学」という名称に変えて、従来から担当していた比較政治の講義と隔年で開講する事にした(一九九九年より)。それと並行して、一九九八年より宇野重規助教授(現在は東京大学社会科学研究所)と政治哲学研究会を作り、今日までほぼ毎月一回づつ開催している。これらの政治哲学の研究・教育活動は、恐らく日本では数少ない試みと自負している所である。
また、先に言及したケンブリッジ・フォーラム以来の縁により、将来世代国際財団・将来世代総合研究所(金泰昌所長)の主催する様々な研究会、殊に(筆者が帰国してから始まった)公共哲学共同研究会(一九九七―二〇〇〇年)に継続的に参加し、政治哲学の立場を中心にして、公共哲学の共同構築作業に積極的に協力して来た[vi]。この研究会は、(専門分化して専門家以外にはわからなくなってしまっている)学問間の壁を超える事、即ち、学問の私物化を超え、学問の公共化を図る事を目的の一つとしており、これが――公私関係の議論の内容と共に――筆者にとっては最も意義深く、魅力的に思える点の一つであった。率直に言えば、決して少なくは無かった問題点を乗り越え、哲学の内容に於いては金博士と論争を繰り返しつつも、このプロジェクトに携わり続けられたのは、――戦後啓蒙期以来、日本では初めてと思われるような――この学際性に魅き付けられたからであり、各学界を代表される高名な先生方のお話を伺えるのは、学問の醍醐味以外の何でもなかった。ケンブリッジで味わったような夢のような学際的な知的交流を、期せずして、日本でもその最高レベルに於いて体験する事が出来た訳であり、これは全くの僥倖以外の何物でもない。
逆に言えば、この学際的研究会で筆者が何ほどかの貢献を為し得たとすれば、それは前述のような筆者の知的遍歴に負う所が大きい。例えば、これらの研究会で、環境問題などを巡って社会科学系の学者と自然科学系の学者とが対立し、緊張が走る事が時にあったが、その時、筆者の念頭に浮かんだのは、「社会諸科学の哲学」に於ける方法論的対立の様相であった。方法論の対立は、単に抽象的な問題に止まるのではなく、具体的な問題に即して考えている際にこそ、深刻な問題として立ち現れるのである。なお、公共哲学そのものについて、ここで触れる余裕はないが、筆者自身の展開しつつある公共哲学は、――拙著の延長線上に展開される筈の新構造主義的公共性論を基盤としつつ――やはりケンブリッジ学派の共和主義研究に触発されたものであり、それ以来想を練ってきたネオ・リパブリカニズム(的政治哲学)を基軸とし、リパブリカニズムを「公共主義」と訳して、「新(総合論的)公共主義」と呼んだものである。
出会いは、以上に止まらない。公共哲学について編著を刊行された事[vii]を契機としてこのプロジェクトに山脇直司教授(東京大学大学院総合文化研究科)が参加され、以後重要な役割を果たされたが、研究会での出会いを機にその著作を読んで筆者は一驚した。迂闊にもそれまで気付いていなかったのだが、教授の『包括的社会哲学』(東京大学出版会、一九九三年)の第三章は、「社会諸科学の哲学――基礎論的考察」と題されており、正しくこの著作こそ、筆者の導入したいと考えていた「社会諸科学の哲学」を日本に開示したものだったからである[viii]。その引用・参照文献から見る限り、(筆者がケンブリッジで収集してきた)「社会諸科学の哲学」の文献は用いられていないから、想像するに、山脇教授は、ゴイス博士が意識しておられる諸研究とは独立して、そのような学問分野の必要性を認識されたようである。もっとも、これは必ずしも偶然とは言えないであろう。山脇教授も、(正統的な経済学から哲学へと関心を移され)――ゴイス博士と同様に――ドイツに留学されて、ポパー以来の批判的合理主義とアーペルの超越論的プラグマティズムとの論争について研究されて博士号を取得され、ドイツで著作を刊行しておられるからである。共にドイツで研究され、フランクフルト学派に造詣の深い二人が、期せずして同じ学問分野を開拓しておられるのも、また筆者がこの双方から順に深い知的刺激と啓発を受けるに至ったのも、とても偶然とは思えない。従って、「社会諸科学の哲学」を日本に導入しようという筆者の企図は、既に山脇教授らによって先鞭を付けられている事になるから、今後為すべき事は、その先駆的業績を踏まえて、日本独自の「社会諸科学の哲学」を発展させてゆく事になろう。拙著(十七頁)で、その後刊行された『新社会哲学宣言』(創文社、一九九九年)に言及しつつ、自分の研究について、その華麗な宣言(マニフェスト)に「呼応して刊行される政治学内部からの挑戦…」と述べたのも、決していい加減な思い付きではないのである。
期せずして、山脇教授も、日本に於ける政治哲学の不在を事あるごとに批判的に指摘しておられ、『新社会哲学宣言』でも第五章を政治哲学に割いておられる。政治学にとっては嘆かわしいことに、この章は、邦語文献の内で、今日の政治哲学についての最も優れた要約的紹介ないし批評となっているようにすら思われる。近年、新しく発足した政治思想学会などでも、規範的な政治哲学の必要性が指摘されており、大いに勇気付けられるが、政治哲学の専門的研究者と見倣し得る人が数人しか思い浮かばない現状では、「政治哲学が法哲学のように独立した学会を形成する」などという事は、夢のまた夢と言わざるを得ない。そこで、(公共哲学共同研究会の発展形態として構想されている)公共哲学ネットワークないし学会の中で、その一翼を担うものとして、政治哲学が―― 「社会諸科学の哲学」と共に――次第に発展してゆくのを念願している次第である。
勿論、この小文では、「社会諸科学の哲学」の具体的な展開については述べられない。予示的に述べれば、筆者は、ゴイス博士の言う(実証主義などの)通説的見解――テイラーの言う「自然主義(naturalism)」(拙著二六九頁)――には勿論批判的であり、解釈学などの(自然科学的な「説明」と社会科学に於ける「理解」との)二元論的見解に共感を持っているが、単に批判哲学に止まる事無く、――山脇教授の示唆されている方向(「自己―他者―世界」了解という根源的問題の考察に基づいて、自然・文化・歴史を主題として取り上げる包括的哲学、さらには、存在論的・生成論的な全体論的(ホリスティック)ないし総合論的哲学)をさらに展開して――社会諸科学の側からの「統一科学」という(ガダマーが少しだけ示唆しているという)展望を本格的に追究し、二元論的な方法論的対立を「総合論」として対理法的(ダイアレクティカル)に止揚する可能性を夢見ている、とでも言えようか(拙著294頁注一参照)。
振り返ってみると、さほど期待も準備もしていなかったにも拘らず、筆者にとって、ケンブリッジでの研究は、予想もしない形で自らの研究を新しい領域として位置付ける事を可能にし、かつその後の日本での展開の準備となる実り豊かなものであった。特に「社会諸科学の哲学」は、余りにも新しい展望を開くものだったが故に、筆者は、まず紹介の労を取る事から始めるつもりであったが、既に先学の手によって優れた仕事が公刊されている事を発見した以上、その貴重な土台の上に立って、筆者が元々企図していた研究(「哲学編」)を展開する事が出来そうである。拙著に於ける、(出版にあたっての改訂でギデンズの構造化理論を摂取した)新構造化理論=新構造主義や総合論的社会諸科学の構想は、その第一歩であり、次作では、これらを本格的に展開すると共に、その基礎の上に「脱日本行動主義革命」を遅まきながら遂行したいと思っている。
[i] 丸山眞男「科学としての政治学」(同『増補版 現代政治の思想と行動』未来社、一九六四年)、三五八頁。
[ii] Tae-Chang Kim and Ross Harrison, eds., Self and Future Generations: an intercultural conversation(Cambridge, The White Horse Press,1999).
[iii] この講義の骨格は、その後、Quentin Skinner,Liberty Before Liberalism(Cambridge, Cambridge University Press,1998)として出版された。
[iv] Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School (Cambridge, Cambridge University Press,1981); idem., Morality, Culture, and History: Essays on German Philosophy (Cambridge, Cambridge University Press,1999).なお、博士は、スキナー(やタック)と共に、定評のある「政治思想史のケンブリッジ・テキスト」シリーズの編者を務めておられる。
[v] Patrick Baert, Social Theory in the Twentieth Century (Cambridge, Polity Press, 1998).
[vi] この成果が、東京大学出版会から十巻のシリーズとして刊行される予定である。
[vii] 山脇直司・大沢真理・大森彌・松原隆一郎『現代日本のパブリック・フィロソフィ』(新世社、一九九八年)。
[viii] この他、この主題に関連するものとして、丸山高司『人間科学の方法論争』(勁草書房、一九八五年)、田村正勝『社会科学のための哲学』(行人社、一九八六年)、同『新時代の社会哲学――近代的パラダイムの転換』(早稲田大学出版会、一九九五年)などが存在する。特に、後二者は、経済学者の作品であるにも拘らず、「社会科学の哲学」ないし「社会哲学」という名称を使って、実際にその名に恥じない水準の論述を展開しており、注目に値する。山脇教授の作品と共に、筆者は共鳴する所が大きく、この二者を――今後発展させてゆくべき――日本独自の「社会諸科学の哲学」の出発点と考えている。