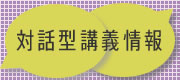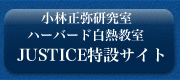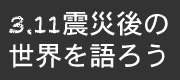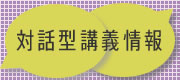

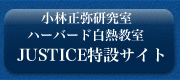

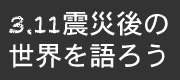
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 「反テロ世界戦争」関連 | Home | 公共哲学による学問の構造改革を! »
Posted: admin on 10:12 pm | 書籍・雑誌情報(Books, Journals, Magazines), 論文・書評・所感など
「公共世界-自己-他者」理解の革新
——『新社会哲学宣言』に寄せて——
山脇 直司
昨年9月に創文社から上梓した『新社会哲学宣言』は、筆者が、経済学から哲学に転向して学位を取得した後、相関社会科学科という全国でもユニークな学科に所属しながら、色々と追求してきた様々な事柄を、体系的なアカデミックスタイルで世に問うた書である。発刊後、『創文』1-2月号での八木紀一郎、内野正幸両氏の書評を始め、様々な方からご批評頂き感謝しているが、本稿は、この書で言い足りなかったポイントを補足してみたい。
まず、拙著が企図した根本的な狙いは、大きく次の三つに分けられる。
1 既存の専門主義的な哲学理解や社会諸科学体制が決して普遍的なものではなく、歴史的産物にすぎないことを、確固とした学問史的展望の下に基礎付けること。その際特に、哲学を狭小な学科哲学の枠内から脱出させ、トランスディシプリナリィな学問として、社会諸科学と統合させること。そしてそのために筆者は、「プレ・専門化」「専門化」「ポスト・専門化」という三つの時代区分を導入した(第一部)。
2 現在非常に混乱している社会科学の基礎的諸概念を再定式化する(第4章)とともに、「公共世界-自己-他者」了解という概念を導きの糸として、社会哲学のコアを成す政治哲学と経済哲学を、それぞれ論考しつつ架橋すること(第5、6章)。
3 そして、こうした試みを単なる国民国家や国内アカデミズムの世界に閉塞させないためにも、過去の歴史の総括を踏まえつつ、未来に向けての国際公共哲学の端緒を築くこと(第7章)。
さてこの中で、第1のポイントに関して、社会経済学者の八木氏は「ポスト・専門化」という時代状況の知識社会学的裏づけの必要性を指摘された(『創文』 20001-2月号,p.37)。氏の指摘は正当であり、特に「電子通信技術の発展や大学の開放の発展によって、所属組織・機関・職業に依存しない学術的コミュニケーションが発展すること」が、「ポスト・専門化」時代の大切な条件であろう。なお、これに付言すれば、大学組織レヴェルでも、すでに由緒あるオクスフォードのPPE(Philosophy, Politics, Economics)コースや10年余り前にできたケンブリッジのSPS(Social and Political Science)コース、また最近のミュンヘン大学哲学部での経済倫理学という講座の開設、そして日本では筆者が所属する相関社会科学コースを始め、様々なところに社会科学と哲学の再統合の兆しが見て取れることを、筆者は確認しておきたい。もちろんこうした動きに対し、専門主義に固執する保守的社会科学者 (特に経済学者)からの根強い抵抗が予想されるが--。
他方の内野氏は、心理学や教育学などを含むもっと多彩なかたちで、またより厳密な基礎付け作業によって、諸学の統合を推進するべきではないかと指摘された (同、p.41-42)。氏の見解は、学問の基礎付けの試み一般を無意味とみなすローティや、『週刊読書人』1999年11月26日号で書評された渡辺幹夫氏の考えとは対極にあるように思われるが、シリアスな社会問題にコミットしながら厳密な知を追求する法学者からの貴重な指摘として受け止め、筆者の今後の課題としたい。
では、第1のポイントについてはこのくらいに留め、本稿で主に補足したい残りの点について言及していこう。
まず拙著の要とも言える第2のポイントのうち、社会科学の基礎概念の再定式化という作業は、トランスディシプリナリーな哲学が今後果たすべき重要課題の一つである。実際それは、社会科学が自然科学とも文芸批評とも時事評論とも異なる独自の学問性をもつ限り(Vgl. 拙稿「社会科学の学問性」『科学基礎論研究』第93号創文社、pp.19-24)、また異なるディシプリンを営む社会科学者間の討論をできるだけ円滑かつ生産的に行うために、必須の作業に思われる。
この基礎的作業はしかし、新社会哲学のコアを成す政治哲学と経済哲学と結びつくことによって、肉づけされなければならない。新たに再構想さるべき政治哲学は、政治的なるものの概念を吟味しつつ、正義、権力、多文化主義などの最先端のイシューを論考する学問として、また復権さるべき経済哲学は、科学主義的な今日の経済学に風穴をあけるべく、久しく継子扱いされてきた規範的経済学のハラダイム変革や、台頭しつつある進化経済学の認識論的諸問題や、経済倫理学のイシューなどを論考する学問として方位付けられる。そしてその際、筆者がこの二つの学問を切り結ぶ根本概念として重視するのが「公共世界」である。この概念は、かの有名なアーレントによって、万人によって見られ、聞かれ、可能な限り最も広く公示される事柄の世界と定義された。しかし、古代ギリシャに範を採る彼女の世界観では、経済という重要な領域が公共世界から締め出されてしまうのに対し、筆者は、ふつう私的とみなされている経済活動も公共世界という枠内にあることを強調したい。
経済活動がたとえ利潤極大化をめざす場合でも、決して公共性の制約から完全に自由ではないという見方は、アダム・スミスが「公平な観察者の共感」を利己的活動の適正さの判断基準と考えた時、歴史学派や旧制度学派が「ルール」や「慣習」を論じた時、またポランニーが「社会の中に埋め込まれた経済」を主張した時、想定された社会観であった。然るに、現在スタンダードとなっている(新古典派流の)経済学教科書では、この重要なポイントは隠蔽されてしまう。公共事業という言葉に代表されるように、公共とは専ら政府(官)が行う市場介入に関わるタームとみなされ、経済活動の可能の制約としての公共性という観点は、教科書から抜け落ちてしまうのである。だがもし人が、そうした教科書が描く世界を現実社会と混同するなら、ここ数年わが国で起こっている経済界の不祥事の根源を認識することができないだろう。この点、実学を標榜するはずの経済学が「社会知らず」という意味での虚学になっている現状は、スキャンダラスですらあり、単にアカデミズムの世界を越えて、経済学教育の社会的責任が問われる事態を招いている。
拙著はこのように、アーレント流の、そしてまたハーバーマス流の政治中心的な公共世界論とは異なる、経済哲学的な射程をもつ公共世界論を中軸に据え、さらに国民国家の枠内に縛られない政治哲学を、「自己-他者」了解の革新という観点から展開しようとしたものである。実際、これまで哲学とは縁の薄かった公共政策も、エスニシィティ、ジェンダー、地球環境、科学技術、過去の歴史といった問題が絡む場合、テクニカルな思考だけでは済まされず、価値理念のレヴェルでの思考を必要とする時代に我々は生きているのであり、今後ますます、個々人の「公共世界-自己-他者」了解が、政治をつくるアクターとして重要な意味を帯びてくると筆者は確信している。
ところで、ここで筆者がいう自己や他者とは、もちろん無色透明で価値中立的な主体ではない。それは、のっぴきならないある特定の文化的・歴史的なファクターによって規定されつつも、対話やコミュニケーションを通して「公共世界-自己-他者」了解を深化・発展・変革させていく主体である。従って、様々な世界に次元に生きる自己(Self)や他者(Other)をどう了解するのかが、政治哲学と経済哲学を切り結ぶ「公共哲学」の根本問題となる。そして、その「公共世界-自己-他者」了解が、国民国家のレヴェルを超えたトランス・ナショナルな次元を内包しなければならない、という見解が拙著の基本命題の一つであり、筆者が第3のポイントを強調したい所以である。
「公共性の歴史」という観点を導入して考えるならば、20世紀は、国民国家が最高規範となり数々の成果を収める一方で、二つの大きな戦争に象徴されるように、公の名のもとに数々の悲惨な出来事をも生んだ。そうした状況の中で唱えられたわが国における「滅私奉公」というイデオロギーは、公が国家と混同され、私という個人が取るに足らない存在者として軽視されたことを端的に物語っている。しかし、拙著が唱える「全体論的・対話論的・生成論的」個人主義は、単なる方法論のレヴェルを超え、一方で人間存在の公共的次元に無頓着なミーイズムに抗すると同時に、他方で現下の日本で未だ根強い滅私奉公的な公私観や国民主義的な公共性観に抗するために打ち出された思想でもある。すなわちそれは、個人がアトミスティックな存在者ではなく、社会制度やシステムによって様々なかたちで規定されつつ、対話、討議、コミュニケーションなどを通してそれらを変革していく公共的存在者であること、そしてまた、その個人の「公共世界ー自己ー他者」了解を国民国家を超えた地球社会という次元にまで及ぼすことを謳う社会思想なのである。そのため筆者は、ウォルツァーの「分割された自己 (divided self)」という考え方に半ば共鳴しつつ、さらに「コスモポリタン的自己(cosmopolitan self)」という考えを不可欠なものとみなした(p.151)。
とはいえ他方、筆者は、コスモポリタン的自己によって「自己-他者」了解がすっぽり包摂されてしまうような超普遍主義的な自己論は採らない。そうではなく、基本的に「コスモポリタン的自己」は、「多次元的な自己」の必要不可欠な一次元として、したがってまた「国民的自己」とも両立可能なものとして了解しうるし、また了解されなければならないという見解に立つ(pp.194-197)。そのように考えることによって、各個人は、過去と現在と未来に責任をもつ国民という次元を保ちながら地球市民となりうるし、また、アングロアメリカン・スタンダードという考えに示されるような、ある特定の文化を普遍主義化するという文化帝国主義的な誤りに歯止めをかけることもできるだろう。もちろんその場合でも、プライベートな次元を含む様々な世界を生きる多次元的な「自己-他者-世界」了解という観点は保持されられなければならない。筆者には、従来の国際関係論や国際社会学と異なる国際公共哲学(trans-national public philosophy)という学問が可能としたら、「地球市民的自己」と「国民的自己」の両立や「公共的自己」と「私的実存」の両立の論理をこそ追求しなければならないように思われる。そして、拙著の終章は、曲がりなりにもその端緒を築くことを狙ったものである。
最後に筆者は、これからの我が国の人文社会系アカデミズムを、欧米思想の受信型研究から発信型研究へ転換させていくということを、知の国際的公共性を謳う哲学の緊急の課題として挙げておきたい。思想ジャーナリズムに操られる「オタク的知」が「公共的知」の対極にあることは言うまでもないが、公共的知を追求する我が国の学会も、特に哲学・思想系学会の大会プログラムや学会誌を見る限り、多くの場合、均質な国民国家的言説空間に埋没しているように思われる。そうした現状を打破するため、学会活動もトランス・ナショナルな公共空間の中で営まれるよう体質が改善されていかなければならない。では、近い将来そうした改善がなされることを祈りつつ、本稿を締めくくることにしよう。