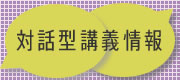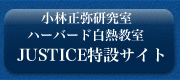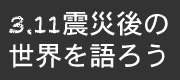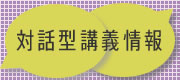

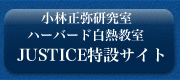

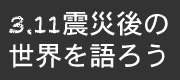
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 「公共世界-自己-他者」理解の革新 | Home | 山脇直司著『経済の倫理学』をめぐって »
Posted: admin on 10:22 pm | 書籍・雑誌情報(Books, Journals, Magazines), 論文・書評・所感など
公共哲学による学問の構造改革を!
――社会諸科学と哲学の学際的で国際的な教育・研究体制の確立へ向けて
山脇直司
21世紀に入り、日本でもCOE構想など、学問体制変革の兆しが見えている。この兆しが今後どのような展開を遂げるのか予断できないが、以下では、筆者独自の見地から、これからの社会諸科学と哲学のあり方に関する抜本的なグランド・デザインを描いてみたい。
筆者が思うに、今日なによりもまず抜本的に変革されなければならないのは、「哲学なき社会科学」と「社会科学と疎遠な哲学・倫理学」の分断状況であろう。現下の日本で、哲学・倫理学と称する学問は、文部省公認の学問分類表によって人文学の一分野と規定されていることに後押しされ、多くの場合、文学部の一学科の中で文献学的研究や抽象的思弁に埋没する一方で、逆に、政治学や経済学や社会学の各分野は、できるだけ哲学や倫理を捨象した実証研究に携わるという形で、研究・教育が再生産されている。しかしこのような学問体制は、長い学問の伝統に照らすならば、非常に偏った状況の産物であるのみならず、21世紀の日本をデザインする上で、甚だ由々しい障害物であることが認識されなければならない。そもそも、古今東西の思想史において、たとえばプラトン、アリストテレス、ストア派、トマス、ロック、スピノザ、カント、ヘーゲル、儒教、イスラム思想などを見ればすぐわかるように、哲学と政治は不即不離の関係にあったし、経済学の祖アダム・スミスにおいても、経済学はどこまでもモラル・フィロソフィ(道徳哲学)に属する学として構想されていた。近世日本においても、徂徠学の伝統や幕末の横井小楠にあっては、政治と経済と哲学が統合された経世済民の学が展開されていた。然るに、19世紀中葉以降に起こった実証主義ないし専門主義の興隆とともに、社会諸科学と哲学研究の分断がおこり、まさにそのような時期に日本の大学制度や学問分類が確立されたのである。
そうした状況を、かつて丸山真男は学問の「蛸壺化」と呼んだが、丸山の警告にもかかわらず、その状態は大学や学会を通して今日まで再生産され続けている。その結果、一方では、政治や経済の考察を排除することを哲学の王道とみなす謬見が、「純哲」とか「哲学プロパー」というイデオロギー的表現の下で正当化・再生産され、他方では、哲学や倫理は文学部で扱われる事柄であって、リアルな政治や経済には関係ないといったメンタリティが支配的になるのは当然の成り行きであろう。そして、一体人々はどのような公共社会をつくり「たい」のかとか、どのような公共社会をつくる「べき」かというテーマ、換言すれば、公共社会を支える価値理念について掘り下げて考えることが、政治や経済を論じるうえで重要な事柄とみなされなくなり、単に「できる」というテクニカルなハウツー能力や、単なる処世術だけが世の中で幅を利かすようになる。実際、学生たちがそのような教育・研究体制で訓練を受け、その訓練の偏りに気づく間もなく、偏った試験でふるいに掛けられ、行政界や外交界や経済界へと進んだとき、彼らが極めて矮小な形でしか政治・外交・経済を論じられなくなる現状は、悲劇ですらある。
しかし今や、このような不健全な学問体制は、社会科学と哲学の「学際的」で「国際的」な研究体制の確立という「ポスト専門化」時代のビジョンによって打破されなければならない。
社会諸科学と哲学との「学際的」研究に関して言えば、それは、社会諸科学と哲学がそれぞれ自律性を保ちながら相互に影響を及ぼし合うという形の研究体制が確立されなければならないだろう。そうした体制は、オクスフォード大のPPE(哲学、政治学、経済学コース)やケンブリッジ大のSPS(社会・政治学部)や東大駒場キャンパスの相関社会科学コースなどに先例があるものの、現在のところ未だマイナーな位置に留まっている。そこで筆者を含む有志は、「公共哲学」を中心概念として、哲学(倫理学や思想史を含む)、政治学、経済学のみならず、社会学や科学論・技術論・環境論などをも含めた学際的なアプローチによって、これからの「公共世界」のあり方について論考していく知的運動を推進しており、今後このようなアプローチが既存の学会・大学・学部の垣根を越えて広がることを期待している。また筆者は、このような学問運動や学問体制が確立されるエポックを、諸学と哲学が未分化であった19世紀中葉までの「プレ専門化時代」、諸学が哲学から離れて個別科学(ディシプリン)化することが学の進歩とみなされた19世紀後半から20世紀後半までの「専門主義時代」と区別して、学問の「ポスト専門化」時代と呼んでいるが、名称はともかくとして、そのような新しい運動や体制の確立は、21世の日本の学問、特に社会科学にとって急務であろう。そうなって初めて、社会が「現にある」姿の経験的考察と、「あるべき」理想社会についての理念的考察と、その理想が「実現できる」可能性の洞察を、区別しつつも切り離さずに論考するような教育や研究が可能となり、将来社会のビジョンについて、スケールの大きな確固とした論議も活性化するに違いないからである。
「国際的」研究体制の確立に関して言えば、これからの社会諸科学や哲学の論議は、国内レベルに留まることがもはや不可能であるとの認識から出発しなければならない。然るに、現下の学会組織のほとんどは、たとえば「日本00学会」という名のごとく、国内メンバーだけによって構成されており、論議内容の評価が国際的レベルで行われることは稀である。たとえば、人文・社会科学系学会の多くは、海外の学説を日本人の間だけで論じて済ますような学会や研究会を再生産しているが、まさにこれは学問の「没国際性」を象徴していると言わなければならない。そしてそうした「没国際性」は単に学会組織に見られるだけでなく、たとえば島国日本だけでしか通用しない議論をもてはやす出版界(出版文化)や論壇にまで及んでいる。実際、書店の思想コーナーにならぶ島国日本のご名士様の多くは、国際的に通用する論客とは到底言い難いのに、わが国の出版文化はそうしたご名士様の夜郎自大性を助長しているし、また逆に、海外の思想を一方的に受信・紹介するだけで済ますような研究や、その周辺に浮遊するジャーナリズム的知は、そうした「没国際性」というコインの裏側に過ぎない。このような島国的状況を突破するため、自然科学のみならず、社会科学・哲学の領域においても、国際的レベルでの「発信・応答」型の研究体制が早急に確立されなければならないだろう。具体的には、国際的レベルでのシンポジウムや学会がもっと多く日本で催され、しかもその成果を、一過性のフローとしてではなく、「未来に繋がるストック」として残すような研究・出版体制が確立されなければならない。特に、日本の学者にとって、東アジアのアカデミシャンとの共同研究体制の確立・強化は不可欠である。そうすることを通して、いまだギクシャクしている過去の歴史認識の問題や、社会科学におけるアングロ・アメリカ的パラダイムの偏りに対する批判的問題意識を共有できるからである。
以上のように、日本の社会科学や哲学が国際競争力を身に付け、世界に貢献していくためには、諸学の「蛸壺状態と島国状態から学際化と国際化へ」という抜本的な構造改革が不可欠である。そのような学問の構造改革が果して出来るのかどうか、それはひとえに、公共哲学運動を含め、割拠見に囚われない大局観を身に付けた学者の自覚と連帯、および出版人の努力にかかっているように思われる。