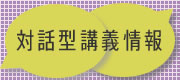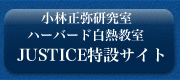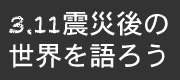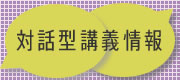

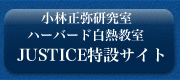

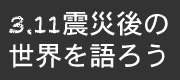
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 朝日新聞2006年12月4日付け朝刊「私の視点」掲載記事 稲垣久和 | Home | 『公共哲学とは何か』 »
Posted: admin on 12:42 pm | 主張・意見・コメント(opinions), 教育基本法改正問題
〔※山脇直司『公共哲学とは何か』(ちくま新書、2004年5月)第5章からの抜粋〕
現下の教育基本法改正(改悪)案をめぐる議論が示すように、「教育と公共性」はホットな争点となっています。しかし、中曽根元首相や読売新聞編集部などに代表される改正(改悪)論者が言うように、「個人の尊厳」を強調するあまり「公共性」がないがしろにされるという考え方は根本的に間違っているというのが、公共哲学の譲れないスタンスの一つです。
1889年の明治憲法とペアになって1890年発布された教育勅語は、「滅私奉公」を説くものとして戦前に忌々しい結果をもたらしました。その反省として、戦後の日本国憲法とペアになって生まれた教育基本法は、「個人の価値と責任」を謳っています。教育基本法第1条を、ここでもう一度引用してみましょう。
「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行なわなければならない」
しかしこうした教育思想は当時、復古的国家主義者のみならず、いわゆる左翼勢力からもブルジョア的個人主義として批判されていたのです(小熊英二『民主と愛国』新曜社、2002、頁参照)。実際、戦後の日教組などでは、第二章9節で触れたように、ソビエトのマカレンコの「集団主義教育」論が影響力を持ち、「個人の価値と責任」などはむしろブルジョア・イデオロギーの一つとみなされていたことは否めません。
いずれにせよ、戦後教育の現場では、ソビエトのコルホーズやソホーズを称えたり、レーニン主義的な集団主義を理想と説くなど、今から思えばとんでもない幻想を生徒に植え付けようとする左翼教師が数多くいたことは確かです。そして恐らくそれは、戦後日本において、マルクス・レーニン主義が宗教のように受け取られたことと大いに関係があるでしょう。また、たとえマルクス主義を信奉していない民主的教師の間でも、「復古主義VS民主主義」という闘争図式の前に、「個人の尊厳」などに関する哲学はあまり追求されてこなかったように思えます。民主主義を支える「個人」の問題がないがしろにされてきたのです。
もちろん例外もあったでしょうが、いわゆる人権派教師の多くが人権の本来の意味とエゴの権利行使との相違を明確にしなかったのは、日本の教育にとって真に不幸なことでした。そしてそうした事態への反動が、1970年代後半から1980年代までの管理教育強化となって現れ、さらに1990年代以降のいじめや学級崩壊の頻発を経て、現下の教育基本法改悪案を招来したと考えるのは、強引すぎるでしょうか。
このような戦後教育の行き詰まりに対し、活私開公を掲げる公共哲学は、教育基本法改正(=改悪)論者に抗し、「個人の尊厳」と「公共性」を対立的にではなく、相互補完的に捉える教育観を呈示しなければなりません。
実際、南原繁らの影響の下で記された教育基本法の条文は、その双方を明記しているのです。この条文に出てくる平和、正義、責任などは、公共世界を構成する重要な価値理念ですし、人格の完成のみならず、健康な「国民」の育成までも条文で謳われています。ですから、この条文で始まる教育基本法が公共性に関する言及に乏しいなどという改正(=改悪)論者の主張は、「民の公共」を「国家の公」と取り違える歪んだ公私観に立脚していると言わざるを得ません。
このことを踏まえた上で、活私開公の哲学は、第一章4節で述べたように、80年代以降日本でみられる「滅公奉私」というミーイズム・エゴイズムが「滅私奉公」の裏返しにすぎないことを強調したいと思います。そもそも公共性は、「自分とは異なる他者とのコミュニケーション」があって初めて成り立つ概念です。然るに、滅公奉私というメンタリティやライフスタイルは、自己中心主義で、自分とは異質の他者とのコミュニケーションに関心を持ちません。ですから、当然それは「国家やお上の公」とは異なる「民の公共」というコンセプトを持ち得ませんし、そのような公共世界を創出する努力もしないでしょう。滅私奉公も滅公奉私も、公共世界は上から与えられるものではなく、我々が生成させる世界だという考え方が不在で、公共性という言葉で「お上の公」しか連想できないでいるのです。
こうした滅私奉公と滅公奉私の双方に反対する「活私開公の教育哲学」は、個人が「異質な他者とのコミュニケーション」の中で活かされ、そのことによって公共性が開花されるような教育理念を掲げます。個人の尊厳は、「自己」の尊厳のみならず「他者」の尊厳を必然的に意味すること、そしてそのような人間観が「公共性の母胎」となることが、幼い頃から教育の現場で伝えられ、学習されなければなりません。これはまた、「個性の尊重」という理念にも通じます。
「均質なみんな」が公共世界を創るのではなく、アーレントが言うように、「共通性と異質性」を兼ね備えた人間同士が公共世界を創るのです。したがって、「個性尊重」の教育と「公共性涵養」の教育は、補完し合わなければならないのです。
もちろん、これをきれい事と批判する人もいるでしょうが、ともかく滅私奉公や滅公奉私に対抗する「活私開公の教育哲学」は、このようなビジョンを語るしかありません。あとは、現場の先生方がこうした「自己―他者― 公共世界」観をもとに、教育をいかに実践するかに教育の蘇生はかかっているのです。