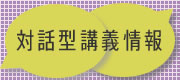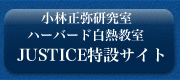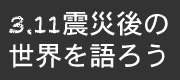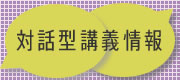

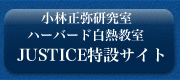

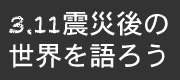
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 「ケンブリッジ・フォーラム所感──概括と成功報告」 | Home | 総合論的公共性論――新公共体主義の展望 »
Posted: admin on 10:48 pm | Michael Sandel, 書籍・雑誌情報(Books, Journals, Magazines), 論文・書評・所感など
「ハーヴァード地球的公共哲学セミナー所感──共同体主義者達との交感」
小林正弥(千葉大学法経学部法学科助教授)
1.序 ハーヴァード雑感──英米双方のケンブリッジ
私にとって、ハーヴァード大学(さらにはアメリカ自体)は初めて訪れた地であるが、にもかかわらず見慣れた地であるかのような既視感があった。というのは、このアメリカの最古の大学がケンブリッジ大学エマニュエル・コレッジの(礼拝堂のステンド・グラスに大きく飾られている)卒業生ジョン・ハーヴァードの残した遺産で創設されたからか、ケンブリッジ大学と物理的にも精神的にも共通の雰囲気が感じられたからである。(マサチューセッツ州)ケンブリッジという地名にも刻印されているように、前者のチャールズ川は、後者のケム川を連想させるし、建物は(チャンプニー様式など)後者のある時代の様式に似ており、さらに二・三日目の会議が開かれたハーヴァード・ファカルティ・クラブには、後者のカレッジそのものと言ってよいほどの類似性が存在した。逆に、──山脇氏の(以下敬称は基本的に「氏」で統一)御教示のとおり──すぐ近くにあるMIT の校舎とは対照的であり、MITビルディングが現代的で無機質・非人間的な印象を与えるのに対し、ハーヴァードの建物は、対照的に古典的な典雅さや人文主義的教養の背景を感じさせ、その知性の懐の深さを思わせた。率直に述べると、筆者はアメリカ文明の核心である科学主義的・技術主義的発想が好きではなく、それ故のアメリカではなくイギリスのケンブリッジ大学を海外研修の地として選んだのであるが、ことハーヴァード大学に関する限り、このような先入見を大いに改めることとなった。アメリカにも、幅広い教養の地がなお残っていることは、──現在の好景気にもかかわらず──夕陽の大国としか思えないこの国の将来になお希望をつながせるものである。かくして、ケンブリッジ・フォーラムに続いてこの地でセミナーが行われたことは、単に英米二国の代表的大学ということにとどまらず、英米双方のケンブリッジというつながりに鑑みて、公共哲学という主題にふさわしい、単なる偶然以上の連関を示しているように思われたのである。
2. 儒教的共同体主義と地球的・世代間的公共哲学図解──護教論と基本的ヴィジョン
豪華なチャールズ・ホテルで開催された初日の会議は、恒例のビデオや挨拶から始まり、参加者の自己紹介へと進んだが、先方の挨拶で印象に残ったのは、チャールズ・テイラー氏がまず「多元的な近代」という観念に言及し、マイケル・サンデル氏が公共哲学との関連における異なった伝統の意義や道徳的・宗教的切望について理解が深まることに期待を表明したことだった。この二人は、いわゆる共同体主義(コミュニタリアニズム)の代表者として世界的な名声を持っているが、(著書には明示的に述べられていないので)オックスフォード大学でサンデルが博士課程にある間にテイラーに教えを受けたという点は、筆者にとって初耳であり、おそらく日本の学界にとっても貴重な情報であろう。テイラーとサンデルの仕事は、共同体主義として括られるような共通の要素を勿論持っているが、サンデルは明示的にテイラーの見解に依拠するという形で議論を進めてはいないので、このような師弟関係の存在は外部からは必ずしも明瞭ではない。逆に言えば、今日の政治哲学における共同体主義の重要性と影響力を思う時、この師弟関係の果たした意義は、いくら強調しても、し過ぎることはないほどである。実際、傍で見ていて、この二人の間の信頼関係は、眩しく見えるほど美しいものであった。情報の意義に鑑み、この二人の発言については特に詳しく紹介することにしよう。
さて、まず初日の午前にはド・バリ氏が儒学の展開を公共哲学との関連において次のように整理された。『論語』に代表される第一段階から、君子の観念に見られるような自己発展の理念が存在し、共有・共通を意味する公の概念には既にユートピア的共同体主義の要素があった。『孟子』に代表される第二段階において、(公共善を表す)天理と(私益に相当する)人欲の対立が概念化され、『大学』の八条目に定式化されているように、前者によって(同心円状により広い共同体へと広がる)共同体主義的理想が説かれ、後者とはむしろ相補的な関係にあった。五倫のような儒教的論理は、元来は必ずしも忠孝に中心があるのではなく、君主への服従を強制するのは、歪んだ日本儒教の特色に過ぎない。さらに、新儒教は、仏教を拒否した公共哲学と考えられる。特に朱子学においては、理の観念が「宇宙全体─人間道徳」を貫通する原理とされ、統一性と多様性(理一文殊)、天地万物一体といったエコロジー的観念が内包されており、(仏教と異なって)公私を分別して真の自己へと至る自己修養と、それに立脚した共同体主義的理想が存在していた。これは、地球的公共哲学へとつながり得るものである。
氏の近著『アジア的価値と人権』(1998年)が「儒教的共同体主義的視角(A Confucian Communitarian Perspective)」という副題を有しているように、ド・バリ氏の報告は公共哲学としての儒学(特に朱子学)を一種の共同体主体と捉えてその意義を説明したもので、サンデル氏やテイラー氏も、自分達の思想との親近性を知って興味をもったようだった。サンデル氏は「魅力的」と評したし、テイラー氏はユダヤ教との類似性に言及して仏教的君子との関連について問い、ド・バリ氏は「仏教には政治的・社会的な教えがなく、国家が仏教を庇護したに過ぎない」と答えて、儒教の(仏教にない)意義を強調された。大沼氏が、日韓は公共哲学を提起するのに比較的適している旨述べたのに対し、ド・バリ氏は「十九世紀まで儒教はアジアに共通の文化だった」と応じられた。金泰昌氏は、「日本では新儒学が個人的哲学として私化されてしまい、また中国哲学の影響で私の価値が過度に軽視されてしまっている」と指摘され、メータ氏は制度との関連において儒教は難点を抱えている点を質問したが、ド・バリ氏は日本の儒教は(侍が担っていたが故に)「日本軍事学派」とでも言うべき歪んだものであるとして、制度との関連についても、「歴史的記録を見よ」と述べて、中国の本来の儒学を擁護した。金泰昌氏の公共空間についての質問については、儒教には「人々による政治」という要素はないものの、民意を統治者が聞く(Consultation)という意味での「人々のための政治」という側面は存在したとして、日本についても聖徳太子十七条憲法の例を挙げた。さらに、同じく金泰昌氏が問うた「国境を越えた公」については、「現実には皇帝の至上性を正統化する面が強かったものの、日本も他文明からの影響を受けているし、中国儒教は普遍主義的であって自民族中心主義ではない」とされ、大沼氏は、日本儒教にも国境を越えた例があることを補足された。
最後に、筆者は、ド・バリ氏の儒教擁護の熱意には心情的に敬意を示しつつも、儒教について全て肯定するような一般的印象を受けた点に懸念を表明し、「日中儒教の差異についての正当な指摘を考慮してもなお、儒教の遺産を二十一世紀の公共哲学の中に生かすためには、戦略的にも、(丸山眞男氏らが注目したような)歴史的儒教の(家父長的要素や非民主主義的といった)否定的側面を直視し反省を加えた上で、肯定的側面を新たに展開したほうがよいのではないか」と問うた。氏は、やはり「今言えるのは、記録を見よ、そして儒教についてより正確な教育を受けるべきだ、ということである」として、「(氏も会ったことのある)丸山氏の儒教理解は不正確であり、西洋中心主義的な偏見から脱却すべきである」と答えられた。筆者も、この点については氏に全く賛成であり、(あたかも儒者であるかの如く儒教に対する偏見と戦う)氏の真摯さに尊敬の念を惜しむ者ではない。しかし、素朴に考えて、儒教に限らず、いかなる大宗教・哲学といえども、それぞれ長所と弱点の双方を持つという見方の方が、むしろ自然であり、儒教に関しては長所のみ主張して短所を認めないという姿勢は、学問的な客観性を疑わしくし、ひいては「贔屓の引き倒し」という結果を招かないであろうか? 氏自身の著書についても、『中国における自由の伝統』(1983年)では自由という観点から朱子学を擁護し、前述のように近著では共同体主義として朱子学を擁護している。自由の伝統と共同体主義とは必ずしも矛盾するわけでないから、直ちに両者の間に矛盾があるとは言い難いが、儒学の自由主義的擁護と共同体主義的擁護の間に一定の緊張ないし重心の変化があることは、否み難いであろう。とすれば、氏の著作は、その時点において影響力のある思想を適宜借りて行う儒教護教論という感を免れず、知的一貫性の点で疑いが生じかねない。もっとも、筆者は両著作の検討を行ったわけではないので、この点の吟味は専門家に委ねたい。そして、私達は、西洋人ながら儒教の真価を深く理解され、通俗的な偏見の打破に努めて下さっている氏に、深く感謝の念を捧げるべきであろう。ただ、氏の説明の価値は、そのような西洋の背景を考慮してこそ十全に理解されるのであり、五・四運動や戦後啓蒙の如き儒教批判がなされねばならなかった歴史的・社会的必然性に眼を向ける時、中国や日本においては、氏の儒教擁護は若干素朴ナイーブに過ぎるという感が、拭い難いのである。
次に、──予定されていた日本側報告者が突然辞退するというハプニングが起こったので──金泰昌氏が予め用意しておられた図表「地球的・世代間的に応答的で責任を持つ公共哲学フォーラムの図解文法(The Illustrated Grammar of Global, Intergenerationally Responsive and Responsible Public Philosophy Forum)」を説明され、ハーヴァード側に共同作業を呼びかけられた。この図解は、──基本線を示して欲しいという要望に応えて──これまでの公共哲学共同研究会の討論内容を氏なりに集約しつつ、(それを牽引してこられた金氏自身の到達された)基本的ヴィジョンを図表として明快に示したものであり、その意味においてこの図解の明示的な定式化・公表は本プロジェクトの展開にとって画期的な意味を持つ出来事だったと言い得るであろう。討論過程に逐一接してきた筆者にとっては、図式の背後にある生きた議論と理論的生成過程が理解できるだけに、感慨深いものがあった。
ただ、惜しむらくは、おそらくハーヴァード側がそのような経験を共有していないためもあって、確たる反応が得られなかったことである。思うに、図式としては華麗であり、一見文句のつけようがないので、討論に入りにくかったのであろう。司会のサンデル氏は、このような雰囲気を敏感に感じ取り、ド・バリ氏の報告との関連に議論を促されたので、ド・バリ氏は、古典教育のカリキュラムの中に儒学の文献を入れるという自らの試みを話された。これに対し、メータ氏は学生が懐疑的になる可能性や教材選択における権威の根拠について問い(※)、ド・バリ氏は、「異なった伝統の古典を扱うからその間の相互比較が可能である」とした。サンデル氏は、日本の儒学についての教育について問われ、大沼氏が「(近年は若干改善の兆しがあるものの)低水準である」と答え、山脇氏及び筆者は日本の哲学的教育の貧困さを説明した。
筆者は、金泰昌氏の報告についての反応を求め、特にテイラー・サンデル両氏に対し、特に(特殊主義的・ローカル地方的な色彩が強い)共同体主義と地球的公共哲学との関連について問題にして、現在の共同体主義を地球的共同体主義へと拡大・発展される可能性について質問した。答えて下さったのはテイラー氏で、「共同体主義は、(例えばカント的・ロールズ的といった一つの理論枠組に対抗する)単一の原理ないし形而上学的枠組として存在するものではなく、自分はそのような意味では共同体主義者ではないが、『(一社会の連帯や公共民としての共通のアイデンティティーの存在ないし重要性故に現れてくる)他社会との間の善の衝突の可能性において、他の異なった社会の考え方を尊重し、そこから学び、自己批判の糧とする』という意味においては、私は共同体主義者である」とされた。共同体主義の地球的拡大という論点そのものに答えたわけではないものの、他の共同体の異文化の尊重と相互の対話への期待という点において自らを共同体主義者と自認する発言は、(文章では必ずしも明示していないので)貴重なものだったと言えよう。なお、その場では発言しなかったサンデル氏に晩餐の際コメントを求めたところ、「地球化との関連については明日自分の報告で話すので、その場で議論しよう」ということであった。
右のテイラー氏の返答は、本セミナーの大きな主題の一つである「共同体主義と地球的公共哲学との関係」について、議論が開始された一幕であったと言えよう。そこで、金泰昌氏は、「日本では共同体という訳語が抑圧的・排他的な悪い意味を持っているので当初共同体主義に好感を必ずしも持てなかったが、サンデル氏らの本を読み、今の応答を聞くに及んで誤解がとけた」と述べられた。これに対し、ド・バリ氏は、「共同体への反抗は時に共同体についての抽象的幻想に基づいている」として、(共同体には批判されるべき実態があったとする)金氏と対立し、「日本においても共同体批判は儒教の歪曲に基づいていて、儒教と結びつく必然性は存在しない」と主張された。これに対し、メータ氏が儒教の抑圧性に言及したところ、サンデル氏が「代替案を示せるか?」と鋭く迫ったのは、印象的であった。大沼氏は、「中国中心的秩序・イスラム中心的秩序といっても、前近代的秩序そのものに帰ることは意図されていない」と指摘された(※)。さらに、山脇氏が韓国におけるキリスト教徒の多さについて述べたのを受けて、ド・バリ氏は、「そこではキリスト教の儒教化・儒教のキリスト教化の双方が見られ、地球的文明にとって重要な示唆が存在する」と答えられた。総じて、ここまでは、一貫してアジアの儒教的共同体主義を擁護するド・バリ氏を軸として、サンデル氏が好意的であるのに対し、むしろアジア出自の金泰昌氏やメータ氏(インド系)が留保ないし批判を行い、大沼氏らが(批判の行き過ぎに対して、儒学の近代化に果たした役割などを指摘して)反論する、という構図が中心だったように思われる。
3、共同体主義の時間軸への展開──多元性と聖性
初日の最後の報告者は、注目のテイラー氏であり、その知名度故か、ベンハビブ女史らも姿を現した。まず、テイラー氏は「近現代をユダヤ教や中世などの一元論的発想の復活と捉え、プロテスタンティズム及びその後の世俗化した規範的一元論が、中世の位階制的秩序に代わって、(個人及び相互扶助を中核とする)(近)現代的道徳的秩序を形成した」とする。氏によれば、これは、世代間の問題について、二つの形で途方もなく大きな問題をもたらす。第一に、それまで人類は歴史的に社会関係の中に埋め込まれていたのに対し、主体がそこから遊離してしまい、そのような人間観が英米道徳哲学の中心となった。第二に、時間も、以前は永遠性や循環性のような高次の時間の中で考えられていたのに対し、世俗的時間へと変容した。この二つの変化の結果、(現在世代の利己主義というよりも)歴史や環境に対するコントロールの増大(※)から「文明の困難」が生じ、社会の多元化も将来世代のための解決策にはつながらない。これは、現代道徳秩序の孕む難題(アポリア)であり、氏自身も確たる解決策を提示することはできないが、次善の策として、問題の見方をこのように示したのである。
まず、金泰昌氏が、Ch. ラッシュのナルシシズム論に言及して、現在世代の利己主義について発言の真意を質したのに対し、テイラー氏は「利己主義の問題の存在を否定したのではなく、それは、より深い問題であると考えている」と答えられた。筆者には、テイラー氏の挙げた二点はいずれも(主体及び時間の)脱─埋め込みというように総括できると思えた。つまり、自己の脱─埋め込みという共同体主義論の基本テーゼを、時間軸にも適用して、世代間問題の考察を行っているわけである。そこで、「氏の(難題を指摘する)結論は、(宇宙論や意味的世界などに対する)何らかの形の再ー埋め込みという世界観の転換の必要性を含意するものなのか」と質問した。これに対して、氏はリオタールの言う「大きな物語の終焉」に言及して、「一定の世界観に戻ることは不可能である」と答えられた。ここで付言しておけば、休憩中に筆者が氏の用いる「存在論」という言葉の意味を聞いた際、氏は「『物事がかくあること』についてであって、形而上学的な深みを含むものの、それより広い内包を持つ」と答えられ、また氏のいう「真正な自己」と東洋的・ロマン主義的な「真の自己」との関連については、「前者は多様であり得るから後者のようには必ずしも収斂しない」と答えられた。要するに、テイラー氏は、世俗的・一元論的近代を批判しつつも、(多文化主義に現れているような)多元性を不可避と考えるが故に、前近代のような統一的世界観に戻るとは考えない。多元的近代という観念を提起している所以である。
それ以後の討論も、主としてこの点を軸にしていたと言ってよいであろう。大沼氏が、世俗化が心理的代償を求めるという機制を指摘した(※)のに対し、テイラー氏はアメリカのアイデンティティーをめぐる諸解釈間の争いを例にして答え、ベンハビブ女史が「統一した聖なる時間に戻ることは言うまでもなく不可能だ」と断言して、文化的・宗教的多元性という時代の条件についてリベラリズムのパラドックスないし矛盾を指摘すると、テイラー氏も(さらにコントロールについての院生の質問に応えて)、「再─聖化は勿論解決ではあり得ない」と追認して、「科学的コントロールは継続せざるを得ないが故に、他の選択肢を考えるのが困難である」というジレンマを認められた。ここで興味深かったのは、サンデル氏が、現在の現代的生活の継続性を「手を触れ得ぬもの(untouchable)」とみる見方に疑問を呈し、特に「聖なるもの(sacred)」の位置について敢えて尋ねたことであった。テイラー氏の返答には、改めて特筆すべきことはなかったように記憶するが、この問答が特に筆者の関心を引いたのは、この麗しい師弟の間に、ごく微妙な、見解の重心の相違が垣間見られたように思われたからである。即ち、多元性の主張に重点を置くテイラー氏に比して、サンデル氏はむしろ聖性の必要性を感じているように思われ、それ故、テイラー氏が(一元論的近代に対して多元的近代を主張するという形で)近代の圏域にとどまっているのに対し、サンデル氏は少なくとも世俗的近代に対しては、より根本的な異和感を持っているように感じられたのである。サンデルの代表作『自由主義と正義の限界』第二版序文(一九九八年)では、初版に比して、共同体的側面よりも善(の正義に対する優先性)の重要性に重点が移動しているように感じていただけに、今回さらに「聖なるもの」という観念を氏が提起したのは、筆者にとって衝撃的であった。上の傾向が確認し得るだけでなく、さらに予想以上に進行していることになるからである。この点について、夕食時に本人に確認し、「地球的資本主義に対抗する原理にして聖性に着目するという(翌日の報告に現れた)観点が次著の主題である」と聞いた。
この点が他の参加者にも興味深かったのか、山脇氏の下の院生諸君も、現代生活の肯定(坂口緑)や『自己の源泉』にあった神学的主張の消滅(中野剛充)について質問し、テイラー氏は後者に対し、「近代観には対立があり、なくすことはできないが、それはより高い水準への道かもしれない」として、「神学的議論は自分にとって最も示唆的である」と答えられた。この後、経済のグローバル化や文明間対話について質問がなされ、ド・バリ氏は「儒教は基本的には人間を対象として扱っているが、天理は地球をも含んでおり、道家のように自然が強調されてはいないものの、文明論的・地球的アプローチにも開かれている」とし、ベンハビブ女史は「新自由主義は地球的資本主義の正統化に過ぎないのに対し、どのようにして連帯を確保するかが問題である」とされた。ムアヘッド氏が「多元主義が十分に説明されていない」として制度について問われた(※)のに対し、テイラー氏は「制度だけでは十分でなく、制度と共に(軽視されている)価値への着目が必要である」(※)と答えられた。さらに、メータ氏やモルガン氏の脱─埋め込みについての問いについては、「カントの場合のように有意義(ポジティヴ)な場合もあるが、十八世紀以来の問題の深刻化が示すように否定的(ネガティヴ)な結果をももたらす」(※)と返答され、金泰昌氏が「(ジェネラティヴィティ・クライシスが示すように)人生における聖性(生への畏敬)の感覚が必要である」と述べて議論を締めくくられたのである。
最後に、この日の晩餐会において、テイラー氏と筆者とのやりとりが注目を集め、後で尋ねられることが多かったので、記しておこう。大沼氏の発言後、テイラー氏と(カント主義的な)サンジョヴァンニ助手との長い問答に皆が注目し、金泰昌氏が私に水を向けて下さったので、筆者は次のように尋ねた。「実は、あなたの今日の報告には、それほど満足できませんでした(一同爆笑)。というのは、あなたとサンデル氏には、世界の他のいかなる政治哲学者以上に期待して来たからです。ケンブリッジで私達は自己と将来世代との関係について議論し、私は、西洋の主流派理論はその原子論的構成故に将来世代のための論理を積極的に提示できない旨述べました。それに対し、全体論的側面を持つ共同体主義ならば、そのような論理を示し得るかもしれないと期待していたのですが、今日のあなたの報告は、問題の根源の指摘にとどまっていました。もっと積極的に、あなたの膨大な仕事に基づいて将来世代の論理を提示することはできないでしょうか?」これに対し、氏は「できる。」と答えて、三つの論法を挙げられた。第一は、人間は自分自身についても未来を考えて行動するのだから、将来世代についても同様というものであり、第二は、人間は子供など家族のことを考えて行動するのだから将来世代についても同様にできるというものであり、第三は、(宇宙全体に対する)執事職(stewardship)という観念を適用することである。この内、第三の論法が以下の議論の対象となり、筆者が「執事職の観念は他の文化にも適用しうると思いますか?」と聞いたのに対し、「氏は確実には言えないが、おそらく存在するのではないか」と答えたので、金泰昌氏がド・バリ氏に対し中国について聞いたところ、ド・バリ氏は「天命」の観念を挙げられた。筆者が「天命は天の観念と密接不可分に結びついているから、執事職とは若干異なるのではないか」と聞いたところ、アメリカ側は「執事職も神の観念と結びついている」ということだったが、金泰昌氏はド・バリ氏の答えに批判的であった。テイラー氏の挙げた三論法は、いずれも将来世代ないしエコロジーをめぐる文献に時折登場するものであり、必ずしも独創的とは言えないが、一応、共同体主義の側からの(将来世代の問題に対する)積極的な議論として記録しておく価値があろう。
4、文際的アプローチと学際的公共哲学──共感と称賛
二日目の午前中から、会場はハーヴァード・ファカルティ・クラヴに移った。まず、大沼保昭氏が報告を行い、国際公法という概念にも現れているように、「公(public)はしばしば国家と関連させて用いられており、混乱している」という問題点を指摘されて、(西洋中心主義的発想を排して、国家中心主義的アプローチを乗り越える)文際的アプローチ(inter-civilisational approach)を提唱された。これに対して、サンデル氏はすぐ「ここにいる大部分の人々は共感するだろう」とした上で、「その先の問題に議論を進めよう」と言われ、「アジアには国家と社会の中に公共空間がないという昨日の(金泰昌氏の)議論との関連」や「文際的アプローチにおいて生かされる、アジア文化の中の資源」について質問された。これに対し、大沼氏は「東洋/西洋」という二分法の限界を指摘しつつ、「アジアにも有意義な公観念は存在する」という立場から相互信頼などを挙げて答えられた。アジアや西洋における公と国家との関連について、金泰昌氏と大沼氏との間で論議が交わされ、テイラー氏が西洋の公概念について、(ローマ以来の)国家と関連する用法と公開という用法との存在(違い)を述べられたので、筆者は、「各地域にそれぞれ(国家中心的等)複数の用法が存在し、共通性も存在するが、比重には相違が存在するので、(垂直的・水平的・超越的などの)各用法を分解して分析し、その地域に必要な公概念(例えば、垂直的公概念の強い日本にとっては水平的な西洋的公概念)を考えるこが有益である」とし、大方の賛同を得たように見えた。
この後、金鳳珍氏が「近代の呪縛」について指摘し、テイラー氏は西洋的政治的伝統の狭さや西洋内部での多様性に言及され、ド・バリ氏は、日本における公観念が日・中・韓からの伝統の混成体であることを詳細に説明した上で、「日・韓にも寺子屋や私塾などの公共空間が存在した」とし、中国の(天に支えられた)公の観念の意義に言及して、法的な西洋的人権概念の限界を指摘された。これらが総じてアジアにおける公共性の存在や西洋的公共性論の限界を指摘していたのに対し、金泰昌氏は日本における研究会の経緯を説明して理解を求められた。ただ、おそらく問題は次のところに存在しよう。筆者も当日擁護したように、(日本における)国家と個人の間の公共空間の必要性という(金泰昌氏の)主張自体は現実的には妥当であるが、この観念自体はハーバーマスなどの西洋的公共性論ないし市民社会論と大差なく、西洋側にとって思想的には新鮮さがない。文際的アプローチが公共性論に新しい理論的貢献をなすためには、アジアを始めとする非西洋文明の公共性観から(従来の西洋的公共性論には存在しない)新しい要素を具体的に提示する必要がある。サンデル氏の冒頭の質問はこの点を鋭く問うものであり、大沼氏自身が最後に発言されたように、この点において議論をさらに彫琢する必要があるのである。とは言え、(院生達の質問に対して氏が答えられたような)非西洋的な知的遺産から(経済的権利に重心を置きがちなアメリカの人権概念とは異なる)人権論への寄与を引き出すという姿勢は、公共性論においても示唆に富むと思われた。
続いて、山脇直司氏の報告が行われた。氏の報告は、学際的・公共哲学の構図を大きく描き出すもので、従来の氏の報告と共通性が高いので内容紹介は割愛するが、特筆に値するのはアメリカ側の反応である。まず、サンデル氏が「とても素晴らしい(very good)。力強い像だ(powerful picture)。」と感想を述べてから、議論が始まり、モルガン氏が超国家的公共哲学にとっての共通言語を問うたのに対し、山脇氏は英語としつつも、「英米文化をただ受け容れるわけではない」と留保を付し、それに応えてド・バリ氏が儒学などアジアの文献を英語に翻訳する意義を述べられた。再度、サンデル氏は、山脇報告について、「非常に印象的だ(very impressed)」「非常に興味深い(very interesting)」と賛辞を連発した上で、今回山脇氏が新しく付加された「(東西の)哲学的思想の比較研究」の部分を「とても強力な発想」とされて、特に「昨日ド・バリ氏の報告を聞きながら自分もスピノザの汎神論的な思想との類似性を連想していたので、山脇氏がスピノザに言及されたのを聞いて驚いた」と述べられた。昼食後、この議論が再開され、テイラー氏は、スピノザの後、総体性・統合性の方向と対話的な方向とに分岐したことを指摘された。金泰昌氏がデカルト的自己からバフチンらの対話的自己へと変る可能性について言及した(※)のに対し、テイラー氏はピアジェの研究を援用して「必ずしもデカルト的自己を必要としない」とし(※)、金氏はエリクソンの発展論的自己観について述べられた。さらに、サンデル氏が「この場ではとても大きな合意が存在しているので、今後について具体的な比較研究の提案を聞きたい」と尋ねられたので、筆者は「自由主義─共同体主義の対立を原子論─全体論という観点から捉えれば、このような対立は様々な地域・時代に見ることができる。そして、例えばアジアの哲学においてはむしろ後者の方が優勢だったので、考察の範囲を以上のように世界大に広げれば主流/傍流の描像が入れ代わるであろう」と述べ、ド・バリ氏は、儒教の中に自由の伝統を見出した自らの研究(『中国における自由の伝統』)の方法論について説明された。最後に、自由主義における多元主義的な可能性に関して院生が質問したのに対し、テイラー氏は「自由主義は、原子論で権利基底的な特殊な思想に現在は占拠されてしまっているが、実際にはJ.S.ミルやトクヴィルやフンボルトなどの多様な種類が存在しうる」と答えられ、「(フンボルトについて氏が用いていた)全体論的個人主義(holist individualism) を支持するか?」という筆者の問いに対し、「簡単に言えば、イエス」と答えられた。
総じて、山脇報告に対するハーヴァード側の反応は絶賛と言ってもよいほどのものであり、サンデル氏があまり称賛を繰り返すので隣りにいたテイラー氏に「あなたも同意見か?」と個人的に尋ねたところ、「全く同感だ」ということであった。山脇氏の報告内容自体は、他の国際セミナーにおけるそれと大きく変わるものではない。にもかかわらず、他の地では見られなかったような好反応が得られたのは、サンデル・テイラー両氏はじめ今回の米(加)側参加者と氏との問題意識に共通性が存在するからであろう。率直に言って、従来の(時には懐疑的な場合すらある)反応に少し物足りなさを感じていた筆者にとって、今回の好評は、漸く国際的に正当な反応が現れたように感じられ、内心快哉を叫びたい気持ちであった。勿論、哲学的な立場の相違により、今回のような反応が現れないことも今後あるに違いない。しかし、問題意識が合致すれば、世界的な政治哲学者といえども、素直に賛辞を呈するような価値が氏の描く構想に存することは、我が国の学会の名誉として記憶されて然るべきであろう。その場に居合わせた一人として、特に証言しておきたい次第である。
5、共同体主義と地球的公共哲学──聖性と公共性の再結合
最後に行われたサンデル氏の報告は、今回の会議を組織された中心者として、これまでの論点を踏まえて行われ、共同体主義の代表者らしい、力のこもったものであった。まず第一に、自己について、氏は(1)ある原則に代替する一つの原則という意味においては、共同体主義というラベルを拒否し(たテイラー氏と同意見であり)、(2)地域の価値における多数派主義(majoritarianism)という(文化的相対主義を帰結するような)意味においても自分は共同体主義者ではなく、(3)「埋められない、負荷なき自己(unembedded, unemcumbered self) という(英米思想における)リベラルな思想に対する批判」という意味において始めて、自分は共同体主義者ということができると述べられた。自己は共同の紐の中に埋め込まれているが、ただ性・文化・歴史などによってその紐が多元的であり、その間で衝突が生じるという点においては、限定を付す必要が存在するという。
第二に、おそらくは筆者の前日の質問に応えて、「共同体が世界的・普遍的であり得るか」という問題について見解を述べられた。氏は、「共同体を頂点として、ハイエラーキをなす同心円的な円状の諸共同体」という描像に対しては、リベラリズムに近いとして否定する。モンテスキューを援用しながら、「ある一つの普遍主義的原理が特権的な地位にあるとする考え方は、多様な共同体間の衝突・対立を見逃がしており、誤っている」というのである。逆に言えば、「このような描像でなければ、(共同体主義の地球化という)大きく改訂された共同体主義の考え方に同意できる」と言明された。
第三に、現代の世界像に関して、それに代替するものとして、「主体中心的でない像をいかに提起することができるか」を問題にされ、前日にテイラーが、「触れ得ぬもの」とした「聖なるもの」が、公共的倫理の重要な特徴となるのではないか、と示唆された。
そして第四に、「地球的時代における公共哲学」について、まず、「地球的公共哲学(global public philosophy)が単数形である点に若干の留保を付したい」として、global public philosophies(複数形)というように、「多様な伝統に立脚した複数の地球的公共哲学」という考え方を述べられた。そしてさらに、公共空間再建に対する経済的障害として地球的資本主義を挙げ、その圧力があらゆる種類の公共的機構を侵食していることを指摘し、それに対抗するものとして、(現在は政教分離によって分断され緊張関係にある)公的なるもの(public, civic) と聖なるものとの(何らかの形での)再結合を示唆された。
つまり、この報告は、第一点において自らと共同体主義との関係(いかなる意味において自らが共同体主義者であるか)を明らかにし、第二点においては(筆者の提起した)地球的共同体主義の構想に正面から答え、第三・四点においては世界資本主義に対抗して公共性と聖性の再連携の必要性を主張したものであり、本会議の論点に正面から取り組んでおり、まだ公刊されたことのない見解を開陳している点でも、その価値は改めて述べるまでもない。討論では、まず金泰昌氏が (1)アメリカと日本とは状況が異なり、日本ではそもそもリベラリズムが確立していないから、リベラリズム批判は、わら人形を撃つようなものであり、 (2)日本では「共同体」という概念は歴史的に悪い経験と結びついているから別の言葉が必要であり、(3)「聖なるもの」は、しばしば(タイなどの)伝統的専制体制が体制正統化のために用いることを指摘され、(4)地球的公共哲学の単数形・複数形の件については、単数の文法的区別のない日本語の事情を説明しつつ、サンデル氏の示唆に賛意を示された。サンデル氏が以上の主張に理解を示された後、大沼氏との間では美徳の観念の必要性について合意を見、大沼氏は「アメリカ(的なもの)は尊重すべきだが日本にはあまりにも無批判に輸入され過ぎる」と指摘され、サンデル氏は「ロールズやフーコーの思想が日本で蔓延しているという(山脇氏の)説明を聞く前は、自分の思想を輸出しようという意図などなかった」と軽妙に応じられた。また、ド・バリ氏やテイラー氏は、西洋の個人主義にキリスト教的背景があったことに言及された(※)。
筆者は、ここで大旨次のように述べた。戦後日本の社会科学も、共同体の観念の問題点や自由の伝統の弱体性を論じるところから出発しており、金氏の指摘は今日でもなお妥当であるが、同時に今日の日本では(アメリカの大衆文化の影響もあって)少年等各種の犯罪や学級崩壊・幼児虐待などに現れているような道徳的退廃も進んでおり、それ故に、美徳倫理学などの共同体主義的思想も必要である。日本の状況に合わせて言葉を変える必要があるというのならば、私は「公共体」という用語を提起し、また(共同体という概念は物化・制度化したそれに制約され易いので)人間関係のエッセンスに焦点を合わせて「共同性(主義)」という言葉を用いている。さらに、過去の伝統に拘束される保守性を避けるために、時間軸を導入して、(現在はまだ確立していないが故に想像力によってのみ構想し得る)将来の人類的・地球的共同体の観念を提起している。(サンデル教授が斥けた、普遍主義的・世界公民的共同体の優越という論点については、東洋哲学においての「一即多、多即一」という弁証法(対理法)的論理があるように、私達は地球的公共体の構成員である(国民的等)下位の公共体の構成員でもあるのだから、現象的には、(例えば日本のような)下位公共体の要請によって地球資本主義の論理に抵抗する場合もあり、サンデル教授の見解と必ずしも矛盾しない。最後に、サンデル教授の提起された「公共性と聖性の再結合」という発想は、非常に新鮮かつ啓発的で、ルソーやベラーの公共民宗教(civil religion)の観念を想起した。ただ、日本には共和主義(公共主義)の伝統が少ないし、国家神道のような悪夢もまだ記憶に新しい。そこで、サンデル教授からの示唆を何か頂けないだろうか、と。
その場では「それはあなたがなすべき仕事ではないですか?」と軽くいなされてしまったので、後で個人的に尋ねたところ、「日本の文脈に応じて共同体主義を考えることには大いに賛成だし、共同性主義という発想にも共感を持てる。今後は(地球的共同体主義等のような)そのような方向が重要だろうと自分も思う」ということだった。このように、幸い好反応を得ることができたものの、率直に述べれば、私自身は政治哲学において共同体主義を最大の関心事の一つにしているので、正面から右記のような(共同体主義の批判的発展を提唱する)報告を行って公的に反応を伺い、本格的な議論を行いたかったという気持ちは、拭い難いところである。
この後の討論で特に重要だったのは、次の応酬であろう。サンデル氏が「より実質的な文明間対話の重要性」に言及したのに対し、大沼氏が「哲学者の要求は過大であり、既に国際的に人権については合意が存在しており、それ以上の厚い(thick)合意は不可能である」とされ、テイラー・サンデル両氏とも、人権については大沼氏に同意しつつも「新しい規範を作り出すためではなく、(イスラムに関する場合のような誤解をなくして)既存の合意を支える厚い理解を形成するために文明間対話は必要であり、それによって(ガンジーとキリスト教の関係のように)お互いから学び合うことができる」(テイラー)「環境問題が内的な道徳的・宗教的問題と関連しているように、ある種の目的のためには(人権への合意以上に)より深い関わり方が必要な場合がある」(サンデル)といったような留保も加えられた。
テイラー、サンデル、ド・バリ三氏の参加はこの日が最後になるので、この後発展協議が簡単に行われた。特に印象に残ったのは、次のようなものである。林氏の「哲学は将来世代を救えるか?」という質問に対し、テイラー氏は「哲学は諸科学の多様な領域に関連しているので、さほど大それたものではないにしても、哲学は解決に一定の役割を果たす」と明言された。また矢崎氏が公共性を学ぶことと教育することとの相違について質問されたのに対し、テイラー氏は自らの政治的活動に言及しながら「学ぶことにおいては実践(practice)が本質的に重要であり、常に学び続けることが必要」とされ(※)、サンデル氏は思想と活動とのつながりに言及して、「市民として、また同時に哲学者として、世界に関わっていくことが重要」と答えられた(※)。いずれも、特に目新しい考え方ではないものの、本質を問う日本側の質問に対し、即座に的確な返答をするところに、(観念上の遊戯ではない)実践的政治哲学の営為に真剣に携わっている両氏の真姿を垣間見た気がした。
金鳳珍氏は、前のセッションで、テイラー・サンデル両氏に「儒教から学んだところがあるか?」と質問され、二人は「もう学んだとは言えないが、これから学びたい」というように答えていたが、これは一種の社交辞令と受け取れないでもなかった。それで、最後に会議全体の感想を問われた際に、サンデル氏が次回への提案の一つとして、(今回のように儒学の話を聞くだけではなく)儒学のテキストを具体的に読むことを挙げられたのを聞いて、私は些か驚いた。先の答えが、単なる社交辞令ではないことが明瞭になったわけであり、ド・バリ氏の報告や私達の議論に触発されて、サンデル氏は東洋的公共哲学として儒学を知る必要性を本当に感じたものと推察される。今日の西洋の代表的公共的知識人の一人にこのような関心を呼び起こしたこと自体が、今回の会議の成果の一つと言えようが、よく考えてみると、このような真摯で謙虚な態度は共同体主義の本質に関わることであり、私達にとってもその意義は大きい。テイラー氏が述べていたように、西洋中心主義の傲慢に陥らずに異文化を尊重しそこから学ぶことは、共同体主義の中心をなす発想だからであり、サンデル氏の提案は、それを(東洋文明の軸の一つである)儒学に誠実に適用したものとみなし得るからである。同時に、お互いから学びあうという対話精神が本研究会の基本原則であることを思うと、偉大な西洋の公共的知識人からこのような姿勢が示されたことの意義は、いくら強調しても強調し過ぎることはないであろう。
特に、筆者個人にとっては、このことの感慨は極めて大きなものがある。なぜならば、第一回ケンブリッジ・フォーラムの準備過程において、ある長老名誉教授の(西洋的・世俗的合理主義に基づく)疑念にさんざん悩まされたからである。西洋的合理主義を学びに来る姿勢に慣れている人にとっては、東洋的哲学の意義を主張して西洋側と対等な立場で議論しようとする姿勢が、そもそも奇異であったろうし、それに加えて資料に仏教など東洋思想への言及があるのを見つけて、「怪しげな宣教的集団か」という疑いをかけられたのである。それを思えば、(聖性と公共性との再結合を語り、儒学からも学ぼうとする)サンデル氏の姿勢は、天と地ほどの違いがある。勿論、その後二回の会議によってケンブリッジ側の疑いは晴れ、信頼関係が醸成されてきているが、ケンブリッジ公共哲学フォーラムの所感で述べたように、将来世代や公共哲学などについての温度差はなお残っている。それで、さすが共同体主義者らしいサンデル氏らの言動に、素晴らしい対話相手の出現を観た気がしたのである。そこで私は、最後に次のように述べた。
「昨日夜に私は不満足等と冗談を(テイラー氏に)言ったが、実は今日は非常に満足している。これまで私達は世界の数カ所で議論を重ね、例えばケンブリッジでは知的に非常に高い水準の議論を行うことができたが、今回はそれに加えて、公共性を実現しようという志や積極的熱意を共有することができた点においてまことに素晴らしかった。既に共同体主義の潮流はアメリカから始まっているわけであるが、日本から始まっている公共哲学の運動がこれと連携して世界大の知的運動になっていくことを期待したい。そこで、特にあまりにも素朴な質問で恐縮だが、テイラー・サンデル両氏には、公共哲学の核心をごく簡単に話して頂ければ有難い。」
返事を聞くことなくこの日の議論は終了してしまったが、サンデル氏は個人的に大いに共感を示して下さり、あたかも同志の如き志の交感が確かに生じた気がしたのである。
6、テイラーとサンデルの人物素描──偉人と聖人
三日目の午前中は、公式の会議ではなく、わざわざ日本から自費で訪れた院生達がテイラー・サンデル両氏に質問する機会が、主催者側の好意で設けられた。筆者は通訳の必要も予期して司会役を務めたが、実際は院生諸君の多くは達意の英語で自ら質疑を行うことができ、通訳する必要は全くないほどであった。サンデル氏が驚かれていたように、質問の水準も極めて高く、応答を聞いていて筆者自身にも大いに参考になり、その場に居合わせることができて感謝している。
細かな内容は多岐にわたるのでここでは割愛するとして、ここでは特に印象に残っている点を記しておこう。そもそも、会場がバイキング形式のレストラン兼ラウンジ風の豪華なところで、天窓から柔らかな光がふり注ぎ、なんとも優雅で美しかった。そのせいもあって、その場全体が流麗な調和に包まれ、両氏には一種の神々しい光が射して私達は神聖な祝福を受けているような雰囲気すら感じられた。会議全体を通じての両氏についての印象をここで記しておくと、まずテイラー氏は背が高くて体格も大柄で、(左右両端が上にはね上がっている)眉毛が印象的であった。カナディアンらしく陽気で明るく気さくであり、大きな身ぶりを交えて勢いよく堂々と話す。象牙の塔にこもって思索にこもる哲学者という雰囲気ではなく、現実の政治家としても活躍しうる迫力が伺えた。にこやかながら雄弁に話すうちに調子が早くなり、「後はもう言う必要がなく、当然でしょう」という雰囲気で手を上げ話を止めることがあるので、筆者には結論が把握できないところもあった。総じて、いかにも大人物という威風堂々たる雰囲気を漂わせており、著作から期待していた通り、博学で見識に溢れる素晴らしい人物であった。
ただ、著作から既に氏の考えについて一定の知識を持ちその実績に深い敬意を抱いていたためか、今回の会議及び質疑から、それ以上の新しい見解を聞き、感銘を受けることには必ずしもならなかった、と言うことができるかもしれない。例えば、院生達の質問にも、(テイラーの著作の中にある二つの要素をとり出して)一見緊張関係があるその二つの関係について問うたものが幾つか存在したが、氏の返答はそれぞれの必要性を別々に説明して、その関係については、文脈ないし次元等の相違という以上には答えないものが多かったように思えた。筆者自身も初日に個人的に、テイラー氏が共感を持っている共和主義と多文化主義との緊張関係について尋ねたが、「それは具体的文脈によって考える」という答えであった。あるいは、このような答え方で十分なのかもしれない。しかし、筆者はこれらの緊張関係に際して、その優先順位や緊張解決の方針などについて何か伺うことができるのではないかと期待していたので、滔々とした弁舌が終わって肩すかしをくったような気がしたことも、無くはなかった。そもそも、テイラーは必ずしも体系的な論理を展開する思想家ではなく、鋭い個別論文によって論点を一つ一つ提示し、その積み重ねによって今日のような影響力を持つようになった面が大きい。それ故、「状況の中に置かれている自己」という彼の自己観は、「状況の中で考える思想」ないし「文脈的思考(contextual thinking)とでも言うことができるようなものにつながり、先述のような軽い失望はその特質の裏面に由来するのかもしれない。
一方、サンデル氏については、(著作から受けていた)事前の想像以上に深い感銘を受けた。勿論、氏についても、『自由主義リベラリズムと正義の限界』におけるロールズ批判に見られるような、犀利な哲学的分析力には事前から大きな感銘を受けており、実際、討論においても(例えば大沼報告の際のように)しばしば鋭利な質問を繰り出していた。しかし、それ以上に印象的だったのは、その世界的名声から、もっと大家然とした様子を想像していたのに対し、──テイラーから指導を受けたという年齢差もあって──驚くほど若々しく、素直で、明るく謙虚だったことである。ことに、その眼は印象的で透んだ輝きを放っており、柔和な笑みは周囲に光をもたらしていた。聖性の必要性を主張しておられたように、その根底には宗教(ユダヤ教)的な関心があるように思われた。──失礼ながら、氏は既にある程度頭が禿げておられるが、氏の放つ光は、そのためだけではなく、一種の精神的なオーラのように感じられた。テイラーを大人物=偉人とすれば、サンデルはいわば聖人のような雰囲気すら漂わせており、儒学への関心も似つかわしく思えたのである。
もっとも、単なる宗教者とは異なり、氏が政治哲学者としての旺盛な政治的・公共的関心を持っていることは言うまでもない。院生との問答では特にリラックスして素顔が現れたせいか、この点について一種の道徳的情熱を込めて(結社による)共和主義的ないし公共民的人文主義的な理想を語っておられた。筆者にとって特に新鮮で感動的だったのは、中野君の質問に対して次のように答えた点であった。即ち、「共同体主義が既に政治に影響を与えていることには、良い点と悪い点とがある。良い点は、政治的発言において家族や共同体などへの言及が増え、政治に現実の効果を与えていることであり、悪い点は、非常に妥協して用いられているが故に現実の政策には十分に現れていない点である。いわゆる第三の道も、このような点で不十分であり、道徳性に言及することはあっても政策には反映していない。福祉国家の失敗以来、新自由主義の下で民営化のみ強調され、共通善に関わる公共的施設(図書館、交通機関など)が衰微していて、これは特に貧困者に痛手を与えている。だから、このような公共的施設(インフラ)を再建して、弱者を助けるべきなのである。」──ここには、共同体主義が時に陥る保守主義的色彩はみじんもなく、共和主義的熱意のみが美しく輝いていた。
この時間の最後に筆者にも質問の機会が与えられたので、要旨を紹介しておこう。筆者「アカデミックな質問になるが、日本の読者にとって今回の発言は大きなニュースになると思うので、確かめておきたいと思います。サンデル教授は『自由主義と正義の限界』第二版序文で、自分は共同体主義者と呼ばれたくない旨述べておられるのに、昨日は『AやBの意味では共同体主義者ではないが、Cという意味では共同体主義者である』と言われたので、少し驚きました。この点について、いかが伝えたらよいでしょうか。」サンデル「あのように本で述べたのは誤解を避けるためなので、この場の皆さんのように、共通善と関連する正しい意味で使われるならば、共同体主義という言葉を用いることに何ら異存はありません。」(テイラーも同感の首肯)筆者「同書のロールズ批判は才気あふれた哲学的分析であるのに対し、日本の学界においては『民主主義の不満』はアメリカの文脈に内在した反面、他の地域に通用する普遍的価値を失ったとする意見がありますが、いかがでしょう?」サンデル「アメリカ向けという印象が生じたのは、特定的に、文脈に応じて、具体的に論述しようと意図した結果ですが、確かにそのような問題点が生じたことは事実でしょう。」筆者「昨日終わりに述べた質問ですが、あなた自身の公共哲学の核心ないし本質について、日本の(読者向けに)一言で教えて下されば幸いです。」サンデル「それは、共通(common)や一緒に(together)ということでしょう。」テイラー「そしてさらに、(他のものに)還元することのできない共通善でしょう。」(※)── 残念ながら、正確な記録ではないが、この最後の瞬間に共同体主義の公共哲学の核心として共通(善)という古典的観念を耳にしたことは、(リベラリズムのヘゲモニーにしばしば悩まされる)私にとっては一種の魂の救いの如き感動であり、この一言を聞くだけでもハーヴァードに来た価値があったと思ったほどであった。なぜならば、これこそ共同性主義という観念の中核に他ならず、そこから友愛や連帯による政治的営為の必要性が導かれるからである。共和(公共)主義者としては、フィナーレとして天からの祝福が一段とふり注ぎ、白き鳩が舞い上がったかのような感に打たれたのであった。
7、地球的公共哲学生成への試金石──合意と多様性の共存
最終日午後の発展協議は、ハーヴァード側からはメータ・モルガン両氏及びサンジョヴァンニ氏が参加されたが、既に三人の主役が帰った上、議論も停滞・空転ないし混乱気味だったと言わなければならない。特に、メータ・モルガン・大沼氏は、「主題がもっと具体的・特定的でないと議論が難しい」等と議事進行に要望された。そこで司会の金泰昌氏は、初日に報告された「図解」の参照を求められ、ハーヴァード側は「既に入念に目を通した」と答えたので、筆者も反応を尋ねたが、モルガン氏らは「私は愚かなのだろうか?右翼やファシストでなければ、誰がこれに反対できようか?」と反問された。筆者は、この図解形成過程にあって、将来世代の問題をはじめとしていかに多くの激烈な議論がなされてきたかについて見聞しているので、その旨説明しようと試みた。しかし、(結果として形成された図解をいきなり見せられた)ハーヴァード側にとっては、どうも総花的な美辞麗句に見え、自分達が学識者として具体的に論じる端緒を見出せなかったように思われる。
かくして、このセッションは、さして実質的な議論に入れずに終了した。ただ、空転気味だったこの議論からも、幾つか有益な示唆を引き出せるので、記しておこう。そもそも、日本側参加者の多くにとっても、図解を見たのは初めてだったので、今後の日本の議論にとっても、ハーヴァード側の反応は参考となる。メータ氏は「まず第一に合意の部分を明確にした上で、第二に一部を対話の主題としてとりあげ議論する」という方法を提起されたが、これは傾聴すべきものを含んでいると思う。筆者としては、右にいう「合意」の基盤を形成したいと思ったので、先述したような質問を試みたのである。残念ながら明確な合意には至らなかったが、総花的ではあれ、ハーヴァード側も図解のには大きな異論がないように見えたことは、必ずしも無意味なことではないであろう。対話を重ね、深めていくことにより、明確な合意が「声明」のような形で成立する可能性が存在するからである。
他方で、このような大枠の合意と並行して、各論ないし合意を支える理論的基礎付けについて議論が深められるべきであろう(メータ氏のいう第二段階)。ここで注意すべきことは、次の点であろう。おそらくこの部分にあっては、議論の深化にもかかわらず、なお多様な見解が残りうるが、それを強引に排除すべきではない。一方でプロジェクトの大目的について一定の合意が存在すれば、その多様性は──一見混乱要因には見えても──むしろ議論を活性化し、最終的にはプロジェクトの前進を可能にするであろう。それ故、一見解で無理にプロジェクトをまとめようとすることなく、多様な見解の存在を認め、かつその表現を尊重しながら、プロジェクト全体への協力が可能になるような運営方針を、要望したい。例えば、文献に共通の合意された目的(=大義)に向けての多様な見解が存在することは、プロジェクトのメンバー以外の人々や後世の人々=将来世代にも議論を開き、活性化することにつながるであろう。
この点は重要なので、具体的に述べておこう。メータ氏は、「金泰昌氏の図解における地球的公共哲学、山脇氏の超一国民国家的(トランスナショナル)公共哲学、小林氏のいう(現在の共同体主義とは少し異なり、修正された)地球的共同体主義というように、具体的な形は違っても、日本側には地球的というような大きな枠組に常に帰る傾向がある」と指摘された。これは、実に明察というべきで、地球的公共哲学形成という志において、殆どの日本側参加者には合意が存在しているのである。しかしながら、これは、例えば図解の細部やその理論的説明に至るまで全員が一致していることを意味するわけではないし、またそのような状態を作為的に目指すべきでもないであろう。この第二段階においては、多様な見解が存在することが、全体として日本側の議論を質量ともに向上させ、国際的な評価を高めるのである。
これは、今回の会議の主題や評価とも大きく関連する。前述したように、金泰昌氏は共同体主義の評価や特に日本における妥当性に慎重ないし批判的であるのに対し、筆者はむしろ肯定的・積極的である。筆者のこの見解は、テイラー・サンデル両氏との現実の交流によってさらに強化されたので、この会議を通じて筆者は、今後日本にも、アメリカの共同体主義的公共哲学の成果を踏まえて、(戦前のような国家主義に陥る危険を警戒するという意味での)日本の文脈に即した「日本(型)共同体主義(的公共哲学)」と(その観点からの)地球的公共哲学が必要であるという確信を強め、その樹立に私なりの形で貢献したいと決意した。筆者は将来世代哲学や地球的公共哲学という「大枠=大義」には心より賛成し、これまでそのために全力で協力してきたが、それを基礎づける私なりの思想に関しては、いかなる批判や圧力に対しても、学問的良心に背いて屈することはできない。従って、もしも本プロジェクトをリベラルないしリバタリアン的な公共哲学に強引に収斂させようとするならば、筆者は自発的ないしは強制的に袂を分かつことにならざるを得ないであろう。
この論点は、決して政治哲学上の些細な議論にとどまるものではない。リベラリズムは正に西洋的近代を代表する主流派思想であり、金泰昌氏が(福沢諭吉や「文明開化」に言及され)最近とみに近代的思惟の重要性を強調し始めておられるのに対し、筆者はその重要性を確認しつつも、なお近代の限界を超えて、環境や倫理的退廃などの今日の新しい問題に立ち向かう必要性を確信しているからである。丸山眞男をはじめ戦後啓蒙の立場から出発した筆者にとって、自立・他者性・法治等近代的思惟の重要性を強調することには何の異存もなく、場合によっては(新国粋主義などに対しては)自らその役を務めたいほどである。にもかかわらず、それだけでは二十一世紀の課題には応えられないと思うが故に、近代批判の契機を共有する共同体主義者達と連帯し、新時代の公共哲学形成に寄与したいと考えるのである。
思うに、最後の発展協議における混乱は、図解が初めて提示されるという「画期的」な出来事があったが故の、意義ある波乱であり、地球的公共哲学の生成途上における試練と捉えるべきであろう。多様性・多元性はリベラリズムの旗印であると共に、テイラーら共同体主義者も等しく尊重するところである。大きな合意の下における意見の多様性が存在してこそ、世界に誇るに足る地球的諸公共哲学(複数形)が真に生成し得るであろう。従って、そのような状態が実現し得るかどうかという点は、正に本共同研究会の運命を占う試金石の役割を果たすことになろう。そもそも、多様な見解の共存は、対話の場の特徴であり、本共同研究会の対話精神の顕現に他ならないであろう。対話的生成過程における強制的一元化は、生ける対話精神を殺し、生成過程を流産させてしまいかねない。会議後、金泰昌氏は、意見の相違を尊重するという方向性を示唆された。これは筆者も大いに望むところであり、大賛成である。これまで(主催者側以外では)もっとも真剣に本共同研究会にコミットしてきた者の一人として、このような形で合意と多様性の共存が真に実現し、今回の波乱を乗り越えて本共同研究が今後も発展し続けてゆくことを祈って止まない。
※参加者の発言は、いずれも要約である。記憶ないしメモに頼って記したので、いずれも完全に正確ではありえないが、特に不正確な可能性がある箇所には(※)を付した。
(『公共哲学共同研究ニュース』将来世代国際財団発行、将来世代総合研究所編集、2000年4月1日、第9号、2-12頁、20001年2月改訂)
なおこの会議についての紹介としては、上記のニュース・レターの他に、山脇直司「ハーバード・ファーラム『地球時代の公共哲学』を終えて』(『UP』 338号、2000年12月、6-11頁)がありますので、御興味のある方は御参照下さい。また、第6節で訳した、院生との質疑応答については、『千葉大学法学紀要』第16巻第1号(2001年)に、その重要な部分を掲載する予定です。