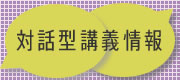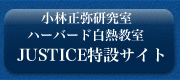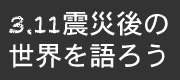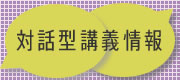

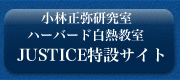

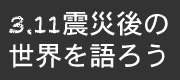
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 日韓公共哲学共同研究会所感 | Home | 「ハーヴァード地球的公共哲学セミナー所感──共同体主義者達との交感」 »
Posted: admin on 10:45 pm | 書籍・雑誌情報(Books, Journals, Magazines), 論文・書評・所感など
小林正弥(千葉大学)
1. 総括的印象──信頼の成果
今回のフォーラムは、ケンブリッジ・フォーラムとしては2回目であり、既に双方に相当の信頼感が醸成されていたため、(韓国や)特に中国の場合に比して、(2日目に朝のタクシーが遅れたというアクシデントを除けば)トラブルや緊張も殆どなく、終始、友好裡に進められた。第一回ケンブリッジ・フォーラムにおいて、年長の名誉教授(P.ラスレット氏)達との(舞台裏や当日における)激しい確執に苦労したことを想起すると、(1回目にも協力的だった)J.ダン教授自らがイギリス側の中心となって組織されただけあって、今回のフォーラムは全く別の地であるかのように平穏であり、ケンブリッジには特別な思い入れがある筆者にとっては、感慨深いものがあった。初めの不信感や衝突を乗り越えて対話を継続する価値を、改めて実感した次第である。
また、具体的な場所としても、前回はケンブリッジ市内のガーデン・ハウスホテルで行われたのに対し、今回は、(フォルテ・ポストハウスホテルで行われた)初日を除き、残る3日間は(ダン教授やR・ハリソン博士が所属する)キングス・カレッジの最も格式の高いセミナー・ルームの一つ(ソルト・マーシャム・ルーム*)で行われた。ケンブリッジは、古い伝統を誇るだけに、大学の部屋も古く、日本の感覚からすると(雰囲気はあるものの)頂けない所が多いのだが、今回の部屋は、私が見た中で最も素晴しいものの一つであり、充実した内容を象徴するような壮重な雰囲気に包まれ、ケンブリッジの正に中心の一室であった。さらに、前回に比して、2─4日継続して出席した参加者が多く、ダン教授をはじめとするケンブリッジ側の厚遇と熱意とが感じられた。
そして内容的にも、今回のフォーラムは質的に前回を遥かに凌駕していたように思われ、国際フォーラムとして最高の水準にあったことを筆者は信じて疑わない。韓国や中国の場合は、歴史問題や国情の相違が議論の背景ないし焦点になり、その観点から有意義な対話が行われたのに対し、ケンブリッジにおいては、そのような政治的文脈とは離れて純粋に学術的な討論を行うことができた。しかも、もとよりケンブリッジ側参加者は、前回から、既に世界的名声を博している人々から成っていた上に、(「自己と将来世代」という前回の主題が比較的新しいものであったのに対して)今回の主題はイギリス側にとっても、当然、以前から意識されてきた重要なものであるだけに、イギリス側の報告・討論の水準も、さすがにケンブリッジの名にふさわしいものであった。従って、今回のケンブリッジ・フォーラムは、私達の日本における研究会の成果を世界において問うための、いわば最高の学術的舞台を提供してくれた、と言うことができよう。総じて、今回のフォーラムは、前回の成果の上に立脚し、それによって形成された──ダン教授と金泰昌氏(日本側は以下「氏」で統一)が共に強調される──「信頼」の勝利であったと思われる。
2. 日本の東西における公私観──拙論を中心にして
報告の順序を離れて、内容を概括的に整理してゆきたい。今回のフォーラムは、「公私についてのアジアと西洋の諸概念についての会議」と題されており、その主内容は日中欧印における公私観であった、と言うことができよう。
まず、初日には、金泰昌氏の提案に即して、筆者と金鳳珍氏とがそれぞれ──日本の中の東西(東京・京都)を代表する思想家として選び出された──丸山眞男と和辻哲郎の公私観について報告した。拙論「日本戦後啓蒙から新世紀の新啓蒙へ──丸山眞男の政治理論の公共哲学としての再定式化」は、間宮陽介氏の近年の丸山論(『丸山眞男──日本近代における公と私』筑摩書房)などを踏まえた上で、まず丸山眞男の仕事を前期(40年代後半から50年代初め)・中期(50年代後半から60年代後半)・後期(70年代から病没まで)と3つに分類し、それぞれの公私観の特徴を公私分離(自然から作為へ)・逆説的公私観(私の上の、私のための公)・文明論的視点(古層論)と整理した上で、ハーバーマスと対比して丸山の逆説的公共観の意義を(金泰昌氏の活私開公の観念につながるものとして)指摘した。さらに、溝口雄三・渡辺浩両氏の説を簡単に紹介しつつ、おほやけ(日本)・公(中国)・公共(西洋)という概念の習合(シンクレティズム)を克服して総合的混成体としてこの概念を用いることを主張し、丸山を超える方途として、自然的作為・生成的結成・ルソー的新公共主義という3概念を簡単に提示して、丸山ら戦後啓蒙の試みを新世紀において再定式化することによって、(戦後啓蒙の素志に反してタコツボ化してしまった)学界の現状を打破するという、学際的な新啓蒙への展望を述べた。
イギリス側参加者にも丸山についての知識はある程度存在していたが、それは主として西欧的・近代的知識人という前期の丸山像であり、筆者の紹介した中・後期の丸山の業績は新鮮だったようで好評だった。例えば、フォーラム後に会ったR・ゴイス博士も、丸山の古層論に一種の歴史的な系譜学としての関心を示し、(非西洋地域における)「近代政治についてのケンブリッジ・テキスト」(ケンブリッジ大学出版局)の一冊に丸山の巻を加えるよう働きかけることを示唆された程だった。日本では未だに前期丸山像に偏した紹介・擁護・批判が跡を絶たないので筆者は中・後期の意義を強調したのであるが、イギリス側のこのような受け止め方は私にとっても啓発的で、今日の思想状況における丸山の意義を新しく開示したように感じられた。また、丸山自身や福田歓一氏とも会ったことのあるJ・ダン教授は、大旨(以下同様)「自分は戦後における丸山の意義についてかねてから認識しているが、戦後から数十年経った今、若い世代からどのように受け止められているのか」と問いかけられ、「無関心な人が増えた一方で、丸山死後にポスト・モダン派が批判の格好の標的として利用している」と答えると、「ポスト・モダンの思想は論外ながら、丸山は日本的なものと取り組んだという点において極めて日本的な思想家だが、日本の文化的資源(Japanese cultural resources)を用いた試みは、その後現れていないのか」と尋ねられた。概して、日本における丸山論は、しばしば信奉者の護教論と(ポスト・モダン派の如き)言い掛かりのような非難とに分極化する傾向があり、(後者は論外ながら)丸山に親近感を持つ日本通の外国人達も、時に前者にも辟易としており、「丸山の議論を承継しつつ新しい展開を試みている人がいないのではないか」という質問を受けることが少なくない。ダン教授の質問も、丸山らの仕事に敬意を示しつつも、時代の変化に応じて新しい展開が行われることを自明視して、「日本の文化的資源」を活用する可能性に興味を示すものだった。(自然的作為や生成的結成などの観念による)丸山の洞察の再定式化という展望は、正にこのような方向を目指すものであり、当日は、「東洋や日本の文化的資源を用いる試みは、ややもすると国粋主義の罠に陥り易く、現に今日の日本ではそのような主張が再び現れている。そのような危険に陥らないで文化的資源を活かす試みは、数少なく、おそらく私達の試みは、そのような先駆的な試みと言えるだろう」と答えたのだった。さらに、中国専門家で日本にもしばしば訪れるマクダモット氏も、日本の学界がタコツボ化している状態を良く御存知で、西洋的観点から日本には総じて批判的であり、当日は(私の語った展望が)「制度的変化・社会的変化とどのように関連ないし影響するか」という点について質問された。21世紀の課題に属するこのような質問に明確に答えるのは容易ではなかったが、ともあれ知日派の西洋人の鋭敏な質問に接して、筆者としては改めて戦後啓蒙の再定式化という方向性の正しさを確認した次第である。
金鳳珍氏の「和辻哲郎の倫理学における公私」は、(自己・個人性と他者・社会性・共同性とからなる)弁証法的人間観や(多層的・ピラミッド的な)「世間」の公共性などの点について和辻の議論の意義を確認しつつも、結局その「全体性」の観念が日本という国家内部に極限されており戦時の滅私奉公につながるものであった点を、和辻の限界として指摘した。この報告は、鋭利な批判的分析となっており、筆者自身にとっても、(全体論的発想を支持するが故に、期せずして到達していた)和辻との共通点と(当然ながら残る)相違点を自覚する上で裨益するところが多かった。イギリス側との討論においては、ダン教授が「丸山は(西洋人にとって)理解が容易だが、(戦争の勝敗という文脈を離れて)何を和辻から日本人以外の人が学べるのか」と質問されたのが印象的だった。報告が単純な和辻礼賛に陥らずに(後半で)和辻批判を行っていたため、逆に(報告の前半で的確に述べられていた)和辻の思想の利点、例えば西洋批判・(空間性の強調による)ハイデッガーの乗り越えといった要素が十分に伝わらなかったのかもしれない。この点に些かの憾みは残るものの、逆に和辻について知識のある日本側内部での討論は活発で、国家主義的共同体主義と多文化的共同体主義という対比の文脈におけるボダンとモンテスキューに対する和辻の評価(山脇直司)や時間性も強調する丸山・東京学派と空間性を強調する和辻・京都学派との対比(金泰昌)などにつき、興味深い議論が交された。
3. 中印の公私──イギリス・オリエンタリズムとの論争
日本側の以上の2報告は、いずれも日本固有の公(おほやけ)観念に批判的だったので、この点ではイギリス側と論争は起こらなかった。これに対し、日英間で見解の相違が明確になってきたのは、2日目の後半に行われた中国の公私観についての討論からである。ケンブリッジ大学の東洋研究所(オリエンタル・スタディーズ)に所属する二人の報告は、大きくは似た方向性を有しており、中国において実際に公の観念が果たした機能に懐疑的で、主として官僚制内部の規律やその正統化の役割を果たしていたことを強調するものだった。
まず、マクマレン教授の「中世中国の公益・私益の理想──後の伝統へのその影響」は8世紀末から9世紀初めの唐時代(とその時代に発達した合理的官僚制)に焦点を合わせ、公(gong)の概念は主君ないし統治者の意味から始まって、「私(si)」に優越する(宇宙的)不偏性・公平性・開放性・均衡性などの規範的な意味を持つに至り、皇帝にも理想を示して公益や人々の福祉の観点から無制限の権力の行使を掣肘する思想的機能を持ったものの、実際の具体的文脈としては──古典が提示するようなユートピア的理想よりも──(ヴェーバーが官僚制の特徴とした)公平性を官僚制内部及び皇帝権力との関係について表わすものだった(が故に、近代になって中国には西洋的な意味におけるpublicな精神が欠如していると指摘されることになった)、とした。これに対し、仏教やヴェーバー理論との関係などが議論されたが、特に重要だったのは、ダン教授が日本の公観念との違いについて質問してからの応酬であろう。マクマレン教授は、日本の公観念が世襲的天皇制及び政府と結びついているのに対し中国の方が科挙制のように開放的であったとし、溝口説に言及した金泰昌氏の質問に対しては、日本では天が日本人と結びつくのに中国では(中国人といわずに)人一般と結びつくとして、日本に比して中国の公観念の持つ普遍性について述べて応答した。しかし、「中国の公観念が国を越えられるか」という金泰昌氏の質問に対し、「ユートピア的には可能だが、現実的ではない」と答えたように、マクマレン教授は、日中の相違点については(聞かれれば)ある程度認めるものの、そこに力点はなく、総じて中国の公観念の歴史的・現実的機能について醒めた見方を強調した。個人的会話で確認したところによると、実はケンブリッジの両氏は溝口説について事前に知悉しており、(日本の公観念に比して中国の公観念の有する意義を強調する)溝口説は中国の公観念を理想化し過ぎているとみなし、それに対する現実主義的(リアリスティック)な観点からの批判をも含意して当日の報告に臨んでいたのである。
それでもマクマレン教授の場合は、その穏やかな人柄もあって、報告も歴史的考察に限定されており、抑制的で批判は暗示されているに過ぎなかったのに対し、おそらく年長のJ・マクダーモット博士の「中国における公私分割の解決と問題」の場合は極めて直截であり、西洋的観念からの典型的な東洋批判の型をなしていた。即ち、中国においては、対立を曖昧にして非政治化し変動に抵抗する傾向があり、公観念も、官僚・政府を正統化する官吏のレトリックであり、儒学的な道徳的観念は政治的現実というよりも陳腐なイデオロギー的正統化であった。さらに、16・7世紀以降には新儒学は変容し(*)、結論として、(公を道徳化する)理論と現実は異なり、その隔差は時代が下がるとより明確になり、人々の抵抗の声も統治者に聞かせるのは難しく、公に関連する政治的変化は、非開放的な政治的頂点のみにおいて起こる、とするのである。マクダーモット氏の議論は明快な反面、図式的に過ぎて歴史的な挙証も少なく、荒っぽい印象は否めなかった。ダン教授が討論の途中で「西洋的観念から単純に斬るのは問題で、慎重であるべきだ」とたしなめたほどである。従って、日本側との議論もあまりかみ合わず、金泰昌氏の公私の背反性や破私立公(毛沢東)の危険性についての質問に対しても、公私は混合していて完全に分断されておらず、破私立公のような危険性は、あり得るとしても(それは実際にはレトリックに過ぎないのだから)普通は存在しない、と答えるほどだった(*、金泰昌氏は勿論不同意)。私も業を煮やして、溝口説や丸山真男の「忠誠と反逆」に言及しつつ、日本と異なる易姓革命の事実や、中国的公観念に啓発されて「反逆」を実践した志士などの存在を指摘して反論したが、説得的な返答は返ってこなかったように感じた。溝口氏のような中国専門家が今回は日本側にいなかったため、これ以上議論を詰めることはできなかったが、傍聴していた台湾のモンハン・ツァイ氏も、農民からの王朝への反乱の存在を指摘して批判を加えてくれたことは、特筆に値しよう(*)。
要は、日中の公観念の、微妙ながら重要な差異を認識するところから私達は日本での議論を始めたのに対し、ケンブリッジ側は中国をも批判的に研究しているのでこのような食い違いがおこったわけであるが、ダン教授がいみじくも上のように指摘したように、イギリス側の中国(の公観念)観に若干オリエンタリズム(E. サイード)の残滓が混じっていた嫌いは否定できないであろう。この点において、日本側は議論の正確さと精密さを誇ることができるわけである。これに関連して、日本側は溝口説に従って中国の公観念に今日の公共哲学を考える際の重要な伝統的遺産=「文化的資源」を観ていたのに対し、イギリス側の見方では(日本のみならず)中国の公観念もその意義を大方否定されてしまうことになるから、東アジアの「文化的資源」の中に公共哲学への手掛かりを見つけることが難しくなってしまう、という難点が挙げられる。それでは、イギリス側は、どこに公共哲学の歴史的起点を求めるのであろうか? ケンブリッジのオリエンタリスト達は、暗に西洋の公共観念を東洋裁断の基準にしていたように思われるが、後述するように、今日の知的状況では事はさほど簡単ではないのである。
最後に、インド人であるS.カヴィラージ博士(ロンドン大学東洋・アフリカ研究所)による、インドの公私観についての報告も、以上の論点と関連するので、ここで簡単にふれておこう。博士は、比較の観点とインドの知的資源とに留意しつつ、方法論的には──共通性という普遍的な広い意味ではなく──狭義の公共性、即ちハーバーマスなどが描いたような西洋的公共性に限定して報告を行った。すると、インドの伝統にも信仰やアドヴァイタの中に広義の公共性に対応する観念はあるものの、カースト制等に妨げられて狭義の公共性は存在せず、イギリス植民地時代に西洋から流入して上流階級が受容した公共性(publicity)の観念が出発点ということになる。純粋にリベラルで西洋的な今日のインド政体は既に25─30年位も作動しており、腐敗によって辞任した人の妻がすぐ圧倒的な賛同で選出されるといった事例が物語るように(*)、公共性の手続き的過程の側面には無関心であるが参加の側面では民主主義が機能しており、博士は長期的には楽観視している、という。討論では、金泰昌氏への応答においては、ヒンズー的理論の将来世代に対する含意や国外の議論への対応などが説明され、ダン教授が触発されて「日本の成功についての説明は、(日本人以外の)人類という種全体にとって、重要な問題だ」と述べられたのが印象的だった。筆者にとって、カヴィラージ博士の説明は、西洋思想とインド的伝統との並存という点において、丸山の古層論ないし日本の習合主義シンクレティズムの現象を連想させ、興味深かったが、その観点からすると習合の将来について些か楽観的に過ぎるように思われた。そこでその旨質問すると、「非常に重要な質問だ」として、ヒンドゥー原理主義の危険性や、経済発展を契機に氏がマルクス主義的革命論からトクヴィル的革命論に転じたことなどを語ってくれた。博士の場合、(おそらく)イギリスで博士号を取得したことからもわかるような、西欧的教養のため、公共性論を狭義の西洋的概念に限定して論じており、それ故に丸山真男ら戦後啓蒙の議論の型と共通性が存在している。その反面、西洋的観念を前提としているので、公共性の概念(と民主主義の関連など)について深い吟味を欠き、「インドの文化的資源」の点では結局いわゆる欠如論に終ってしまい、西洋に対するインドからの貢献とはなり得なかった点に、憾みが残ると言わざるを得ない。
ケンブリッジ側の中国研究者にオリエンタリズムの影が感じとれたように、博士のインド観にも類似の問題を指摘し得るかもしれない。この点で、日本の公共哲学共同研究会で報告したシャブシヴァナンダ氏は、ヒンドゥーの宗教的伝統の内部から積極的に公共哲学への示唆を語っておられ、対極的であった。この双方の視座は、日本における「東西」たる丸山と和辻に対応しており、いわばインドにおける「東西」のようなものとして、共に尊重されるべきであろう。
4. 哲学・経済学・公共政策──積極的提言(日)と懐疑的・消極的応答(英)
他のケンブリッジ側報告は、いずれも西洋的公私観にふれるものだったが、同時に理論的側面を含んでいたので、後に述べることにしよう。前述の2報告以外の日本側報告は、いずれも理論的色彩が濃いものだった。山脇直司氏の「21世紀への超(トランス)─国民国家的公共哲学の鍵概念と方法」は、(氏が既に韓国・中国で語ってきた)多次元的自己の概念に加えて、新全体論的発展概念や全体論的・対話論的・生成論的個人主義などを鍵概念として提起し、(オックスフォードのPPEを発展させたような)PPEC(哲学、政治、経済、文化研究〔カルチュラル・スタディーズ〕)という包括的・学際的新カリキュラムを大胆に提唱する意欲的なものだった。これに刺激され、ケンブリッジのSPS(社会政治学部)の中心の一人であるダン教授は長い応答を行われ、おそらく自らも中心的一員として組織してきたカリキュラムを念頭に置いて、山脇氏の全体論的プログラムの利点を認めつつも、(ヘーゲル的な)絶対知や存在論に疑問を呈されて、より現実主義的な立場から、より弱いプログラムを対置された。さらにR・ゴイス博士は、大学におけるダン教授との共同セミナーを彷彿とさせる形で、(表現が洗練され過ぎていて英国人大学院生にすら聞きとりにくいと言われる)ダン教授の意を汲んで、ハイデッガーを援用しつつ、人間の限界の自覚について質問された。これらに対し、山脇氏は、ヘーゲル的な絶対知は拒否することを明言しつつ、ハーバーマス的な「ポスト形而上学的思考」にも組しないことを主張され、金泰昌氏は、生成論の可能性を示唆されて、(教授のためではなく)学生の必要に応える大学への変化を主張された。これは、おそらく本セミナーで最も白熱した議論の応酬であり、日本側の積極的で将来思考的立論とケンブリッジ側の消極的で慎重な姿勢との対照が、最も鮮明に現われたセッションだったと思われる。それ故、筆者は、第l回セミナーにおける激烈な論争を想起し、「日本の学界のタコツボ的状況は、(既に一定程度学際的な)ケンブリッジに比して、一層本格的に学際的改革を行う必要が存在する」旨説明して、ケンブリッジ側に理解を求めたのであった。
似た対立関係は、塩野谷祐一氏の「福祉国家における公私」でも現れた。氏が、公私に加えて「個人/制度」という軸も加えたモデル(PPIIモデル)を提起され、その観点から日本の福祉国家の危機を道徳的(退廃)・政治的(公共理性の欠如)・経済的(過度の拝金主義)という3点を挙げて説明され、(福祉国家の公的領域に経済的論理を導入することによる)その再建のために、──従来の政治・産業・官僚制(PIB)に代えて──政治・経済・道徳(PEM)の三角形を形成することを提言されたからである。ダン教授は、PEMの構想に共感を表明されて、「どのように道徳化するか」ということは実に深く重要な問いだとしつつ、「それに対して今日の西洋は確たる解決策を持っておらず、そのことは私達がいかに深い困難の中にいるかを示している」と述べられた。さらに、教育や資本主義との関連が論じられた後、塩野谷氏の(戦後教育の結果としての)道徳的退廃という主張に対し、足立氏の疑問を踏まえて、ゴイス博士が「道徳の退廃と歴史的変化との混同の可能性」について問われた。ケンブリッジ側に経済学者がいなかったためもあって、経済そのものよりも道徳に議論が集中した嫌いはあるものの、ここでも日本側が、道徳性の復興を積極的に主張したのに対し、それに懐疑的ないし悲観的なケンブリッジ側という構図が再現したように思われた。
以上の2報告において日英間の対立の構図が鮮明であったのに対し、イギリス側から相対的に抵抗感が少なく、むしろ日本側内部で興味深い議論が交されたのが、足立幸男氏の「公共政策研究への経済的アプローチの限界」である。足立氏は費用・便益分析の意義と限界を論じた後、「広義の純便益の概念・十分に良い補償という考え方・経済的誘因の考慮」などを公共政策研究に組み入れることを主張された。ここにおける公共性や効率性の概念について金泰昌・塩野谷祐一両氏と討論がなされた後、M・レイン女史が功利主義的アプローチの一種と位置付けて、憲法論的アプローチとの関係を問題にし、足立氏は功利主義的なR・グッディンの影響を受けていることを明らかにされた。(功利主義的伝統の強い)イギリス側から異和感が少なかった理由の一つは、ここに求められえよう。特に(おそらくグッディンに示唆された)選好洗濯(preference laundering)の考え方は、ゴイス博士らの関心を呼んだが、金泰昌氏は、(それを始めとする)公共政策研究が人々の操作に用いられる危険を指摘され、ダン教授も分析的テクニックとしての利点・問題点双方が存在するとして、「誰が権力を行使するのか」という論点を指摘された。「公共政策と公共哲学との相違点」について質問した筆者の関心も、これらに沿うものであった。総じて、足立氏は、単なる経済的アプローチを批判し、それと区別して、費用・便益分析の進展による公共政策研究の前進を主張されたが、経済学者・塩野谷氏すら(価値に関わる)政策目的の決定が先行することを指摘されたように、政治学的観点からすると、なお手段的・道具的理性に関わる経済的効率性に議論の重点があったという印象は、否み難いように思われる。
5. 公私の理論──リベラリズムとその批判
経済的側面にかなりの比重を置いた日本側に比して、ケンブリッジ側の他の報告は、いずれも哲学的ないし政治思想史的なものであった。まず、若手のM・レイン女史の「市民の安全性──政治思想における、公私の間の、安全性の、問題を孕む位置」は、リベラル(及び共和主義)の公私二分法に疑問を呈し、(通常私的とみなされる)消費行動と(通常公的とみなされる)市民的行為とに公正という点で共通性がある、と主張する。さらに、──例えば、匡正的正義の実現までの痛みを考えれば明らかなように──ノジックらが最小国家論で考えた以上に、安全性という価値は重要であることを指摘し、(従来は公的とみなされてきた監獄について、私的な要素が加わる)「民営監獄(private prison)」を例にして公私の分類の不明確性を論じた。この刺激的な議論に対し、まずイギリス側内部で安全や私的監獄について活発な討論がなされたが、日本側からは金泰昌氏が、超国家的公共性を考える上で、安全性という観点に従来の西洋理論にない魅力を見出し、高く評価された。レイン博士の返答は必ずしも質問に呼応するものではなく、──市場における公共性という観点(への萌芽)を評価した上で──公私問題についての含意について問うた筆者の質問にも「大きすぎる問題でまだ答えられない」とされたように、まだ理論として完全には熟していないという印象は否めなかったが、安全性という観点の提起及び着目は本フォーラムの一つの成果であった、ということができよう。
年若いレイン女史とは対照的に、残る二人は、今日のケンブリッジの政治思想・哲学の研究・教育体制の根幹を担う中心人物だけに、その報告はケンブリッジ側の理論水準を代表するものとみなし得よう。まず、(筆者が在英時にもっとも丁寧に御教示頂いた)R・ゴイス博士の「無恥、精神性、そして共通善」は、まず(1)西洋史からディオゲネスの無恥、(2)(ローマの公益より自らの私益を優先した)シーザーのルビコン越え、及び(3)アウグスティヌスの回心(の告白)を例として挙げ、公私には少なくとも(1)皆が物理的に知り得ること/他人に影響のないこと、(2)皆に関わる公益/部分的私益、(3)内面的に当人のみが知り得る存在論的・認識論的私秘性、といった3種類の意味が存在することを説明した(*)。そして、これらは(私有財産への不干渉を内実とする)今日のリベラリズムの用法とは異なったものだから、公私の概念に統一的用法は存在しないし、その概念によるリベラリズムの正統化は誤っている、と主張したのである。前半で歴史的3事例を挙げることによって西洋における公私の多義性を明らかにした手法は、生彩に富み鮮やかだったし、ここまでは異論は少ないように思われる。ただ、ダン教授が指摘したように、そこから急転直下して今日のリベラリズム批判に向かう結論は、(プラグマティックなマルキストを自称した)ゴイス博士特有のものであり、ダン教授の結論とは必ずしも同一ではないかもしれない。直接伺ったところによると、ゴイス博士は、「中立性」を謳うリベラリズムの偽善が好きではなく、リベラリズムからは道徳性を語ることはできないと考えている(*)、ということであった。
ダン教授の「公と私──規範的地図と政治的・社会的戦場」は、辞書により歴史的な用法を概観した上で、まず公と私との領域をめぐっての様々な歴史的な争いの根源にある問題は、政治的強制権力への服従ないし制限である、という現実主義的観点を強調した。そして、「私」が浸透してきている反面、(歴史的には「私」に対して優越することが自明視されてきた)「公」の規範的基礎が堀り崩されて「公」が動揺している事実を指摘しつつも、結論としてはむしろ逆に、(ウォーターゲート事件からクリントン・スキャンダルに至る)統治に関わる私秘性(privacy)の崩壊を問題とし、それを妨げる文化的資源として(歴史的に私秘性を擁護してきた)キリスト教を挙げて、その影響が将来失われると私秘性を守る規範的根拠が失われてしまうだろう、とするのである。
ダン教授は、行論中で(「私」の優位性を唱える)リベラリズムも(その論敵たる)共同体主義も、経済的・政治的・社会的因果性を捉えていない点において共に不正確であるとして斥けているが、筆者には、その議論がなお公私二分論の枠内にとどまっており、「公」の動揺を指摘しつつも結局は「私」の崩壊への懸念で終っている点において、なお──アメリカ的リベラリズムとは違うにしても──自由主義的な公私論であるように思われた。「私」の崩壊の防波堤をキリスト教に求める点は、いかにも(J・ロックの神学的側面を明らかにした研究で一躍名声を博した)ダン教授らしく、ロック的な自由主義の色彩を感じたのである。ゴイス博士との差異を感じた所以である。そこで筆者は、政治的無関心に対する丸山の若干共和主義的な対応などに言及しつつ、以上の点について、口火を切って質問したところ、ダン教授はその(自由主義的という)解釈をいなして斥け、ブレア首相の例などを挙げつつ、政治の範囲を越えた社会の問題の存在を指摘された(*)。これに対し、ゴイス博士が公私の関係について、「(ダン教授の強調した)権力をめぐる公私分離や人々の心理的動機という二次元の他、道徳的・イデオロギー的・想像的な構成という、もう一つの次元があるのではないか」と質問されたのは、筆者の質問の意を汲んだ助勢で、暗にダン報告を批判したものだったように思われたので、それに対してダン教授が返答する暇(いとま)がなかったのは、残念だった。この後、山脇氏の質問を機に、議論はキリスト教との関連に移り、ダン教授が西洋のキリスト教を念頭に置いているのに対し、「韓国やフィリピンなどアジアのキリスト教は公共的役割を果たしている」という指摘が日本側からなされた。山脇直司、金泰昌両氏のこのような指摘の正しさをダン教授も認められた。
6. 総括──日英の温度差と最高の賛辞
最後に国内の公共哲学共同研究会における発展協議に相当するものが、金泰昌氏の用意してこられた「現在及び将来世代のための地球的公共哲学の基本的問題」をめぐって行われた。カヴィラージ氏が共同性(common)と公共性(public)の相違について述べ、ゴイス氏は「公共性の概念は歴史的にあまりに多様な意味群から成っているので、単に用語のみについては答えられず、用法によって区別することが必要だ」とされた。レイン女史は、ヴィトゲンシュタインの私的言語論に言及して「公的知識と私的知識を区別することはできない」と論じたが、これに対し、ダン教授が業を煮やしたように語気強く反論され、例えば自然科学の領域で知識が私物化してしまうという問題の深刻さを指摘して、金泰昌氏の問題提起の重要性を確認された。
このように、ダン教授は、公共哲学の重要性に理解を示され対話に積極的だったものの、第4節で言及したように、(ダン教授自身も含め)イギリス側と日本との間に、総じて積極性の点で温度差があったことは否めない。レイン女史の議論は新鮮だったが、女史自身は公共哲学の必要性については十分に理解しておられなかったようである。ダン教授は、ゴイス博士が「(直接見た人の中で)世界で最も懐疑的な人」と評するほど、悲観主義的な見方をするのが例であり、キリスト教的で道徳的関心を強く有するものの、キリスト教の未来には悲観的であり、同様に公共哲学の可能性にも単純には賛歌を送れないのも、むしろ当然であろう。その人柄をある程度知る筆者にとっては、時折垣間見せる熱意の方にむしろ驚いたほどである。おそらく、ゴイス博士は、今日のリベラリズムに批判的で、キリスト教のみならず他の諸宗教や(それに対応する)ルソーのような世俗的思想にも公共性の道徳的根拠を認める点において、公共哲学や共和主義に最も好意的であると思われるが、博士にしてなお、公共性の多義性の分析はリベラリズムの公私観念の批判に目的があり、公共性の観念を氏独自の観点から規定して積極的に用いるには至っていなかった。政治思想史のケンブリッジ学派は共和主義研究で有名なので、筆者は共和主義をめぐる議論を期待していたが、(レイン女史の批判的言及以外には)殆どふれる報告がなかったので、訝しく思い、後でゴイス博士に質問したほどであった。
しかし、このような温度差は別にして、今回のフォーラムが学術的に極めて充実した最高水準のものであったことは、疑う余地がなく、このような評価は、会議中及び会議後にケンブリッジ側からも異口同音のように繰り返された。例えば、ゴイス博士は、最終日の翌々日(17日)に氏の自宅で私の論文について意見を伺った際、会議全体に対しても次のような感想を述べられた。ダン・ハリソン両氏との一致した評価として、今回の会議は、これまでケンブリッジで行われた国際会議の中でも最高度の水準のものであった。また、会議設定の仕方も素晴しく、長過ぎて退屈になることも短すぎて議論ができないこともなく、このことは参加者が殆ど最後まで継続して参加したことに表われている。また、英語能力の高さに驚くと共に、(一人一人が何を考えているかわからないことの多い)日本人との会議の中では異例なことに、日本人間での意見対立も含め、日本側の意見が明確にわかり、最後には日本側参加者の一人一人の個性までわかるようになった、というのである。さらに、内容としては特に、(1)東アジア・西欧に加えて、インドの観点がとりあげられた点、(2)哲学・政治学に加えて(足立氏の述べた選好洗濯のように)経済学の観点が加わった点、(3)家族という問題が論じられた点、について言及されて前進と評価され、この会議の結果、(4)ケンブリッジ側と日本側との間の差異と同時に共通点も浮かび上がった、とされた。差異は、(山脇報告の討議に典型的に表われていたように)日本側には形而上学的・存在論的議論が存在するのに対し、ケンブリッジ側はそれに懐疑的であるという点であり、共通点とは、日本側も(アジアの公共性の概念の比較考察や丸山の古層論のように)ケンブリッジ側と同様に歴史的・系譜学的考察を重視しているという点である。博士は、これらが次なる対話の端緒となることを示唆しているように思え、私としてもこれは重要な主題だと考えるので、ケンブリッジ側とまた議論する機会を持つことができた際には、将来世代や公共性との関連で、存在論・生成論・歴史等を主題として本格的な議論を行うことができれば、学問的にも実り多く有意義だろうと感じたことを付言しておきたい。
私達のこれまでの試みの価値については主観的には改めてイギリス側の評価を聞くまでもない事ながら、ケンブリッジ側から客観的に上のような高評価を受けた事の意味は、国際的には決して小さくはない。ゴイス博士が力を込めて言われるには、「日本側の報告には、世界で最高水準に位置しないものは、どれ一つとしてなかった」(強調点は本人)というのである。報告の中に最高水準のものが含まれていたというのではなく、全てが最高水準にあり、だからこそ会議に飽きなかったというのであり、(外交辞令では全くない)この本当の感想を是非日本側に伝えて欲しい、という雰囲気であった。これは、最高の賛辞に他ならず、(予想以上の日本側の水準に対する)ケンブリッジ側の率直な驚きと対話の継続への期待を、ここに読みとることができる。
第1回フォーラムで一部ケンブリッジ側参加者の──見知らぬ日本の新しいグループに対する──懐疑心と不信感に悩まされた筆者にとって、遂にこのような評価が確定したことは、感無量であった。これは、日本側参加者全員にとっての光栄であることは勿論ながら、何よりもこれまでの公共哲学共同研究会全体にとっての名誉であろう。国内の研究会の蓄積があったからこそ、その成果に立脚した私達の議論は、世界の学問の最高峰の一つをも驚かせる様な水準に、期せずして達していた、と考えられるからである。「勝って兜の緒を締める」ということわざ通りに今後一層の努力を重ねることを期しつつ、あたかも戦勝報告にでも似た愉快な気分で、この拙文を皆様への成功報告とさせて頂きたい。
*当日提出されたペーパーの分を除き、筆者のメモと記憶に頼って書いたものなので、若干不確かと思われる部分には、*を付しておいた。なお、会議中の発言の引用は、いずれも要旨である。
(『公共哲学共同研究会ニュース』将来世代国際財団発行、将来世代総合研究所編集、1999年12月5日、第7号、1-7頁、20001年2月改訂)