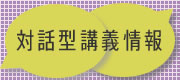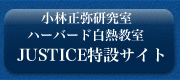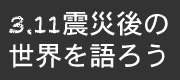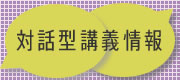

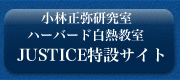

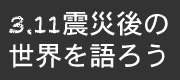
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 稲垣久和『国家・宗教・個人――近現代日本の精神』 | Home | 稲垣久和「温暖化問題と公共信託論」 »
Posted: admin on 5:38 pm | 主張・意見・コメント(opinions)
稲垣久和「南原繁へのレスポンス」〔読書人の雑誌『本』1月号(講談社)より引用〕
人間は理性の動物か、情念の動物か。近代科学以降、理性は特権的地位を与えられた。もちろん情念も芸術や文学で重視されてはいた。では、社会生活や政治の世界ではどうか。答は、理性も情念もその両方があったということなのだが、建前的には、近代政治の仕組みは良くも悪くも「理性」によって社会を作り上げる。
啓蒙主義からはじまって、自由主義・資本主義はそうだった。またそれと対抗的な社会主義・共産主義もそうだった。「科学的合理性」は自由主義、共産主義の両者に共通な「普遍的ものさし」であった。冷戦期にはこの両方が東西イデオロギーとして国際政治を強く縛って対立を深めていたわけである。
とはいえ実際には、東西の両陣営とも、これらイデオロギーを支えているナショナリズム的愛国心は「情念」に深く関わるものであった。人々が理性だけで動いていないことは明白である。
ところで、東西イデオロギー対立が崩壊したあとの世界は、どうなったのであろうか。そこには、啓蒙主義近代が想定していた「理性と情念」の二項対立では測れない現象が多く出てきている。つまり「宗教」や「民族」の問題である。特に「宗教」は、近代啓蒙主義以降は封印されてしまったのであったのだが、これが新たな装いで浮上してきたのである。
西側でも東側でも、宗教はなくなったわけではない。“政教分離”によって個々人の内面に「私事化」されていた。それが、イスラーム世界の原理主義の登場以来、二十一世紀に宗教は再び外面に登場してきた。ポストコロニアルな民族の問題も単なる「情念」ではなく、宗教的ないしはスピリチュアルなアイデンティティーと絡んでいる。
日本でも、小泉政権下の「靖国神社」参拝、安倍政権下の改正教育基本法の「愛国心」と「公共の精神」も、実はこのグローバルな宗教的、スピリチュアルなアイデンティティーと関わっている。特に靖国問題はきわめて日本に特徴的な宗教・政治的現象だ。単なるナショナリズムということであれば、グローバルに共通の問題なのだが、靖国には明治国家成立時の独特のスピリチュアリティーが横たわっているからだ。
宗教は、結局、いつの時代も、なくならないのだと思う。コント的な実証主義や進歩史観では、宗教は弱まって科学の時代に移行するはずだった。しかし、もはや、啓蒙のプロジェクトが挫折しているのは誰の目にも明らかだ。そうだとすれば、どのような形で宗教を人々の幸福に生かしていくべきかを、学問の課題として方法論的にも明確化する必要がある。
ただ、いわゆる宗教学や宗教社会学といった価値中立な手法では、この問題は十分に扱えない。哲学、政治学、法学、社会学などを視野に入れつつ学問横断的な手法が必要になる。ここで、最近の日本の学会でトランス・ディシプリナリーな関心で展開されている公共哲学は強力なツールとなる。
筆者の立場から、公共哲学の内容を簡単にをまとめておこう。
宗教は両刃の剣だ。宗教は共同体を結び付け一体感を与える機能を秘めているだけに、一人ひとりの人間の「良心」を殺す方向性にも働きうるということである。他者を同化して共同体に縛っていく道具になってしまう。近代がいかに批判されるべき面を持つとは言え、人間の内面の良心を尊重し「人権」として法的に保障したことは大きな成果である。
したがって、共同体の一体感を与える面にウエートを置く宗教と、一人ひとりの内面の自由と良心とにウエートを置く宗教では、同じ「宗教」でも性格がまったく異なる。単に宗教心の復興が重要であるといっているのではない。人間を内側から変革して、他者への「寛容」のモラルを示す宗教性こそが、市民社会形成に資する、と主張したいのである。
そう考えると、改正教育基本法の「公共の精神」の導入(前文、第二条)は議論の出発点になる。公共哲学では「公共」に従来のような国家や行政の意味ではなく、「市民」の間に開かれたフォーラムとしての意味を与えているからだ。
今日、ほとんど忘れられているが、戦後の旧教育基本法制定に関わった南原繁、彼の政治哲学は、民族や宗教の問題を深く考えていた。再検討されてしかるべきである。ただ、その際に彼の「宗教」の捉え方が一つの焦点になる。
南原の主著『国家と宗教』(一九四二年)の、戦後の「改版の序」(一九五八年)に次のようにある。「真の神が発見されないかぎり、人間や民族ないし国家の神聖化は跡を絶たないであろう」。また、東京帝国大学総長として敗戦後初の「紀元節」で講演した「新日本文化の創造」(一九四六年)では、今後の日本には宗教改革と同時にルネッサンスが必要であると述べ、「民族宗教的な日本神学からの解放」のためには単なる人文主義の理想ではだめだとする。
このとき、すでに戦後の「リベラリズム」の行く末を見通した慧眼を示していたのではないか。それだけではない。「宗教に代うるには同じく宗教をもってすべく、ここに新たに普遍人類的なる世界宗教との対決を、いまこそ国民としてまじめに遂行すべき秋(とき)である」とも言い切る。
「無宗教」の日本人よ、目を世界に向けよ、と。続けて「これは一個の主観的信仰や憶測から立言するものではなく、精神史研究の学問的立場から客観的に主張し得ることである」と。宗教、政治、社会を総合的に扱える学問的方法論の開発を促していたのである。今回、上梓した『国家・個人・宗教——近現代日本の精神』は、この『国家と宗教』への筆者なりのレスポンスである。
詳述してはいないが、筆者の本書にはもう一つの主張がある。それは「国家主権」の再考である。
かつてヨーロッパ中世での「教会」という共同体組織が、宗教改革後の動乱を経て、近代には「国家」という組織に置き換わった。国家を国家たらしめているのは主権概念である。国家主権論はボダンの提唱から、ホッブズに受け継がれルソーによって国民主権論となった。しかし、ルソーの近代国民国家の社会契約論は、一つの難点をはらんでいた。個人個人が契約を結ぶという「理性」に訴える面だけではなく、市民宗教(公民宗教)と呼ばれる名の強固な愛国心、つまり「情念」を通り越した一種の「宗教」を要求していたのである。
ルソーのアポリアを逃れるには、国家よりも市民社会を強くする必要がある。「国民主権」の抽象性を脱構築して、各種市民グループに分散した「市民主権」さらには「領域主権」を構想する必要があるのだ。近代の国民国家の限界が指摘されている今日、地方分権の流れと同時に、市民が生命、生活、生存のニーズのために環境、福祉、平和、共生を目指して、国境を越えた自発的な大小さまざまなNGO/NPOなどを結成して、友愛に基づいて連帯していくことの重要性がここにある。