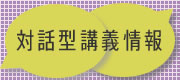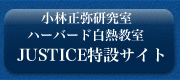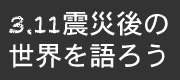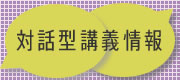

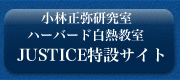

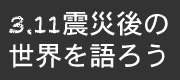
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 戦争宣言予告編:悪夢のシナリオ 小林正弥(千葉大学) | Home | 「外交哲学の貧困と御用学者の責任1」 山脇直司(東京大学) »
Posted: admin on 2:17 pm | 主張・意見・コメント(opinions), 平和問題
※ 12月3日(現地時間)のイスラエルの攻撃により、以下の論稿が恐れていた通りの事態が既に起こり始めてしまいましたが、これについては、続けて論じたいと思います。
1.対テロ戦争の世界的拡大という恐怖――アフガニスタン戦争から中東戦争へ
戦況は大きく変化し、マザーリ・シャリーフ(11月11日)・カブール陥落(13日)・クンドゥス投降(25日) などにより、北部同盟が北部を占拠し、ベール(ブルカ)を脱いで喜ぶ女性達の映像が流れています。ボンでは、現在、政権構成の協議が4派で行なわれてお り、皇太子妃の出産で湧く日本では、あたかも戦争は――南部で抵抗するタリバーンの残党を除けば――終わったかのようです。アメリカでは、「最も偉大な国 の力」を自賛する声が、あちこちで聞かれます。
しかし、私の心は晴れま せん。アフガン国内は、北部といえども無政府状態で、マザーリ・シャリーフ近郊でのタリバーン投降兵の反乱と全員射殺という(アムネスティー・インターナ ショナルなどが調査を要求した)残酷な事件や、メディア関係者の死などが報じられています。そして、何よりも、南部では、まだカンダハル周辺で抵抗を続け るタリバーン軍に対し、アメリカの爆撃が最大規模で激しく続いています。
報道量が減っているだけで、一般市民の死も勿論続いています。クエッタの病院には、連日民間人の犠牲者が運び込まれているようです(11月27日、朝日)。また、東部のジャララバード近辺では、ビンラディン氏らが潜伏していると見て、連日集中的に爆撃を続けており、この文章の執筆中にも、2つの村で住民50人が死亡したと伝えられました(12月1日)。
アメリカは、遂に本格的な地上作戦を開始してしまいました。「迅速な自由作戦」と命名したそうです。カンダハル近郊の空港を制圧して前線基地を作り、特殊部隊約400人だけではなく、海兵隊約1000人まで投入して、計1500人で、カンダハルを死守しようとするタリバーンとの地上戦に突入しようという構えを見せています。
それどころか、ブッシュ大統領は、26日に、宿敵・イラクと、テロ組織の存在する諸国へと対テロ戦争の拡大を示唆しました。湾岸戦争が繰り返される危機、いわば第2次湾岸戦争が起こる危険が現実化してきました。
さらに、イスラエルで、エルサレム繁華街(1日)・北部のハイファの路線バス(2日)で連続自爆テロが起こり、計27人死亡、200人 以上が負傷という恐るべき衝撃的なニュースが飛び込んできました。昨年来の衝突の中で最大級の事件で、アメリカが特使を派遣して進めていた停戦仲介はこの ため崩壊寸前となり、パレスチナ自治区では全域に非常事態宣言が出されました。イスラエルは、既に同等以上の報復を宣言しています。
ブッシュ大統領は「正当化できない殺人行為」と非難し、訪米中のシャロン首相と予定を繰り上げて会談し、シャロン首相はすぐ帰国しました。今回は、アメリカは自制を公式にはイスラエルに求めず、ただ7日間の猶予期間を自治政府に与えるように求めました。この間に自治政府が、犯人の逮捕や支援組織の壊滅をしなければ、あたかも報復を容認するかの如き態度です。
ブッ シュ大統領が「正義をもたらす」という文句、アフガニスタンについては聞きなれた句を使ったのが、非常に気になります。前観光省暗殺時にイスラエル首相が 主張したような、対テロ戦争の論理を、ブッシュ大統領が用いているように見えるからです。その時には、アメリカは――自分自身はアフガニスタンに対して用 いた――対テロ戦争の論理に反対して、イスラエルに自制を求めました。そして「パレスチナ国家」案への支持を表明して、和平の仲介を試みていました。これ は、戦争開始後の、最も賛成出来るアメリカの外交的変化でした。然るに、自治政府がテロに責任があるとしてしまえば、自治政府は和平の当事者からテロ擁護 政府という事になってしまい、議長や自治政府は、オマル師やタリバーンと同列の存在と見做す事になりかねません。
こ うなれば、むしろ自治政府自体が攻撃の対象となってしまいます。現に、イスラエル内部では、最早アラファト議長には期待できないとして、議長や自治政府を も攻撃の対象とするべきである、という議論がなされています。既にハマスら強硬派は攻撃の対象としており、今回の自爆テロは、ハマス幹部ら3人の暗殺(11月23日)の報復です。この攻撃をを自治政府にまで拡大してしまえば、後に残るのは、アフガニスタン同様の戦争しかないでしょう。北部アフガニスタンで戦火が収まった途端に、パレスチナで戦争が始るわけです。これこそ、私の恐れていた事態に他なりません。
時評で、「米、地上作戦開始」と「イスラエル軍のベツレヘム侵攻」という記事が並んだ日(10月20日)の衝撃を述べましたが、ここ数日に、この双方が共に拡大された形で再現されているわけです。10月 の段階では、地上作戦といっても特殊部隊に限定されていましたが、今回は海兵隊です。ベツレヘムなどパレスチナ自治区に侵攻した戦車は、その後アメリカの 圧力で撤退しましたが、今度もこのようになる保証はありません。最悪の場合は、和平が破綻し、戦争がパレスチナで始まる危険も無視できません。
つまり、現在は、既に起こってしまった「アフガニスタン戦争」が、――ブッシュ大統領の意思により――イラクとの「第2次湾岸戦争」に、あるいは「対テロ世界戦争」に、そして――アメリカの意向さえ超えて――「パレスチナ戦争」へと拡大する危険を迎えている訳です。第2次 湾岸戦争とパレスチナ戦争が同時に始まってしまえば、これは「中東戦争」になりかねません。「第5次中東戦争」ということになるでしょうか。こうなってし まえば、「文明の衝突」ないし「文明間戦争」へと発展してしまう危険が現実化してきます。これは、本当に「世界戦争」へと繋がりかねない危険であり、戦慄 の恐怖としか言いようがないでしょう。この状態で、どうしてお祝い気分になれましょうか。
これまで、この戦争について、まだ国際的な呼称は定まっていません。「アフガニスタン戦争」という呼び方もありますが、ソ連が侵略して始まった戦争(ソ連の軍事的侵攻は1979―89年)と混乱し易いという問題があったからです。もう一つの呼称は、「対テロ戦争」です。この呼称は、アメリカの掲げている戦争目的をそのまま用いているという点で、アメリカから見た表現であるという問題点がありました。
し かし、どうやらアメリカは、アフガニスタンだけではなく、本当に、アメリカがテロ支援国家と認定した国に対して次々と攻撃を拡大していくつもりのようで す。そうだとすれば、やはり「アフガニスタン戦争」という地理的な表現よりも「対テロ戦争」という表現の方が適切だろうと思われます。先のアメリカ寄りと いう「偏向(バイアス)」を避けるべく括弧を付して「対『テロ』戦争」と呼ぶ事にしましょう。
ブッ シュ大統領の言明をそのまま信じれば、アフガニスタンだけではなく、どこまでも戦線が広がる可能性があるのですから、この戦争は「対『テロ』世界戦争」と 見做す事が出来るでしょう。この全体から見れば、アフガニスタンの戦争は、この世界戦争の「始まり」に過ぎないので、「第1戦線」という事になります。そして、イラクやパレスチナが「第2戦線」「第3戦線」という事になるわけです。勿論、第2戦線以下は、まだ現実のものではなく、潜在的な危険性に注意を喚起するための表現です。以下では、このような展望の下に、これらの危険を順に見ていく事にしましょう。第2戦線以下が現実のものとならない事を祈りつつ。
2.アフガン戦線:戦局転換における既視感(デジャ・ビュ)――タリバーン「敗走」と湾岸戦争の「勝利」
振り返って見れば、現在 のように、アメリカ軍が圧勝し、反米側がたわいもなく敗れ去ったように見えたことが、かつてもありました。そう、湾岸戦争におけるイラクの「敗北」です。 その時、父ブッシュ大統領は、勝ち誇って勝利宣言をし、「新世界秩序」の到来を力説したのでした。あの時、皆様は、それを信じ、そこに希望を託したでしょ うか。
私は、信じませんでし た。当初は、「独裁者」のフセイン政権も、アメリカの力により終止符が打たれるように見えましたが、結局は生き残り、先に政権を去ったのは、ブッシュ大統 領の方でした。そして、(湾岸戦争後にアメリカ軍が「聖地」・サウジアラビアに駐留を継続している事に憤った)イスラム過激派が、9月11日に同時多発テ ロを起こし、全世界は、湾岸戦争の深刻な帰結に漸く気付いたのでした。湾岸戦争でアメリカは、本当に勝ったのでしょうか?
ブッシュ親子は、そして アメリカは「勝利」を信じたいのでしょう。ですから、その帰結として生じた今回の事件でも、タリバーン政権を打倒し、アルカイーダを始めとして、テロ組織 を根絶する「戦争」に勝利して、その「勝利」を不動のものとしたいのでしょう。しかし、歴史は、そのように展開するでしょうか。私には、むしろ、現在のア メリカの歓喜は、10年前の勝利宣言と重なって見えるのです。湾岸戦争の時と同じように、いずれアメリカは、その帰結に直面せざるを得なくなると思えるの です。
以前、次のような点について、これらをアメリカが犯すと、アメリカにとっても危険だと警告しました(公共民9 時評など)。
①本格的地上戦突入
②イラクなどアフガニスタン以外の国への攻撃
③パレスチナ問題の発火
④無辜の民の犠牲者数
心情倫理からすれば、そもそもアメリカの攻撃は首肯し難いものです。結果倫理からすると、極めて限定的な攻撃の場合は別にして、大規模報復攻撃は、アメリカにとってすら危険な帰結を招くが故に、愚かなのです(拙論第2部参照)。そして、この4点を犯せば犯すほど、それは大規模報復の発想に近づき、従って結果倫理からみても誤りです。
空爆開始後4週間に及ぶ、タリバーンの予想外の抵抗によって、アメリカのメディアにおいてすら、一時、ベトナム戦争のような泥沼化が懸念されました(時評11月8日[i]参照)。戦局が好転したので、一転して楽観論が圧倒的になっていますが、アメリカの友として、敢えてこの時点で上の警告を再度繰り返したいと思うのです。
3.地上戦の罠――ベトナム戦争化の危険は未だ去らず
空 爆に限定している限り、――倫理的には非道であっても――アメリカ軍に大量の死者が出て、敗北することはありえません。逆に言えば、当初北部でもタリバー ンが抵抗をした点については、戦術的には疑問の余地があります。一方的に空爆を受けていれば、戦力の消耗が激しいのは、理の当然だからです。4週間の間持ちこたえたのを見て「一寸の虫にも五分の魂」という言葉を思い出しましたが、――戦前の日本と同様に――精神力にも限界があるというものでしょう。タリバーン側の撤退は、人的・物理的損害のために、軍事的に北部の拠点を支えきれなくなったことを意味します。
従って、戦術的後退とか 民間人の犠牲を避けるための撤退という、タリバーン側の説明を鵜呑みにする事は出来ないでしょう。しかし、問題は、この先にあります。軍事的撤退の結果、 戦勝気分に酔ってアメリカ側が地上に降りれば、アメリカ軍にも生命の危険が生じるからです。もしタリバーンが現在の難局を軍事的に凌ぐ事が出来れば、地上 戦の可能性が生まれ、逆にタリバーン側にも反撃の機会が生まれてきます。つまり、タリバーン側が主張しているように、結果として「戦術的後退」をしたこと になるのです。
純戦術的に考えれば、タ リバーン側は、初めからゲリラ戦を中心にした方がよかったかもしれません。現に、このような判断が指導部にあるから、マザーリ・シャリーフ陥落直前に、カ ブール始め北部からの撤退を決め、一時はカンダハルの放棄までオマル師が宣言しました。パキスタンからの義勇兵に対して、カブール陥落直前に、「今は地上 に米軍はいないから、いったん帰国しろ。地上に来たらまだ応援を頼む」という指令がオマル師から届いた、という報道がなされています[ii]。
16日 には、カンダハルの後継支配体制(イスラム党ハリス派のバシェル司令官とイスラム協会のナキブラ司令官)まで決めて、オマル師らはカンダハルを放棄し山間 部に立て篭もってゲリラ戦を行なうつもりだったようです。ところが、「カンダハルを死守せよ」という預言者の夢をオマル師が見たので、翌日一転して「カン ダハルを放棄するつもりはない。死ぬまで戦う」と方針転換した、という報道がありました(未確認)[iii]。その真偽はともかくとして、もしカンダハルが陥落しても、タリバーン側が山岳地帯に立てこもって、執拗なゲリラ戦を続け、戦闘が泥沼化することは十分に考えられます。
アメリカは、既に戦争に勝利し、「これは、やはりベトナム戦争型ではなく、湾岸戦争型だった」と凱歌を上げているようです。湾岸戦争も、本当の勝利かどうか疑わしいと書きましたが、「ベトナム戦争化しなかった」と速断できるかどうかも、実は疑問の余地があると思います。
そもそも、ベトナム戦争の場合は、まずホー・チ・ミンの下でベトナム民主共和国(北ベトナム)がフランスから独立を宣言し(1945年)、これに対して、米仏が支援して南ベトナム(当初はゴ・ジン・ジエム政権)が樹立されました(1954年)。この南ベトナム政権と、それに対する南べトナム民族解放戦線(ベトコン、1960年結成)との間の戦闘という形で始まり、政権を支援するアメリカ(南ベトナム援助軍司令部設置、1962年)が徐々に介入を拡大し、ベトコンを支援する北ベトナムの爆撃(北爆、1965年開始)などを行ったのです。これは、反米デモやベトナム反戦運動を激化させました。ベトコンの執拗な悩まされて、戦局は悪化し、最後にはアメリカ撤退と南ベトナム政権の降伏で戦争が終結した訳です(1975年)。
この過程を思い出してみれば明らかなように、アメリカが本格的に介入してから10年以上がかかっており、この間には様々な戦局がありました。それ故、「第1次 の目標は達成できた」(ブッシュ大統領)と言っても、予断は禁物です。例えば、現在行なわれている暫定政権設立を南ベトナム政権樹立に喩えれば、カンダハ ル周辺の爆撃は北爆に似てきます。南北は転倒しますが、南北が分断されてアメリカが片方を軍事的に支援する構図は同じです。ですから、タリバーンが南部の 支配を維持できれば、この戦争の構図は、むしろベトナム戦争に似てきてしまうのです。また、仮にカンダハルが陥落しても、山岳地帯でゲリラ戦化した場合に も、やはりベトナム戦のような泥沼化の危険は存在するでしょう。
しかも、北部も決して安 定してはいません。東部のナンガルハル州では、地元の反タリバーン勢力がタリバーン軍を追放したものの、北部同盟にも対立しているなどという状態です。つ まり、北部同盟は、北部の拠点は抑えたものの、その全域を統制する力は持たず、全国が様々な部族の群雄割拠状態になってしまっているようです。さらに、寄 せ集めの北部同盟内部の主導権争いも激しく、解体する危険すら指摘されています。
こ のような状態を考えてみれば、ベトナム戦争のように泥沼に陥る危険は去ったと歓喜する事は出来ないでしょう。タリバーンは過酷な処罰によって秩序を維持し ていたのですが、タリバーンの「敗走」=撤退の後に来たものは、いわば混乱した無政府状態です。この無秩序からは、底なし沼のような危険が待ち受けている かもしれません。
それ故、アメリカは、この「戦果」で満足して、ここで鉾を収めるべきであり、地上兵力の投入をすべきではなかったと思います。そうすれば、少なくとも、現時点では、湾岸戦争の時のように凱旋する事が出来たでしょう。しかし、残念な事に、アメリカは、既に10月後半(19日頃)から開始していた地上作戦を拡大してしまいました。まず、北部同盟が、アメリカの制止を無視してカブールに入ってしまった事を苦々しく思い、「地上に部隊を置かないと事態を制御できない」と考えたのでしょう。
実際に、北部同盟は、治安維持のための欧州軍の受け入れに難色を示しています。イギリス軍に対しても、100人の海兵隊は認めましたが、6000人の派遣には合意しませんでした(21日)。また、北部同盟のドスタム将軍は、フランス軍の受け入れを拒否しました(20日)。 他方で、カンダハルなど南部での抵抗はまだ続き、北部同盟だけでは勝てるとは限りません。北部同盟がタジク人・ウズベク人・ハザラ人などの部族から成って おり、その侵攻にはパシュトゥン人の反発が予想されるので、アメリカは、北部同盟のみによって地上戦を行なわせる事を断念したのでしょう。
こうして、特殊部隊約400人に加えて海兵隊約1000人、合わせて1500人 ほどの地上軍を投入し、カンダハル周辺に基地を作ってしまいました。当初は反タリバーン勢力の支援と言っていましたが、反タリバーンのパシュトゥン勢力だ けではタリバーンに勝てない状態なので、自らもカンダハル攻撃に加わる姿勢を見せ始めました。果たして、この地上戦への突入が、軍事的に賢明なのかどうか ――もし、この戦争でアメリカに苦杯が訪れる事があるとしたら、その軍事的失敗の一因はここに求められることになるでしょう。
4.イラク戦線:第2次湾岸戦争の危険――世界帝国統治一家の私的戦争
し かし、仮にアフガニスタンでアメリカが「完勝」したとしても、まだこの「戦争」は終わらないかもしれません。いよいよ現実化してきたのが、イラクなど他の 諸国の攻撃という懸念です。アフガン戦線の「勝利」に見通しがついたと考えるや否や、アメリカは次なる「戦線」を開く事を考え始めました。
「勝利」の確立を焦るブッシュ大統領は、何と驚くべき事に、21日には、「アフガニスタンは始まりに過ぎない」と述べ、「テロ組織を支援する国家は他にもある、米国は全ての脅威をつぶすまでは安全とは言えない」と演説しました。そして、26日には、次の攻撃対象としてイラクや、アルカイーダの関連組織があるイエメン・スーダン・ソマリア、さらには(イスラム過激派アブサヤフのある)フィリピンを挙げました。対テロ戦争の標的を早くも拡大しようとしているのです。
そ して、他の諸国政府とは異なって、敵対的なイラクには、大量破壊兵器の査察要求を行ないました(イラクは拒否)。「拒否したら攻撃する」という、イラク爆 撃の布石です。現在のところ、同時多発テロに対してイラクが深く関与したという証拠は存在しません。そこで、「大量破壊兵器で世界を脅かす国」という概念 を持ち出し、「大量破壊兵器の存在自体が、世界を脅かすから、攻撃を行う事ができる」という驚くべき論理を持ち出しました。北朝鮮にも、同様の論理で査察 要求を行なっています。
タリバーン攻撃の際に は、「テロ組織を保護している政府も、敵と見做して攻撃・打倒する」という論理を用いました。今度はさらにエスカレートし、(現実にテロ組織を支援してい なくとも)大量破壊兵器の所有自体が「敵」とされ、攻撃の対象となる、というのです。言い換えれば、イラクはテロを支援していなくとも、大量破壊兵器を保 持しているから攻撃の対象となり、「イラクの脅威を説明するのに、9月11日(の同時多発テロ)は必要ない」(ライス大統領補佐官)というのです。
大 量破壊兵器の保持が望ましくない事は自明であり、その放棄が全世界で同時に行なえるのならば、それは素晴らしい事です。しかし、世界で最大の大量破壊兵器 を所有している国家、そしてそれを現実に行使している国家は、アメリカでしょう。この論理からすると、何故、アメリカは、世界各国の攻撃の対象にならない で済むのでしょうか?[iv] ここには、驚くべき二重基準(ダブル・スタンダード)が存在すると言わざるを得ません。
イギリスを始め、対テロ 戦争を支持している友好国(欧州・中東諸国)からも、アメリカのイラク攻撃には流石に批判の声が続々と上がっており、これでアメリカが思い止まる事を祈り ましょう。私には、戦局の一時的な好転に浮かれて自己抑制を失うと、恐るべき反動が訪れる危険がある、と思えるのです。
そもそも、戦局転換以前 には、ラマダン(断食月)に攻撃を続行すると、イスラム教徒の反感を買う事が懸念されていました。タリバーンの撤退で、現在は反米デモは鎮静化しているよ うですが、だからと言って、今攻撃をエスカレートする必然性があるでしょうか。南部に爆撃を続ける事ですら、この点で問題であるはずなのに、ましてイラク の攻撃を企てるとは、正気の沙汰とは思えません。
勢いに乗って、父・ブッシュ政権以来の宿敵を打倒しようとしているとしか、見えないでしょう。これは、正しく、政治の巨大な私事化に他ならない、と思えるのです。権力の「私事化(privatisation)」 こそ、およそあらゆる腐敗した権力の特徴ですが、通常の国家の場合は、国内政治の腐敗や汚職という形で現れるのに対して、覇権国・アメリカの場合は、それ が「戦争」という形で現れる事が可能です。既に、国際法や国連を無視したアフガニスタン攻撃に、このような「私事化」は現れていました(拙論第2部参照)が、イラク攻撃に及んで、この私的性格は頂点に達すると言えましょう。これは、正しくブッシュ家の「私的戦争」であり、「私戦」に他ならないでしょう。
緊急論説第2部で書いた ように、アメリカ政権内部に、パウエル国務長官ら慎重派と、ウォルフォビッツ国防副長官らタカ派との対立が存在します。現在の軍事的「成功」は、前者が後 者を基本的には制して、大規模報復作戦を抑制したからでしょう。しかし、ブッシュ大統領は、前者に完全に軍配を上げたわけではなく、とりあえずは限定的軍 事作戦に止めるけれども、その後に拡大を検討するという意向を示していました。
今、その拡大の時期が訪 れたとして、パール元国防次官補(国防長官諮問委員会議長)ら政権内部のタカ派は、イラクらへの攻撃拡大を主張しています。当初から目論んでいた大規模報 復作戦の遂行です。ある意味では、慎重派とタカ派との政権内部での角逐は、父・ブッシュ政権以来の物語です。湾岸戦争終結時に、おそらく父・ブッシュ大統 領はフセイン政権を一気に軍事的に打倒したかったのですが、やはり慎重な軍事作戦を指揮した当時のパウエル将軍らは、それを制して戦争を終結させました。 ブッシュ父子には、そのままフセイン政権を倒してしまえば、その後に生き延びる事もなかったという思いがあり、今回こそ宿敵を打倒したいのでしょう。
論説で書いたように、軍事的合理性に立脚するパウエル路線[v]に 拠る限り、アメリカは軍事的には簡単には敗北しないでしょう。しかし、これを乗り越えて戦線を拡大する時に、軍事的な破綻の危険が忍び寄るのです。ベトナ ム戦争の拡大を推し進めたケネディ政権の中心者達は、当時の輝ける知的エリート達、アメリカ・エスタブリッシュメントの「ベスト・アンド・ブライテスト」 (D・ハルバースタム)[vi]でした。たたき上げの軍人で黒人のパウエル長官は、このようなエリートではありません。しかし、タカ派の中心人物・ウォルフォビッツ副長官や、ライス補佐官は、輝かしい経歴を誇っており、正に現在の「ベスト・アンド・ブライテスト」です[vii]。それ故、そのような人達の主導する路線に、私はアメリカにとっての危険を見るのです。
ここまでのアメリカの 外交的・軍事的「成功」は、限定作戦の「成果」です。これに対して、大規模報復作戦こそは、アメリカの驕りの極みであり、アメリカ帝国主義の現われに他な りません。国連決議や国際法も関係なく、テロ組織や大量破壊兵器の保持を理由として爆撃を行う事が出来るのならば、殆ど無限に拡大適用が可能になります。 これらの存在は証明が難しいわけですから、アメリカが、テロ組織や大量破壊兵器が存在すると主張するだけで、攻撃する事が可能になってしまいます。
これでは、アメリカは自分に盾突く国は、悉く爆撃しても良い事になってしまいます。これを「世界帝国主義」と呼ばずして何と呼べましょうか? これは、既にチャルマーズ・ジョンソンら具眼の士が指摘している事[viii]で すが、それどころか、アメリカ国内のタカ派は、驚くべき事に、自ら「新帝国主義」「新植民地主義」を主張しているのです。つまり、「戦後に、この地域の植 民地支配を止めて間接統治(傀儡政権による支配)にしたが、それが良い結果を生まなかった。だから、直接統治に戻すべきだ」という驚愕すべき議論です[ix]。
社 会科学では、この間接統治の実態を見抜き、批判的に「新帝国主義」等と呼ぶわけですが、さらに直接統治、即ち「旧(!)植民地支配」そのものの回復を積極 的に主張する論者がいるとまでは想像していませんでした。これは、極端な主張であるにしても、アメリカの内部に巣食う驕りを端的に示しています。
イ ラク攻撃とは、世界帝国の統治者ないしは統治する一家(ブッシュ家)が行なおうとする「私戦」であり、「世界帝国統治一家の私戦」に他なりません。これを 皮切りに野放図な軍事力の行使へと至るかどうか。これが、私が極力批判してきた誤りへと至る決定的な分岐点なのです。最早、イラク攻撃に踏み切れば、アメ リカが「王道」から遥かに逸れ、「覇道」を歩んでいる事が、万国の民に明らかになるでしょう。「戦勝」に奢って、次々と爆撃を行う時、これまでは同時多発 テロの犠牲に同情していた世界の人心が離反し、そこに「帝国」の危機が訪れることは、必定と思うのです。
5.パレスチナ戦線:中東戦争の危機――パレスチナのアフガン化・アメリカのイスラエル化・世界のパレスチナ化
あ る意味では、事態はイラク攻撃どころではないかもしれません。冒頭に述べたように、正にパレスチナ問題が再び発火しかかっているからです。アメリカの態度 で最も期待を抱かせたのは、この問題を無視する態度を改めてパレスチナ国家の実現への姿勢を見せたように見えた事でした。
私自身は、パレスチナ国家の樹立というだけで、この問題の解決に十分かどうかは、自信がありません。そもそも、イスラエルという国家は存在しなかったわけですし、パレスチナ国家との分割線についても、少なくとも戦後の国連分割決議181号(1947年11月)までは戻って考える必要があるように思えます。しかし、そのような理想論を述べても現在の状況では、あまり現実性がありませんから、パレスチナ国家の樹立という現実的目標が、イスラエルの最大の支援国・アメリカによって表明された事は、とても重要だと思えます。
毎日のように、イスラエ ル・パレスチナ双方の犠牲者が報道されてきました。既に9月11日以来、100人を超えたようです。それにも拘らず、これまで『公共民10』で述べた停戦 崩壊の懸念が辛うじて回避されてきたのは、アメリカがイスラエルに交渉に応じるように圧力を加え、他方、パレスチナ国家への支持を表明することによって、 自治政府らパレスチナ側に一縷の望みをつながせているからでしょう。
勿論、シャロン首相に積 極的に和平を進めようとする気がないのは、周知の事実です。それを押し切って、和平を進展させるには、国際社会、ことにアメリカの強固な意志が必要です。 ここで問題になるのは、アメリカに本当にその決心があるいのかどうか、という点です。現在、アフガニスタンに――そして、もしかするとイラクに――戦争を 仕掛けているから、イスラム諸国の支持を取り付けるために、一時的に期待を持たせる言葉を述べているのではないか。このような疑念をまだ拭う事ができませ ん。
今回の自爆テロは、和平進展の可能性が生まれてきたその時に起こりました。パウエル国務長官が、中東和平への積極的介入を表明し、パレスチナ国家支持を確認する一方でイスラエルにも入植の停止を求め(19日)、ジニ元中央軍司令官が停戦確立のために特別顧問として派遣されている時です(26日到着、これでイスラエルは唯一占領していた自治区ジェニンから撤退)。これは、ハマス幹部暗殺への報復で、ここには典型的な「報復の報復」という典型的な悪循環を見ることが出来ます。
今年6月13日の停戦発効以後の主なものだけを拾ってみても、「エルサレムでの自爆テロと、イスラエル軍の自治区侵攻(8月9日)→パレスチナ側のイスラエル軍陣地奇襲と、イスラエルによるパレスチナ解放人民戦線(PFLP)議長暗殺(8月25日)→PFLPによるイスラエル観光相暗殺(10月17日)と自治区侵攻(死者20人以上)→パレスチナ警察によるイスラム聖戦幹部逮捕(11月14日)→イスラエルのハマス幹部ら3人暗殺(11月23日)→イスラム聖戦によるイスラエル北部ハデラの路線バス自爆テロ(死者3人、11月29日)→イスラエルのジェニン再侵攻と、ハマスによるエルサレム繁華街の自爆テロ(12月1日)・北部ハイファでの路線バス自爆テロ(2日)」という事になります。
PFLP議長暗殺の報復がイスラエル観光相暗殺、イスラム聖戦幹部逮捕の報復がハデラでの自爆テロ、ハマス幹部暗殺の報復が今回の自爆テロであり、それぞ れに対してイスラエルも報復を行っています。これこそ、血で血を洗う報復の悪循環に他なりません。イスラエルが今回また大規模な報復を行なえば、またそれ は将来のパレスチナ側の報復を呼ぶ事でしょう。
こ こには、私が反対してきた報復戦争の縮図があります。構造的に、イスラエルがパレスチナを占領しており、入植活動を続けているからこそ、パレスチナ過激派 は絶望して自爆テロに走っているのです。これに対して、イスラエル側は、自治政府に過激派の取締りと攻撃停止だけを一方的に求めており、――パウエル長官 がこれらの問題も指摘したのに対して――シャロン首相は、攻撃停止だけに限定する事を主張しています。しかし、この構造的要因を解消しない限り、完全な攻 撃停止は不可能なのです。
だ からと言って、前述のように、自治政府が過激派を保護しているとして、穏健派である自治政府自体を攻撃してしまったら、和平の崩壊と戦争の再開あるのみで す。イスラエル観光相暗殺時にシャロン首相はアメリカの対テロ戦争の論理を主張し、そして今回はブッシュ大統領までもが、その論理を匂わせました。1週 間の間に犯人逮捕と支援組織壊滅を要求するというのは、ちょうど同時多発テロ事件後にタリバーン政権に対してビンラディン氏引渡しとアルカイーダ壊滅を要 求したのと全く同じでしょう。いわばビンラディン氏やアルカイーダに相当するものとして、イスラム聖戦やハマスを考え、タリバーンに相当するものとして自 治政府を見做す事になるわけです。
そ れ故、自治政府がこれらの要求を満たせなければ、タリバーンの場合と同じように、自治政府やアラファト議長自体に対して、イスラエルが「報復」攻撃を行な う可能性があるのです。こうして戦争に突入すれば、ここに起こるのは、いわば「パレスチナのアフガン化」であり、アフガニスタン戦争と同型の論理として、 「パレスチナ戦争」が起こる事になってしまいます。
他 方、この報復の泥仕合は、アメリカの用いている報復の論理の行き着く先を端的に示しているのです。アメリカ国内の炭疽菌問題やニューヨークの飛行機墜落 は、どうもイスラム過激派のテロではないらしいとされていますが、必ずしも原因が確定したわけではありません。そして、仮にカンダハルなども陥落して、ビ ンラディン氏も死に、アフガニスタン戦争が終結したとしても、アメリカは今後、果てしないテロの恐怖に脅かされる事になるでしょう。アルカイーダの構成員 は、ラディン氏を護衛する1000人を除くと、既に多くが国外に脱出したという情報もありますし、その他にもイスラム過激派は数多いからです。
ア メリカで(反戦の)言論弾圧や大統領権限の強化、根拠の薄い拘束などの人権侵害が起きています。つまり、アメリカは「テロとの戦い」の名の下に、既に兵営 国家化し始めているわけです。そして、この最先端の例がイスラエルに他なりません。イスラエルのテルアビブ空港は取り締まりの厳しさで有名ですし、そして いつパレスチナ側のテロが起こるかわかりません。同様に、アメリカも国内の取締りが強化され、自由は抑圧され、しかもテロの脅威に脅えて暮らす事にならざ るを得ません。
これは、いわば「アメリカのイスラエル化」と言う事が出来るでしょう。考えてみれば、イスラエルの過激派暗殺は、紛れもない「国家テロ」でしょう。緊急論説第2部で批判したように、アメリカはアフガニスタン攻撃によって、やはり「国家テロ」への道を踏み出してしまいました。「テロ」と「国家テロ」との応酬という点に於いて、アメリカはイスラエルと同じ道を歩んでいると言わざるを得ないのです。
そ して、アメリカが「テロ支援」とか「大量破壊兵器の所持」というだけで、ある国家を攻撃するようになるならば、前述したように、アメリカに反対する国家 は、いつ「国家テロ」を受ける事になるかわかりません。つまり、イスラエルに攻撃されるパレスチナのような状態が、論理的には世界中の諸国家に広がる事に なってしまいます。いわば「世界のパレスチナ化」です。
こ れまでは、パレスチナの悲惨な状態は、特に日本ではごく僅かの注意しか引きませんでした。それが可能だったのは、この報復の応酬が、パレスチナという一地 域に限定されていたからでしょう。しかし、世界がパレスチナ化してしまう危険が生じれば、パレスチナ問題は最早他人事ではなくなる事でしょう。
繰り返しておきましょう。パレスチナに戦乱が起こる時こそ、世界戦争の危機が訪れる時です。かつての4回 に渉る中東戦争には、パレスチナ問題が深く関連しています。現在の中東諸国の姿勢からすると、すぐに全面的な中東戦争へと展開する事はないでしょうが、こ のような危険性だけはどうしても回避されなければなりません。そのために是非必要なのは、報復の応酬という復讐の論理から逃れる事です。
ア メリカがイスラエル化の危機に見舞われているのは、この報復の論理を採用してしまったからです。そして、アメリカはイスラエルに自制を求め、パレスチナ和 平の崩壊を阻止したいにも拘らず、イスラエルがアメリカと同様の「対テロ戦争」の論理を用いてパレスチナを攻撃しようとするのに対して、それを止める事が 難しくなってきました。「パレスチナ戦争」はアメリカの望まない帰結とは言え、自らの論理の結果、自縄自縛に陥りつつあると言えましょう。
か くして、今起こりつつあるのは、パレスチナのアフガン化の危険であり、アメリカのイスラエル化であり、さらにイスラエルのアメリカ化です。もともと、イス ラエルとアメリカが極めて密接な関係にある事は周知の事実でしたが、今まではアメリカがその自由意思によって余裕を持ってイスラエルを支援していたのに対 し、今やアメリカは、イスラエルから逃れられなくなり、いわば一蓮托生の様子を呈しています。一時的にアフガニスタン北部で「戦勝」しても、この論理に基 づく攻撃は、結局は復讐を呼び、イスラエルと同型の論理が、アメリカに対しても同じ帰結をもたらす事になるのです。
6.アフガン大虐殺?――イスラム/アメリカ原理主義の相克を超えて
ここで改めて一連の時論の不変の主題に立ち戻っておきましょう。改めて、問いを立ててみます。果たして、空爆開始以後に、何人の無辜の民が死んだのか。あるいは、戦士も含めて、この戦争では、一体既に何人が死んだのか。
正確な数字は誰も知りま せん。タリバーンが北部で抵抗を続けていた時には、タリバーン側や、アフガン・イスラム放送が犠牲者数を報告していましたが、その数字さえなくなってしま いました。私達が知ることができるのは、テレビなどに映る死体の姿だけです。タリバーン兵士に対して、北部同盟側の処刑の噂が絶えません。前述のカライ ジャンギ捕虜収容所でのタリバーン兵の反乱では数百人が亡くなったと報道されています。約80人を除いて、後は「皆殺し」です[x]。アムネスティー・インターナショナルや国連弁務官が調査を要求するのも、無理はありません。
この事件では、タリバーン側に、アメリカ人が存在していたので、その人の口を通じて、悲惨な攻撃の実態が証言されました。「地下室にガソリンをまかれて火を付けられたり、水を流し込まれたりし、さらに何個かの手りゅう弾も放り込まれた。 地下室はタリバーン兵の死体でいっぱいだった」というのです[xi]。これは、ホロコースト(大虐殺)を連想させないでしょうか? この米国人タリバーン兵は、いわばガス室からの生き残りのような役割を果たしたと言えるでしょう。
この事件では、アメリカが公式に認めた初めてのアメリカ側死者(CIA要員)が出ました。しかし、戦士も含めれば、既にアフガニスタン側では、数千人が死んでいるのではないでしょうか。あるいは、もう一万人を超えているかもしれません。この死者の比!
そして、アフガニスタン側の死者は、もう米国同時多発テロ事件の犠牲者数をおそらく遥かに超えているでしょう。同時多発テロ事件の犠牲者数は、事件直後は5-6000人と言われていたのですが、実は4000人 以下だったと報告されました。兵士を入れて考えれば、アフガニスタンの犠牲者がこれを大きく超えている事は確かでしょう。民間人に絞れば、どうでしょう か。アメリカの誤爆の犠牲者数は知る由もありませんが、食糧や医療の欠乏による犠牲者や難民としての犠牲者数は、おそらく莫大な数になるだろうと思いま す。まして、南部の攻撃を激化させ、イラクまで攻撃してしまえば、同時多発テロの犠牲者数を超えてしまう事は、火を見るよりも明らかです。
タリバーンの撤退は、前 述した戦術的失敗の結果かもしれませんが、それでも、北部の空襲は止みましたし、そのお陰で、人道的援助も再開できるようです。これは、手放しで喜べる事 です。もし、あのままタリバーンの抵抗が北部でも持続していれば、この冬に百万単位の餓死者が出るだろう、と援助機関等から警告が発せられていたからで す。アメリカは、その危険を無視して空爆を続ける姿勢でしたから、タリバーンの撤退だけが、人々の命を救う道でした。もっとも、南部の民に同様の危険が生 まれているのではないか、と私は危惧しています。
タリバーンの撤退や、そ の兵士の犠牲は、哀れには思いますが、それは自業自得という面もないではありません。バーミヤンの大仏の破壊に見られるように、やはりその原理主義は、硬 直的に過ぎて時代遅れであり、非寛容・非現実的という問題点を否定することはできないからです。アメリカの爆撃には反対ですが、思想的にタリバーンを擁護 することはできません。その撤退によって、人々の命が大量に助かるならば、それ自体は止む無しとされなければならないでしょう。
しかし、それを爆撃する アメリカの現政権も、また、一種の原理主義と呼べるような、硬直的・独断的な考え方に立っていると言わざるを得ません。そもそも、現政権は、――論説第1 部で書いたように――世界資本主義的公共哲学に立脚しており、レーガン=ブッシュ政権以来の「ネオ・リベラリズム=市場原理主義」の路線を採用していま す。そして、単に、市場原理主義というだけではなく、それが軍事力の行使というタカ派路線と結合している点に於いて、「新保守主義」路線でもあります。
さ らに言えば、アメリカ帝国主義とも呼べるような覇権主義と結合しているが故に、これは「アメリカ原理主義」とすら呼べるかもしれません。勿論、「イスラム 原理主義」とは異なって、自由・民主主義・市場などの「アメリカ的原理」を標榜している点に於いては、現代的な装いをしていますが、これも、精神の硬直 性・独断性という点では原理主義的なのです。このような観点から見れば、今回の戦いは「(イスラム)原理主義と(アメリカ)原理主義との戦い」と言う事が できるでしょう。
およそあらゆる原理主義 は、精神的に硬直しているが故に、視野狭窄に陥っており、それ故に、異質な考え方に対して冷酷になりがちです。実際、アフガン南部への地上戦力の展開や、 イラク攻撃の可能性を示唆した時、ラムズフェルド国防長官やブッシュ大統領の顔付きは、ただならぬものに思えました。ある人の表現では、「(最近のラムズ フェルド長官は)死神のような顔である」ということになりますが、正しく身の毛のよだつような鬼気迫る表情です。これと比較すると、実際に死が旦夕に迫っ ているかもしれないラディン氏や、オマル師の表情の方が、死を覚悟しているせいか、遥かに落ち着いていて、澄んでいるようにすら思えるのです。
純粋に精神的次元で考え た場合、アメリカ指導部とタリバーン指導部と比較して、どちらが高い精神性を持っているかというと、アメリカの側にそう簡単に軍配が上がるとは思えませ ん。また、これほどアメリカに好意的なメディアなのに、「タリバーン側が捕虜を残虐に扱ったとか、虐殺した」という報道は、殆どありません。柳田大元氏を 始め、タリバーンに拘束されていた西洋側のメディア関係者は、殆ど解放されたり脱出しています。それどころか、「拘束されて暫くすると、タリバーン兵はい い人達である事がわかった」などというコメントが、しばしば聞かれ、誰もタリバーン側の非道さを訴えてはいません。アメリカの爆撃により敗走する最中なの に、殺そうとしなかったのには、感心しました。
これに対して、メディア 関係者が死んだのは、北部解放後の混乱下であり、殺人者は特定されていません。無政府状態・無秩序状態に陥り、ゲリラなどの武装集団による略奪や強姦が頻 発していると報道されています。また、マザーリ・シャリーフを始め、タリバーン兵の大量の死も、ささやかながら報道されています。BBCでは、カブール陥 落の際の映像を流しており、そこにはタリバーン兵士の遺体が映っていました。また、学校に隠れていた無抵抗のタリバーン少年兵が、100人 以上も虐殺されたという報道もありました。非人道性という点では、その典型的な例が、前述のタリバーン反乱兵の虐殺です。これらは、一種の「アフガンガ ン・ホロコースト(大虐殺)」ではないでしょうか。勿論、その下手人が北部同盟であることは、明らかでしょう。かつてカブールを制圧した際に、非道を行 い、人心の離反を招いた北部同盟です。
問 題は、北部同盟だけではありません。ラムズフェルド国防長官自身が、有名な「生死を問わず」(ブッシュ大統領)どころか、ラディン氏を殺したいとまで語っ ています。そして、アメリカは、ラディン氏を捕まえたら、通常の法廷で裁かずに、軍事法廷で裁くとし、諸国の批判を招いています。また、北部同盟が投降し たタリバーン兵を恩赦する可能性を見せているのに対し、タ リバン兵がクンドゥズに立てこもっていた際、国防長官は「殺すか捕虜にする」「外国兵〔アラブ兵〕が祖国に帰ることを望まない」などと述べていました。ア フガニスタンのタリバーン兵が投降しようとしたのに対して、アラブ兵は最後まで抵抗しようとしたと伝えられますが、投降しても殺されるなら、当然でしょ う。敢えて抵抗させて殺したいのでしょうか。身の毛のよだつような冷酷さ!
こう考えると、タリバー ン=アルカイーダと北部同盟=アメリカと、どちらが非道な殺人鬼なのか、よくわからなくなってきます。「テロ」集団・アルカイーダを擁護していたからタリ バーンは攻撃されているのですが、タリバーンだけを取って考えると、厳格な規則(による処刑)や女性抑圧はあっても、悪辣非道という非難は、聞いたことが ないからです。逆に、残虐な北部同盟を支援して空爆を行なうアメリカは、アフガン人から見ると、悪辣非道に見えるのではないでしょうか。
今は、11月27日 以来、ドイツのボンで4派の代表が集まって、アフガン代表者会議を開き、タリバーン後の政権構成を協議しています。しかし、北部同盟のラバニ元大統領は、 そこで決着を付けることに反対していますし、パシュトゥン人の代表は僅かです。イタリアで優雅に暮らしていた元国王ザヒル・シャーの支持派(ローマ・グ ループ、パシュトゥン族)を始め、その多くは、内戦下のアフガンを離れて亡命生活をしていた人たちです。そのような勢力の樹立する政権は、傀儡政権と見ら れるのではないでしょうか。南ベトナム政権や、かつてのアフガニスタン戦争に於ける(ソ連の支援した)カルマル政権のように。
実 際、4派の1つキプロス・グループ(ハザラ族)の中心であるヘクマティアル元首相(イスラム党)は、アメリカの攻撃に反対しており、タリバーンと連帯して 反米抗戦するとしており、代表者会議には招待されませんでした。そして、アメリカは傀儡政権を樹立しようとしている、と批判しています。また、北部同盟が パシュトゥン族を取り込むためにNo.2としていた人(ナンガルハル州知事ハジ・アブドル・カディル氏)は、途中で帰国してしまいました。このような状態 で、国民の信を得られるでしょうか。私は、些か懐疑的です。
それ故、タリバーンのイスラム原理主義が大きな痛手を蒙るのは止むを得ないとしても、一方のアメリカの市場原理主義が、全面的に勝利するかどうかは疑問です。タリバーン側が大打撃を受けた今、問題は、アメリカがこのままで完勝する事ができるかどうかでしょう。
私は、そのようなことは 起こらない事に賭けます。ちょうどソ連の共産主義が崩壊した後にも、アメリカの資本主義的自由主義が完勝したと論じた人が大勢いました。私は、それも信じ ませんでした。共産主義は、思想的・理論的にも組織的にも誤まっていたから、その必然的な結果として崩壊したのであり、だからと言って、資本主義的自由主 義が正しいという証明にはならない。資本主義的自由主義に、思想的な問題があるのなら、その問題はやがて浮上して、それに変容を迫るだろう。そう考えたか らです。
タリバーン政権が崩壊したのは、タリバーンにも思想的問題があるので、止むを得ない部分もあるでしょう。しかし、だからと言って、アメリカの問題性が免責されるわけではありません。タリバーン政権の崩壊後に――従って、これからーーアメリカの問題が浮上し、その世界帝国主義に変容を迫るでしょう。
アメリカがパレスチナ国 家の承認へと踏み切らざるを得なかったのは、その第1歩です。そして、さらに為すべき事は、山のようにあります。サウジアラビアからの米軍撤退、イラク制 裁の解除、そして何よりも世界的な環境問題と貧困問題の解決です。しかし、これらは、いずれもアメリカの帝国主義的権益と抵触しますから、痛手を蒙らない 限り、アメリカが真剣に取り組む事はないかもしれません。
アフガン北部の勝利によって、アメリカには、熟考すべき好機が与えられました[xii]。 ここまで限定戦争に辛うじて止めたからこそ、世界各国の支持が得られ、現時点では一応の「勝利」へと至る事が出来た事を忘れてはなりません。ここで鉾を収 めれば、凱歌を挙げ帰国することが出来るでしょう。しかし、「戦勝」に酔って、深追いしたり、まして他国へと戦線を拡大したりすれば、ベトナム戦争のよう な泥沼化が待ち受け、敗戦の憂き目を見ることになるかもしれません。
それ故、最後にもう一度、「追悼 終戦への祈り――アフガニスタン・テロの犠牲者に捧ぐ」(10月8日)に於ける呼びかけを繰り返しておきたいと思います。「ここで止めよ!」。既に、前述の4条件を犯す瀬戸際までアメリカは来ています。戦争気分に酔うアメリカにとって、実は「死線」が眼前に迫っていると思えるのです。
そ れ故、ここがアメリカにとって自らの命運を決する分水嶺に他ならないでしょう。既に同時多発テロの犠牲者の「報復」は、過度に過ぎるほど十分でしょう。こ こで戦争を止め、テロの原因を洞察し、自らを反省して、世界の構造改革にこそ、アメリカは取り組むべきなのです。その賢慮をアメリカが持つでしょうか。
漸く拙論の執筆も再開できそうです。第八部では、この世界の構造改革を主題として論じたいと思っています。
(12月3日)
[i] 実践的行動案内――戦時下の「学問的自由」のための声明
http://homepage2.nifty.com/public-philosophy/academicliberty.htm
[ii] 『アエラ』2001年12月3日号、「タリバーンの反撃はあるのかーー義勇兵が誓う『リベンジ』」、17頁。
[iii] 「オマル師は96年のカブール攻略の前日、カンダハル市内の大モスクにタリバン兵士を招集。予言者ムハンマドから『立ち上がりなさい』とのお告げを夢で聞いたと熱弁を振るい、『神の使命』」としてのカブール奪取を呼びかけたといわれる。」『産経新聞』、2001年11月18日。
[iv] 全く同じ論点にふれているものとして、「次はイラクだ」(ムミア・アブ・ジャマール 2001年11月27日)がある。該当箇所は、
「爆撃に満身創痍のアフガニスタンが一見ようやく平定されたかに見え、空爆も先が見えたきた今、ふたたびイラクが、米国にとっての、お次の悪役候補として浮上してきている。
メディアと軍が一体となってイラクを目の敵にする理由は、あの国が大量破壊兵器を所有していることだという。
ほう、ではどこに、大量破壊兵器を持たぬ国があるのか。
以前、ビル・クリントン前大統領が、このイラク・カードを使おうとして、イラクは大量破壊兵器をもつ世界唯一の国ではないにせよ、それを使ったことのある唯一の国だと主張したことがある。
著名な歴史家で『民衆のアメリカ史』の著者として知られるハワード・ジンは、クリントンのような主張を容認することができるのは歴史に盲目な国民だけだと、述べた。
「彼は、歴史への認識を奪われている国民に向かってのみ、そんなことが言えたのである。合州国は、トルコやイスラエルやインドネシアに大量破壊兵器を供給してきたのであり、それらの国はそれを一般市民に対して用いた。しかし、いちばん罪が重い国は、我々自身のこの国だ。世界のどんな国も、米国ほど多くの大量破壊兵器を所有してはいないし、また米国ほどそれを頻繁に使い、かくも多くの民間人の生命を奪った国はない。我々がそのような兵器を使ったために、広島では数十万人が死に、朝鮮と南ヴェトナムでは数百万が死んだのである」
そういう国が、ほかの国が大量破壊兵器をもっているからといって、その国を脅迫するのだから、その露骨な偽善には驚いてしまう。アジア人とアラブ人はみな呆れていっせいに首を振るだろう。
クリントン二度目の任期に見られた右傾化は、今やブッシュに引き継がれ、前任者の嘘が再利用されている。イラクが米国の臣下(あるいは従属国)の地位に甘んじず、厚かましくも主権国家としてふるまったのを、老ブッシュがきちんと懲らしめることができなかったので、若ブッシュがその始末をつける。それを正当化するのが、「大量破壊兵器」という、古い作り話である。
偽善にさらに輪をかけるのは、イラクの兵器の中に実際に大量破壊兵器が含まれるという事実を米国政府がよく知っていたのは、なぜかということだ。それは、そもそもイラクがより効果的にイラン人を殺せるように、米国の武器が提供されたからである。米国、英国その他の西洋諸国は、そのような武器をイラクにだけでなくイランにも売却することで、莫大な富を築いたのだ。80万人以上の(おそらく100万を超える)男女と子どもを殺害し、8年間続いた戦争で、両国が、そのような恐るべき効率性をもつ武器を使った。米国は、シャー(王)がイランから追放され、故アヤトラ・ホメイニが権力の座についたことに気を悪くしていたので、隣国イラクに対しては、商売人のえびす顔で、もみ手をしながら、武器を持たせ、そそのかしたのである。
きのうの友はきょうの敵。
そして、明日、アフガンに対して続けて行なった爆撃の巻き起こした砂塵が、あの国の硬い冷たい大地にすっかり落ち着くころ、アメリカは、新十字軍をさらにイラクに赴かせようとしている。
欧米諸国が10年間爆撃を続けたイラクに。50万人の非戦闘員が犠牲になったイラクに。有毒廃棄物の捨て場となるまでに爆撃されたイラクに。1991年も、1993年も、1998年も、あるいは今も、イラクを威嚇し、標的として、爆弾を投下することは、イラクの大量破壊兵器とは何の関係もない。
なぜ今日イラクが、格別の悪役にされているのか。
90年代末にイラク空爆を指揮したウィリアム・ルーニー准将が、あからさまにこう言っている。
「イラクがレーダーのスイッチを入れたら、あいつらの地対空ミサイルを吹き飛ばしてやる。彼らは、我々が彼らの国を支配しているのだということを知っている。彼らの領空も我々のものだ。・・・我々が、彼らがどう生きて何を喋るかを指図する。今や、それが、アメリカの偉大さなのだ。これはいいことだ。特に、我々の必要とする石油がたくさんある場合には」(ウィリアム・ブラム『ならず者国家』コモン・カレッジ 2000年 159頁)。
これが真相だ。石油である。
どうしてこれが国際法違反の犯罪ではないだろうか?
(訳 萩谷 良)
[v] 典 型的には、アメリカ軍の犠牲者を出さないためのパウエル・ドクトリンに見る事が出来よう。これは、湾岸戦争の際に、パウエル米統合参謀本部議長が、多くの 犠牲を出したベトナム戦争の教訓から、打ち出した新戦略である。即ち、 地上兵力は逐次投入ではなく、大規模な兵力と装備を集積する。まず圧倒的な航空戦 力で防空システムや交通・通信網を破壊したうえで地上戦に移る。このようにして、目的を限定し、短期終結に導くものである。しかし、湾岸戦争とは条件が異 なっているので、今回の戦争では、初めから放棄されている。
[vi] デイヴィッド・ハルバースタム『ベスト&ブライテスト――栄光と興奮に憑かれて』(朝野輔訳、朝日文庫、上・中・下、1999年)。
[vii] デビッド・ブロッツ、「ブッシュ政権のタカ派キーマン、ウォルフォウィッツ」Slate、2001年10月16日
http://journal.msn.co.jp/articles/nartist2.asp?w=75636
[viii] チャーマーズ・ジョンソン『アメリカ帝国への報復』(鈴木主税訳、集英社、2000年)、原著が2000年に出版されたこの本で、ジョンソンは、アメリカ帝国に「反撃(blow back、報復)」があるだろうとして、「アメリカ帝国が21世 紀に直面する危機」を見事に予見している。即ち、〔ブロー・バックという言葉の〕「その意味するところは、アメリカの国民に秘密にされている政策が意図せ ぬ結果をもたらすことである。『テロリスト』や『麻薬王』や『ならず者国家』や『不法な武器商人』などの有害な行為が毎日のように報道されているが、それ らはかつてのアメリカの活動の『ブローバック』、即ちアメリカの帝国主義的政策に対する報復だとわかる事がしばしばある。」「ある者から見ればテロリスト であっても、別の者から見ると当然ながら自由の闘士であり、いわれのないテロ攻撃が罪のない市民を犠牲にしたとアメリカ政府当局者が非難しても、それはア メリカがかつて帝国主義的な行動を取った事への報復である場合が多い。」「帝国への報復は、報復が報復を呼ぶ破滅的な悪循環におちいりかねない。…従っ て、アフリカのアメリカ大使館に対する攻撃は、本当にビンラーディンが関与していたとすれば、いわれのないテロリズムではなく、報復の一例である。アメリ カは大使館爆破への報復としてスーダンやアフガニスタンの各地点を爆撃するのではなく、サウジアラビアに駐留する大規模かつ挑発的なアメリカ軍の削減また は撤退を検討するべきだったと思われる。」25―28頁。
[ix]田中宇「米英で復活する植民地主義」〔植民地主義の復活を唱える記事の紹介〕
http://tanakanews.com/b1114colony.htm
[x] 【ワシントン27日共同】血まみれタリバン兵の遺体 凄惨な暴動鎮圧
現場無数に撃ち込まれる銃弾。あちこちに転がるタリバン兵の遺体―。米三大ネットワークテレビは二十七日、アフガニスタン北部のマザリシャリフ郊外の捕虜収容所で起きた、タリバンの外国人兵士の暴動鎮圧の際に繰り広げられた生々しい戦闘の模様を一斉に放映した。
二十五日に始まった暴動に対し、北部同盟兵士に加え、米特殊部隊員や米中央情報局(CIA)の工作員も参加。CIA工作員がカメラクルーに対し険しい表情で「撮るな」と怒鳴りつけるなど、現場の緊張は極限に達した。
攻撃側は収容所の包囲網を徐々に狭め、最終的には機関銃を持った戦闘員が収容所内に突入、五百人以上のタリバン兵を次々と射殺していった。
暴動鎮圧後の収容所内は、血まみれのタリバン兵の死体があちこちに横たわる。米メディアが「これまでのアフガニスタンの軍事作戦で最も血塗られた場面」(ABCテレビ)とコメントするほど凄惨(せいさん)なシーンとなった。
(了) 11/28> http://www.kyodo.co.jp/kyodonews/2001/revenge/news/20011128-305.html
[xi]タリバーンに米国人青年がいた 7日間地下室に潜み救出
アフガニスタン北部マザリシャリフ近郊の捕虜収容所で先月下旬に起きたタリバーン兵の暴動事件で、生き残った20歳の米国人タリバーン兵ジョン・ウォーカーさんが、救出までの模様を明らかにした。
米CNNテレビなどが2日、伝えたところによると、今回の暴動では、ウォーカーさ んは当初、投降するつもりでいたが、タリバーン兵の一人が手りゅう弾を投げて爆発させたため、北部同盟兵士側と銃撃戦になったという。この銃撃戦で右足を 撃たれ、他のタリバーン兵とともに地下室に逃げ込み、7日間、何も食べずに潜んでいた。この間、地下室にガソリンをまかれて火を付けられたり、水を流し込 まれたりし、さらに何個かの手りゅう弾も放り込まれた。地下室はタリバーン兵の死体でいっぱいだったという。
暴動は11月25日に起きた。数百人のタリバーン兵捕虜のうち、生き残って降伏したのはわずか約80人で、あとは全員、殺害されたという。暴動では、米中央情報局(CIA)の作戦部員1人も巻き込まれて死亡した。
ウォーカーさんは現在、米特殊部隊の監視下で治療を受けている。
ウォーカーさんは16歳の時にイスラム教に改宗。18歳で故郷を離れ、イエメンに渡りアラビア語を勉強したという。その後、パキスタンに移り住んでイスラムを学び、ここでタリバーン支持者らと接触してタリバーンに傾倒した。
その後、カブールに行き、支持者らの勧めで半年前にタリバーン部隊に加わり、アフガン国内の訓練キャンプでカラシニコフ銃の撃ち方などを教わったという。
米軍が空爆を始めた時、クンドゥズまで約160キロを徒歩で逃げた。そこで3千人以上のタリバーン兵とともに捕虜として捕らわれ、マザリシャリフ近郊の収容所に入れられたという。(23:27)
http://www.asahi.com/international/update/1203/019.html
[xii] ク リントン前大統領の演説を契機に、漸くアメリカでも、同時多発テロの原因を自らの対外政策に求める見解が現れてきた。特に、「有力シンクタンクの戦略国際 問題研究所(CSIS)は、テロを封じ込めるための提言書「勝つために」を27日に発表するが、この中で「テロが根づき、増大する条件」が米国の政策にも あったことを認め、途上国援助や中東政策など米外交政策を根本から見直すことを提案」している。
http://www.yomiuri.co.jp/attack/1127_08.htm