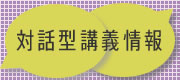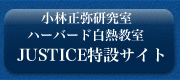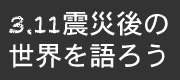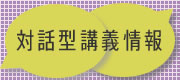

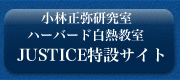

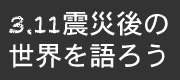
メーリングリスト
検索
リンク
重要リンク
- 小林正弥研究室Facebook
- 対話型公共哲学TV
- 公共研究センター(旧:地球環境福祉研究センター)
- 持続可能な福祉社会に向けた公共研究拠点
- 小林正弥研究室
- 地球平和公共ネットワーク
- 活動記録(旧サイト)
« 山脇直司著『経済の倫理学』をめぐって | Home | グローカル公共哲学の射程-新自由主義に抗して »
Posted: admin on 10:27 pm | Michael Sandel, 書籍・雑誌情報(Books, Journals, Magazines), 論文・書評・所感など
山脇 直司
去る3月7日から3日間、アメリカのハーバードで、「地球時代の公共哲学(Public Philosophy in the Age of Globalization)」と題するフォーラムが開かれた。そもそも公共哲学(パブリック・フィロソフィ)とは、特に1980年代以降、北米を中心に使われ始めた言葉である。そして現在その最も有力な提唱者が、マイケル・サンデル現ハーバード大学政治学部(ケネディ・スクール)教授であり、1982年にロールズ『正義論』の批判者として学界に華々しくデビューした彼は、1996年に著わした『民主主義とその不足感』において、個人の権利追求を優先するリベラリズムの公共哲学に抗し、人々の自治に基づく共通善の実現を追求するリパブリカニズム(共和主義)の公共哲学を唱え、今日に至っている[i]。その彼と、京都を拠点としてここ二年にわたり多様な観点から幾多の公共哲学研究会を主催している京都フォーラム・将来世代総合研究所長の金泰昌氏が、チャールズ・テイラー氏やWm・セオドア・ドバリー氏といった世界的に著名な学者やハーバード大学政治学部の教員や院生を招き、グローバルな観点からの公共哲学の可能性について議論を試みようというのが今回のフォーラムの趣旨であった。そして日本からは、大沼保昭東京大学大学院法学政治学研究科教授と東大大学院総合文化研究科に所属している筆者が提題者として、また小林正弥千葉大学法経学助教授と金鳳珍北九州大学助教授、および日本で学んでいる大学院生6名が討論者として、それぞれこのフォーラムに参加した。筆者はすでに昨年の秋に、東大駒場キャンパスで、このような国際公共哲学をめぐるフォーラムを、将来世代国際財団の援助も得て、ヨーロッパ、香港、韓国などから学者を招き主催した[ii]が、今回は、一体北米の学者がグローバルなレヴェルでどのような公共哲学を構想するのか大いに関心を抱いて、このフォーラムに臨んだ。以下では、その模様と参加者の一人として色々感じたことをまとめてみたい。
奇しくもスーパー・チューズと重なった3月7日の初日は、ドバリー氏とテイラー氏の提題をめぐって、活発な議論が行われた。アメリカにおける朱子学の大家として名高いドバリー氏は、約20年前に朱子学とリベラリズムの親近性を論じて注目を浴びた学者であるが、最近ではむしろ儒教を一つのコミュニタリアニズムとみなして、その現代的意義を論じる傾向が強まっている[iii]。そこでまず、彼が一体どのような問題提起を行うのかに、参加者の関心が集まった。その彼は、朱子学が仏教やエスノセントリズムにはない普遍主義的倫理を持ち、しかもその理気思想が宇宙論的射程を持つが故に、地球的規模でのエコロジー危機に対処しうる公共哲学になりうることを指摘した。そしてさらに、儒教には「人民による政治」という伝統はないものの、統治者が常に民意を汲み取り「人民のための政治」を行うという意味での公共性の伝統が存在している点を強調した。これに対し、金泰昌氏から儒教が人間存在の私的側面を過度に軽視しているのではないかという疑問が、またインド系の政治哲学者メータ準教授から、制度との関わりにおける儒教の難点についての疑問が出されたが、ドバリー氏は、侍文化によって歪められた日本の儒教・朱子学と異なり、本来の儒教・朱子学には人権思想や制度変革思想が存在することを改めて力説した。
こうした見解はしかし、一時期わが国の知識人に影響を与えた丸山真男の朱子学観と大きく異なるものである。この点をついた小林氏の質問に答えて、案の定、ドバリー氏は丸山の朱子学観は西洋中心主義的発想に由来する偏見に過ぎないと一蹴した。だが、小林氏も指摘するように、丸山の朱子学観がいかに不正確だったとはいえ、果たしてドバリー氏が強調するほど朱子学が個の自覚について肯定的役割を担いうるかという問題は、今後も争点であり続けるであろう。なお筆者は、かつては悪しき混交主義とみなされがちであった「キリスト教の儒教化や儒教のキリスト教化」も、たとえば総人口の約30パーセントをキリスト教徒が占める韓国にみられるように、これからは積極的に肯定されていくべき現象ではないかと質問したが、ドバリー氏の答えは然りであった。
続いての提題は、今おそらく世界で最も注目されている哲学者の一人、チャールズ・テイラー氏によるものであった。彼は、特に近代のリベラリズムが規範的一元論に立脚していると指摘しつつ、文化の「差異」や「多様性」を擁護してきた論者として名高いが、このフォーラムでは、そうした欧米の一元論が「進歩」の名の下に異文化を支配するイデオロギーともなった点を批判し、今改めて、地球的規模で多様な文化が相互に学び尊重し合うことの意義を説いた。これに対し、単に文化の多元性を謳うだけで十分なのかという質問がハーバードの若い学者から出され、またこのセッションだけ同席したベンハビブ教授から、新自由主義の名で蔓延しているグローバル・キャピタリズムに対抗するための自律と連帯の論理がそれだけでは生まれないのではないかという疑問も提出された。それに対し、テイラー氏から、リオタールのいう「大きな物語」が終焉した今日では、地球規模での文化の多元性の承認こそ重要、という答え以上のものを引き出せなかったのは、少々物足りなかった。とはいえ筆者には、そうした慎重な答えの中には、北米に住むリベラルなカトリック教徒でありながら、いわゆるキリスト教文化の独善に陥らず、イスラム文化や他の諸文化と真に対話可能な社会哲学を模索しようとする彼の真摯な姿勢が反映されているように、思えてならない。
そしてフォーラム二日目の最初に、このような文明間対話の重要性を人権論という観点から唱えたのが、国際法学者の大沼氏であった。大沼氏は、グローバルなレヴェルで人権問題を考えるためには、西欧中心主義や国家中心主義を乗り越える比較文明論的アプローチが不可欠とみなしつつ、それが単なる抽象論に陥らないよう、すでに合意が出来上がっている具体的な人権条約などに即しつつ議論を深めていくことが必要と説いた。これまで筆者は、同じ東京大学に籍を置きながらもキャンパスを異にしているため、大沼氏の見解を直に聴くことができなかったのであるが、これを機会に、国際公共哲学という視点の下、国際法学と哲学との対話を身近なところから始めなければと痛感した次第である。
次いで、いよいよ筆者の提題となった。筆者は、公共性という概念が社会諸科学を貫くトランス・ディシプリンであることを確認しつつ、公共哲学は様々な公私の領域で生活する人間の在り方を主題化する必要があり、そのためには、均質な理性的主体を想定するロールズやハーバーマス的アプローチよりも、多様な「自己ー他者」了解をキー・コンセプトにするテイラーやサンデルのアプローチの方がプロミシングであるが、さらにその「自己ー他者」論を国家を超えたトランス・ナショナルな公共性理解にまで及ぼすことが必要なことを唱えた[ⅳ]。そして、近代西欧の偏った進歩主義的社会思想やハーバード大教授でもあるハンチントンが懸念する「文明の衝突」論を乗り越えるためには、比較社会思想のような学問をインターナショナルなレヴェルで発展させ、またかつてピコ・デッラ・ミランドーラが夢見たけれども実現しなかった「文明間の哲学的対話」を今こそ促進させていく必要を説いた。実際、筆者はヨーロッパの社会思想史・社会哲学についてこれまで書物を著してきたが、そもそもそれはヨーロッパの諸思想を賞賛するためではなく、むしろそれらをグローバルなレヴェルで相対化するためである。
このような主張に対し、サンデル氏とテイラー氏が強い共感の意を表してくれたことに、筆者は大いに勇気づけられた思いがする。そしてまたここで、筆者が比較社会思想研究の恒例として汎神論と多元的民主主義思想を兼ね備えたスピノザを挙げたことに対して、サンデル、テイラー両氏とも、スピノザが東西思想の架け橋となりうる哲学者であろうと格別の関心を示したことを、特記しておきたい。なおその他、日本にも住んだ経験があるというモーガン助教授から、トランス・ナショナルな公共空間で語り合う言語は何であるべきかという質問が出たのに対し、筆者は現時点では英語優先とならざるを得ないだろうが、それはアングロ・アメリカ文化を優先させることではない、と応答した。実際、アングロ・アメリカ文化に染まることなく、国際コミュニケーションの手段として英語を使用するという根本姿勢が、今後トランス・ナショナルな公共哲学を発展させる上でますます必要となろう。
提題に基づいての討論はこの二日目までであったが、そのトリを務めたのは、サンデル氏であった。彼は、自らに貼られたコミュニタリアンというレッテルについての誤解を解くべく、自分がこのレッテルを受け入れるとすれば、それは英米で支配的なリベラリズムが暗黙のうちに想定している「負荷なき自己」を批判し、公共性の担い手としての「自己」が、何らかの形でコミュニティに規定されていることを理解するという意味においてであって、単一的な善やコミュニティの多数派主義を擁護する意味では決してないことをまず明言した。その上で、このフォーラムのテーマであるグローバルな公共哲学の可能性について、それはグローバル・ハブリック・フィロソフィーズという複数形でのみ存在可能であるのに、現在の経済グローバリズムはむしろその可能性を蝕んでおり、そうした現下のグローバル・キャピタリズムの横行に対し、自分としては、ポスト・政教分離社会を前提として「聖なるもの」と「公共性」の再結合の可能性を、多様な関連から論考していきたいと締めくくった。
このサンデル氏の提題は、これまで主にアメリカ社会について論じてきた彼の新たな思想的発展と受け取れる。この注目すべき提題に対し、金泰昌氏から、リベラリズムが確立していない東アジア社会においては、リベラリズム批判は藁人形を打つようなものであり、また聖なるものという概念も悪用されがちであるとの疑問が出されたが、その点についてサンデル氏は同意した。筆者からみれば、この両者のずれは、両者が生きている社会的伝統の違いを考慮すれば当然であり、そうしたずれを十分踏まえながら、いかにして国際公共哲学としての文明間対話を遂行するかが今後の大きな課題となろう。そしてそのためには、欧米思想を研究する日本の学者も、できるだけ早く蕃書調所的なメンタリティを克服して、応答・発信型のメンタリティに移行しなければならないことは言うまでもない。
そして、最終日三日目の午前中に行われた大学院生とテイラー、サンデル両氏との討論会は、まさに若い学者がそうした新しいメンタリティを育むにふさわしい内容のものとなった。院生の内訳は、東大総合文化研究科に所属する日本人4 名(男女2名)と中国人1名、一橋大学所属で現在カナダで学んでいる1名の計6名であったが、両氏の政治思想に精通している彼(彼女)らは、ひるむことなく鋭い質問を投げかけ、それに全力で答えたテイラー、サンデル両氏も、内容の濃い討論に大変満足げであった。筆者としては、この討論に参加した院生達が、応答・発信型の研究を今後大いに推進してくれることを期待している。
かくして、大物学者を迎えてのハーバード・フォーラムは幕を閉じた。国際公共哲学が今後可能であるとすれば、それは単一の価値や哲学に基づいて展開されるべきではなく、多様な価値や哲学を尊重しつつ、文明間対話という形で遂行されなければならない。これが、細部においては見解の相違もあったこのフォーラムで最終的に確認されたミニマム・コンセンサスと言えるだろう。
[i]日本語で読めるサンデル氏の著作としては、『自由主義と正義の限界』(菊地理夫訳、三嶺書房、1999年)や、「公共哲学を求めて」中野剛充訳(『思想』1999年10月号、岩波書店、34-72頁)が挙げられる。
[ii]国際公共哲学・駒場フォーラムの模様については、「東京大学・教養学部報」、1999年12月1日号の第2面を参照して頂ければ幸いである。
[iii] ドバリーの著作としては、『朱子学と自由の伝統』(山口久和訳、平凡社、1987年 但し絶版)が訳されているが、最近の彼は、Asian Value and Human Rights : a Confusian Communitarian Perspective, Havard University Press, 1998を著し、儒教をリベラリズムよりコミュニタリアニズムに引き付け、その意義を説いている。
[iv] なお、このような筆者の見解について、昨年出した拙著『新社会哲学宣言』(創文社、1999年)をも参照して頂ければ幸いである。